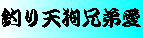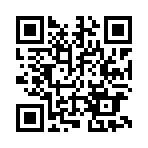2008年03月17日
メバル3型を追う
毎度毎度のメバル話で恐縮ですが,,,。
当地のメバルは回復中期に突入し,今の彼らにとって,労なく口に入るといえども栄養価の低いアミ食いは,もはや無意味。
今,底に貼り付いているのは,今期回復接岸が遅れた茶メのヤセ♀。いくら大きくても味が乗らず,釣る価値なし。
例年今頃は,底層アミから海藻由来の数種のエサへ,すなわち平面から三次元的に徐々に摂餌範囲を広げていくのだが,今年はこれが少ないとみえ,いきなり浮いて暴れている。
春ここしばらくの最初のキーは「風」。堤防や岬先端などの「潮」の青メ狙いでは1発でオワリ→オカズになりませぬ。それに,青メの旬は夏でござる。これまた釣らんでもよかろう。
で,最近私が追いかけているのは,アミ食いを卒業していよいよ回復調子にある茶メの♂のみ。今後どこへ行くかはわかったもんではない浮浪児たちではあるが,今,これが一番旨いメバルだ。
******************************
京都大学の中坊および甲斐という魚類学の先生と仲間たちが,長いこと1種類とされてきた「メバル」を赤(A)・黒(もしくは青,B)・茶(C)の3つの型に分け,胸びれの軟条数の違い(A:15,B:16,C:17)を発見し,遺伝子的にも検証されて,近々,3つの別種として報告されるであろう,というのが最近の当学会で言うところの“メバルビジネス”の展開状況であるが,そもそもこの研究の発端が“釣り人の観察およびその報告”から来ているところがヨイではないか。
ほぼ周年メバルを追っかけるメバル釣り師が世にどれほどいるかは知らないが,数知れぬほどのメバルを,いろんなところで釣っては眺め,どうもやっぱりコレとアレは全然違うよなあ,といった「全体観」,あるいは多くの数を見た経験から生まれる「直感」,というようなものによって,釣り人の疑問は科学の受け皿を得て解析へと向けられた。
むろん,種の分類に限らず,釣りというものそれ自体が,科学と不可分の関係にあることは言うをまたない。というより,自然界が「合理的」にできている以上,それを相手にする“釣り”は,ほぼ科学である言ってよい。そして何よりも,“想像力”がこれを支えている。このしくみが総合的に作用する様を称して“釣りは直感だ”,と言ったりもする。
では科学とはナニカといえば,けして学者が実験データを集積・解析することだけがそうなのではなく,老練な漁師の神業も,中国4千年の整体術や漢方も,想えば膨大な時間と技の継承をつぎ込んだ大きなひとつの実験であった。前回ログでご紹介した「魚付き林」も然り。
“こうしたら,こうなる”,“なぜかは知らんがコレがいい”というような定性的な事実の積み重ねを,より合理的かつシンプルに解説し,より客観性および再現性を付与する補助的役割を持つのが,いわゆる科学である。
従って,世界はすべからく科学性に満ちていると言えるし,また逆から見れば,全てが芸術性を帯びていると言ってよい。これはけして矛盾ではない。
さて,過去ログ「メバルの3型とその味わい」以来,ここであらためて「メバルの3型」に言及するのは,ここ2ヶ月ばかりのメバルの型別の釣れ方を通して,“味”以外の3型それぞれの特徴が,少し見えてきたような気がしたからだ。
******************************
既に過去ログ「境港発メバル事情」シリーズでも述べ来たように,2007秋から2008冬のメバルの行動は,例年に比べて実に変則的であった。
接岸せずに沖で繁殖行動を終えてしまった茶メの♂が回復接岸を開始したのが,ちょうど1ヶ月前の2月上旬であり,このあと3週間ほど2月下旬までは,ごく底層を這うような群れを発生する1㎝ほどの半透明の沿岸性アミ類に餌付いていた。
2月も下旬あたりからは北西の風に混じって南~南西の風の頻度が高まったことに加え,風・雨次第で散発的ながら海水温も上昇したため,例年並みに表層に浮く小メバルが大量に発生したが,今年はこれに混じって青や,茶の23㎝前後も浮き始め,回復途上ゆえに体型にはバラツキがみられるものの,順調に推移している。
そもそもこの時期の当場所に小メバルが沸くのは毎年のことであるが,良型のメバルが浮いたのは過去4年間で初めてのこと。変則的には違いない。
ところが,全部が浮いたわけではなかった。
茶メ♂のアミ食いがほぼ終了した3月中旬,同じ場所の同じ種型であっても底に貼り付いているのと浮いているのがおり,底に付いているのは茶メの♀が主体で♂は混じる程度。♀の場合は2月に底に付いていた♂よりも一回り大型の25㎝前後。これは沖で産卵を終えて♂の後から接岸したもので,むろん痩せている。回復度合いが先に接岸した♂より遅れているので,今の青メや茶メ♂のようにエサを追いかけ回して摂る体力・筋力は,まだない。
一方,今浮いてるヤツはどうかといえば,体の肛門から後方はまだ痩せているものの,肩から中程にかけてはプックラと盛り上がっていて食味も悪くない。全て♂である。もし♀が浮くとしたら,まだ先であろうと推測している。
ま,これらは今後の狙い方に関わることなので,置いておくとして,,,。
******************************
【 出来事 その1 】今期の浮きメバルに関する疑問
この一連の現象のうち,回復接岸した茶メバルの♂は,初期には「追わなくても捕食できるエサ」ここではアミ類を主体に食べていたが,体力が回復するに伴い,徐々に表層のエサであるシラス等小魚類も追い始めた。この“徐々に”というところがポイントで,つまり,潮が表層に小魚を運んできても,これを追えるだけの体力がつくまでは茶メは浮くことをせず,青メのみがこれを追っていたのが2月下旬あたり。そして3月に入り,コンスタントに表層で釣れるようになったメバルを見ると,青と茶が混じるようになっていた,というわけなのだ。
こんなことを喋っていると,巷でよく聞くコメントは,「中・低層の茶,中・表層を動き回る青,その違いでしょうね。」というもの。私もかつてはそのように思っていたのだが,実際には必ずしもそうではないようなのだ。
“青メは表層”,というのは,たしかにわかりやすい。この前の2週間,底層で20~25㎝程度の茶メを釣っていたときでも,合間に強い潮が入れ込んでくると,表層で同サイズの青メが単発的に釣れてはいたからだ。しかも青メは,底層には潜らない。エサを伴う潮と共にワッと来てサッと去る。同じ場所に長居をしない,込み潮の使者だ。
ちなみに3型と釣れ方の全体的な傾向を言うと,
2月上旬から下旬にかけて,極めて底層にへばりついていて釣れていたのは,ほとんどが茶メで赤メが少し。青メはというと,既に述べたとおり2月中旬あたりから表層でチビメバルのライズが続く中,潮が強く利いてきたときのほんの短時間だけ回遊してきてバタバタッと釣れて終わりなので,型は良くてもアテにはならぬ,という状況であった。
それが,2月下旬頃から表層でコンスタントに釣れるようになって以来,赤メは瀬を中心に底にへばりついたままであったが,表層は青メだとばかり思っていた中に同型の茶メが混じり始めたのである。というより,その後,日を追うごとに茶メの割合は増えていき,今や表層付近で釣れるメバルのほどんどが茶メという状態なのだ。
余談であるが,茶メと青メは,生きているときの青メの背が見る角度によって緑色に底光りすることで判断できるわけだが,漁場によっては外見からは判断がつきにくい場合がある。また,小型であるほど見分けがつきにくい。かといって,胸びれの筋をいちいち数えてもいられない。
が,これを持ち帰って下処理課程で鱗を取って眺めてみると,これはハッキリする。
青メの方は,鱗を引いた後の肌合いが,ひげそり後のような寒色なのだ。そして,過去ログ「塩煮の世界」で述べたとおり,調理したときに,その差は更に明確になる。
茶と青を比較すると,茶メの身はしっとりしてコクがあるのに対し青メのそれは堅くパラパラしており味が薄い。茶メの皮は薄くて身との一体感があるのに対して,青メのそれは,加熱すると,身から離れようとするがごとくプリンと堅いのである。
それぞれに活かしようであるが,かつて過去ログ「メバルの3型とその味覚」で,青メの大判は夏に薄造りで,皮の湯引きを添えて食うに限る,と申し上げたのは,この特性にある。
話を戻し,
「ワカランことがあればいろんなかたちで触ってみる」,というのが基本であるから,次は胃内容物の調査などに突入していくのであるが,これによってようやく,メバルの型とそれらの行動特性,および棲み分けのメカニズムの一端が,見えたような結果となったのだ。
たとえば一昨日釣れたのは茶メが2尾に青メが1尾。いずれも23㎝前後で型揃い。15分の間に,同じ道具で,同じ立ち位置から狙った表層付近の,同じ層の同じ誘いで釣れてきたものだ。
当然のことながら,胃内容も同様と思っていたのだが,さにあらず。
結果は,青メの胃の9割以上が3㎝ほどのシラスおよび3~5㎝ほどのアイナメのなど(アイナメの稚仔魚期はイワシ類のような外観で表層生活をしている)で占められていたのに対し,茶メの胃内容は,水温上昇に伴って2㎝ほどまで成長した低層性のアミが7割で,青メの食っていたような小魚類は3割程度にとどまっていたのである。
横にいた青年二人に,釣り方を教えるから胃袋だけくれと頼んで調べてみたのだが,調べた青メ5尾,茶メ7尾とも,全て同様の傾向であった。
更に先日,もっと興味深いことがあって,いよいよ3型の特性が浮き彫りとなった。
******************************
【 出来事 その2 】 場所による同種型の差違
私は外灯のある漁場で,小メバルがライズする灯りの中心部に対して潮下の離れた暗がり表層下で23㎝前後を釣っていた。先週以来続いていた浮きメバルも潮回りが進むにつれて時合いが短くなりかつ散漫な釣れ方になっていたこともあり,もう一人の青年は少し離れたテトラ付近の暗い斜面を探って20~23㎝ほどのを3尾釣って戻った。コチラで釣ったのとアチラで釣ったの。その距離はテトラをはさんだ両側20m範囲。両方とも茶メの同サイズ。
しかしこれが,違うのである。
テトラ周りの茶メは,体に対して目が大きく,回復してきているとはいえ全体的に痩せ型で,コチラの表層茶メは体高があり相対的に目が小さく,痩せているのは体の後方のみ。胃内容はテトラ周りの斜面がアミ類であるのに対し,コチラはアミ7割+小魚3割でこのところの傾向と変わらず。
この時,これまで境港から島根半島で釣ってきたメバルの種型,形態的特徴,釣れ方,胃内容物,等々の記憶が,走馬燈のように脳裏を走った。
たとえば同じ茶メでも,半島の褐藻群落の間から釣れてくる引きの強いやつ。これは,お前はカエルか,というくらい相対的に目が大きく発達している。同じ場所で釣れる赤メでは,あのような違いは見られなかった。あれは何だったのか。
そして,ほとんど隣接した漁場であるにもかかわらず,エサが違い,外部形態(体型や各部の比率)まで違う茶メがいる。どうしてテトラ斜面の茶メは,回復途上にあるのだから,ひょいと20mばかり移動して,なぜ,もっと栄養のある小魚類を捕食に行かないのか。しかも,外観的な違いは,同時期同場所の赤メや青メでは見られず,なぜか茶メだけに起こっている。
******************************
さて,丁寧に整理してみよう
①今期接岸した茶メは,初期には底層の沿岸性アミ類を専食していたが,回復が進むにつれて,表層付近の小魚類に餌付くようになった。底層で釣れていたときには全てアミ類であったのに対し,青メと混じりで釣れ始めたときの胃内容物は,アミ7割,小魚3割となっていた。そして,時期が進むに従い,アミの比率は減り,小魚の割合が増えていった。
②同時期同場所の表層で,小魚類に餌付いていた青メは,回復期の茶メがまだ底層に貼り付いていた時期から,強い潮と共に来遊し,表層で短時間単発的に釣れていた。そして,胃内容物は,9割以上がシラスやアイナメの稚仔魚であって,アミ類はごくわずかであった。なお,青メは底層で釣れることはなかった。
③同時期同場所での底層では,茶メの回復接岸が始まった段階から赤メが釣れていたが,その後,茶メが表層に浮くようになっても,赤メが浮くことはなかった。胃内容物は,底層のアミ類に加え,海藻や岩礁に由来する固着性甲殻類(ヨコエビ類)であった。なお,この傾向は,茶メが浮いて底層で釣れなくなった後も,変化することはなかった。
④茶メが表層に浮いた漁場に隣接するテトラ帯の斜面漁場で同日に釣れた茶メは,同サイズであっても相対的に目が大きく,回復の度合いが遅いように見られた。なお,隣接するテトラ帯から目の大きい茶メが移動してきて表層の茶メに混じって釣れることはなかった。
⑤島根半島の褐藻帯から釣れる茶メは,今回観察されたテトラ帯の茶メよりも,更に相対的に目が大きい。ただし,同場所同時期に釣れる赤メでは,そのような差違は見られなかった。
*******************************
【 メバル3型にみられた行動・棲み分け・生活様式の違い 】
以上の事実から導き出される結論を要約すると,次のようになる。
● 赤メは海藻や瀬(構造物)に対する依存度が最も高く,中~低層の海藻や構造物に密接して生活圏を形成し,その範囲のエサを摂っている。形態的差違は少ない。
● 青メは潮に対する依存度が最も高く,表~中層,もしくは一時的に海藻や構造物にも生活圏を形成し,その範囲のエサを摂っている。形態的差違は少ない。
● 茶メは表・中・低層,構造物等,餌を採る手段を最も柔軟かつ合理的に選んでおり,状況に応じて生活圏を変える。赤メのように構造物に強くこだわるグループもいれば,こだわらないで動き回るグループもいる。そして,それら環境に応じて形態的差違が大きいのが特徴である。
● 更に茶メでは,繁殖後の回復に伴い,食べやすい底層性のアミから追いかけて食べる表層性の小魚類に向けて徐々に移行していく。つまり,回復期における茶メの摂餌形態は,個体の能力に応じて徐々に合理的な方向に変化することが推測される。なお,赤メや青メでは,そのような変化はみられなかった。
● 結果として,赤と青は生活圏レベルで完全に棲み分けているが,茶は成長もしくは回復の過程で両方の生活圏に参加している。
ここまでは,わかった。
が,,,
【 悩みは尽きぬ 】
しかし生じる更なる疑問は,,,
ここで得られた事実を見る限り,たしかに茶メはいかようにも摂餌行動およびそれに応じた生活圏を変えている,のであるが,では結果としてその生活様式が外部形態の差違に現れるのは,卵から老成魚までの,どの段階で生活様式が“染みついた”場合にそうなるのか。ということ。
まず,小メバルが毎年一定の場所で湧くところをみると,未成熟期に形質が固定されるわけではあるまい。ここから成長に伴い,それぞれに何らかの出来事があり,それぞれの生活様式およびそれに応じた形態になっていくと推測されるのだが,
しかしそのメバルは,ずっとそこにいて成長するわけではない。季節に応じた離岸・接岸がある。
2週間前には底でエサを摂っていたので眼が大きかったですけど,今週からは表層に浮いてるので眼は小さくなりました,などという器用なしくみのハズがないし,回復期の体型でさえ,いくらエサを食いまくったとて,太り具合でさえ,差が出てくるのに1週間はかかろう。
そうなると,先述した,底のアミ食いメバルとその後に釣れた表層アミ+小魚を食っていたメバルは,全く別の群れなのであろうか。今は,表層茶メが釣れ始めると同時に底層茶メがいなくなったことから,回復過程で底から表へエサを変えたものと解釈しているのだが,たしかに底と表層の茶メの体型は,別の群れかと思うほどに違っているのである。
接岸過程で変わる環境やエサに合わせて態を変える?
つまり,接岸した茶メの,場所による外部形態の差違は,毎年の繁殖~回復接岸過程で形成される???
そんな短期間に?
そしてもうひとつ気になることは,「進化」の問題。
これら3型が,その生活形態において,一部は重なるけれども異なる行動生態,あるいは生存戦略をもってサバイバルしていると。特に茶メは行動に伴い様々に外観の態を変えるとすると,それでは「進化」の過程として,赤・青・茶の,どれがどれに分化していったのか。
固定したところから多様化したのか。逆に多様の中から固定化していったのか。そして,今現在,どの課程にあるのか。一般進化論でふつうに考えれば順応性の高いものから派生して固定化し,遺伝的に隔絶されていくと考えがちだが,そうなると胸びれの条数との関係はどう解釈できるのか。茶17本→赤15本,青16本。軟条が少なくなるメリットなんてものは考えにくいし,これは退化???。 あるいは逆に,赤・青→茶???。
魚類学のレポートでは遺伝的にそれぞれ分離しているというのだが,実際に釣ってみると,3型としての外観的要件を満たしていても,その生活において,青のようにふるまう茶や,赤のように暮らす茶が存在することも,また事実。分化する前の昔の名残が生活に出ている???。 ワカランなあ~,はははのは。
でも,感触としては,形態を柔軟に変える「茶」の謎を追っかけること。これがこのテーマを紐解くカギになるのではないかと思っている。
といったようなことで,アレコレ悩ましいですね。
メバルの世界が奥深いのは釣りだけではない。こうなってくると,もうあくまでも学術的ロマンですな。我々人間の第4の欲求,すなわち“知りたい”というヤツだ。
******************************
【 メバル3型とワタクシ 】
でも,それよりなによりも,これまで過去ログでも述べ来たとおり,メバル3型には明らかに食味上の大きい違いがあるということが当方最大の関心事。こちらのほうが,やはり優先されるのです。
従って,メバル3型とワタクシの直接的な関係は,
ひとつの海から,
① 3型ごとに,それぞれ一番旨い時期に一番旨いサイズを選んで釣る。
② 混在している中から3型を釣り分ける。
③ そのための見識と技術を体得する。
というようなことで,これすなわちメバル釣りにおける「オカズ釣り道」の極めるべき道の果てであろうと思う次第。
こんなことが想定可能なのも,同場所で同時に3次元的に漁場を探れるメバルの疑似餌釣り=メバリング,ならではのこと。いろいろ使えてスバラシイですね。
ウエカツは所詮は食い気かよ →そのとおり。
食で自然界とつながってこその自分だ。
だからこそ,個として必要量を獲り,必要以上を獲らない。またそれが続けられるようにモノゴトを追求するし,それをわかった上で釣り方を変え,漁獲圧を調節する。
数やサイズを他人と競うような風潮とは無縁。相手はサカナだ。そして自分だ。
いずれにせよこの3型を追うテーマはオモシロイので,また何かわかってきたら続報いたしましょう。釣技の向上にもたいへん役立ちますしね。
今日のところは,これでおしまい!
当地のメバルは回復中期に突入し,今の彼らにとって,労なく口に入るといえども栄養価の低いアミ食いは,もはや無意味。
今,底に貼り付いているのは,今期回復接岸が遅れた茶メのヤセ♀。いくら大きくても味が乗らず,釣る価値なし。
例年今頃は,底層アミから海藻由来の数種のエサへ,すなわち平面から三次元的に徐々に摂餌範囲を広げていくのだが,今年はこれが少ないとみえ,いきなり浮いて暴れている。
春ここしばらくの最初のキーは「風」。堤防や岬先端などの「潮」の青メ狙いでは1発でオワリ→オカズになりませぬ。それに,青メの旬は夏でござる。これまた釣らんでもよかろう。
で,最近私が追いかけているのは,アミ食いを卒業していよいよ回復調子にある茶メの♂のみ。今後どこへ行くかはわかったもんではない浮浪児たちではあるが,今,これが一番旨いメバルだ。
******************************
京都大学の中坊および甲斐という魚類学の先生と仲間たちが,長いこと1種類とされてきた「メバル」を赤(A)・黒(もしくは青,B)・茶(C)の3つの型に分け,胸びれの軟条数の違い(A:15,B:16,C:17)を発見し,遺伝子的にも検証されて,近々,3つの別種として報告されるであろう,というのが最近の当学会で言うところの“メバルビジネス”の展開状況であるが,そもそもこの研究の発端が“釣り人の観察およびその報告”から来ているところがヨイではないか。
ほぼ周年メバルを追っかけるメバル釣り師が世にどれほどいるかは知らないが,数知れぬほどのメバルを,いろんなところで釣っては眺め,どうもやっぱりコレとアレは全然違うよなあ,といった「全体観」,あるいは多くの数を見た経験から生まれる「直感」,というようなものによって,釣り人の疑問は科学の受け皿を得て解析へと向けられた。
むろん,種の分類に限らず,釣りというものそれ自体が,科学と不可分の関係にあることは言うをまたない。というより,自然界が「合理的」にできている以上,それを相手にする“釣り”は,ほぼ科学である言ってよい。そして何よりも,“想像力”がこれを支えている。このしくみが総合的に作用する様を称して“釣りは直感だ”,と言ったりもする。
では科学とはナニカといえば,けして学者が実験データを集積・解析することだけがそうなのではなく,老練な漁師の神業も,中国4千年の整体術や漢方も,想えば膨大な時間と技の継承をつぎ込んだ大きなひとつの実験であった。前回ログでご紹介した「魚付き林」も然り。
“こうしたら,こうなる”,“なぜかは知らんがコレがいい”というような定性的な事実の積み重ねを,より合理的かつシンプルに解説し,より客観性および再現性を付与する補助的役割を持つのが,いわゆる科学である。
従って,世界はすべからく科学性に満ちていると言えるし,また逆から見れば,全てが芸術性を帯びていると言ってよい。これはけして矛盾ではない。
さて,過去ログ「メバルの3型とその味わい」以来,ここであらためて「メバルの3型」に言及するのは,ここ2ヶ月ばかりのメバルの型別の釣れ方を通して,“味”以外の3型それぞれの特徴が,少し見えてきたような気がしたからだ。
******************************
既に過去ログ「境港発メバル事情」シリーズでも述べ来たように,2007秋から2008冬のメバルの行動は,例年に比べて実に変則的であった。
接岸せずに沖で繁殖行動を終えてしまった茶メの♂が回復接岸を開始したのが,ちょうど1ヶ月前の2月上旬であり,このあと3週間ほど2月下旬までは,ごく底層を這うような群れを発生する1㎝ほどの半透明の沿岸性アミ類に餌付いていた。
2月も下旬あたりからは北西の風に混じって南~南西の風の頻度が高まったことに加え,風・雨次第で散発的ながら海水温も上昇したため,例年並みに表層に浮く小メバルが大量に発生したが,今年はこれに混じって青や,茶の23㎝前後も浮き始め,回復途上ゆえに体型にはバラツキがみられるものの,順調に推移している。
そもそもこの時期の当場所に小メバルが沸くのは毎年のことであるが,良型のメバルが浮いたのは過去4年間で初めてのこと。変則的には違いない。
ところが,全部が浮いたわけではなかった。
茶メ♂のアミ食いがほぼ終了した3月中旬,同じ場所の同じ種型であっても底に貼り付いているのと浮いているのがおり,底に付いているのは茶メの♀が主体で♂は混じる程度。♀の場合は2月に底に付いていた♂よりも一回り大型の25㎝前後。これは沖で産卵を終えて♂の後から接岸したもので,むろん痩せている。回復度合いが先に接岸した♂より遅れているので,今の青メや茶メ♂のようにエサを追いかけ回して摂る体力・筋力は,まだない。
一方,今浮いてるヤツはどうかといえば,体の肛門から後方はまだ痩せているものの,肩から中程にかけてはプックラと盛り上がっていて食味も悪くない。全て♂である。もし♀が浮くとしたら,まだ先であろうと推測している。
ま,これらは今後の狙い方に関わることなので,置いておくとして,,,。
******************************
【 出来事 その1 】今期の浮きメバルに関する疑問
この一連の現象のうち,回復接岸した茶メバルの♂は,初期には「追わなくても捕食できるエサ」ここではアミ類を主体に食べていたが,体力が回復するに伴い,徐々に表層のエサであるシラス等小魚類も追い始めた。この“徐々に”というところがポイントで,つまり,潮が表層に小魚を運んできても,これを追えるだけの体力がつくまでは茶メは浮くことをせず,青メのみがこれを追っていたのが2月下旬あたり。そして3月に入り,コンスタントに表層で釣れるようになったメバルを見ると,青と茶が混じるようになっていた,というわけなのだ。
こんなことを喋っていると,巷でよく聞くコメントは,「中・低層の茶,中・表層を動き回る青,その違いでしょうね。」というもの。私もかつてはそのように思っていたのだが,実際には必ずしもそうではないようなのだ。
“青メは表層”,というのは,たしかにわかりやすい。この前の2週間,底層で20~25㎝程度の茶メを釣っていたときでも,合間に強い潮が入れ込んでくると,表層で同サイズの青メが単発的に釣れてはいたからだ。しかも青メは,底層には潜らない。エサを伴う潮と共にワッと来てサッと去る。同じ場所に長居をしない,込み潮の使者だ。
ちなみに3型と釣れ方の全体的な傾向を言うと,
2月上旬から下旬にかけて,極めて底層にへばりついていて釣れていたのは,ほとんどが茶メで赤メが少し。青メはというと,既に述べたとおり2月中旬あたりから表層でチビメバルのライズが続く中,潮が強く利いてきたときのほんの短時間だけ回遊してきてバタバタッと釣れて終わりなので,型は良くてもアテにはならぬ,という状況であった。
それが,2月下旬頃から表層でコンスタントに釣れるようになって以来,赤メは瀬を中心に底にへばりついたままであったが,表層は青メだとばかり思っていた中に同型の茶メが混じり始めたのである。というより,その後,日を追うごとに茶メの割合は増えていき,今や表層付近で釣れるメバルのほどんどが茶メという状態なのだ。
余談であるが,茶メと青メは,生きているときの青メの背が見る角度によって緑色に底光りすることで判断できるわけだが,漁場によっては外見からは判断がつきにくい場合がある。また,小型であるほど見分けがつきにくい。かといって,胸びれの筋をいちいち数えてもいられない。
が,これを持ち帰って下処理課程で鱗を取って眺めてみると,これはハッキリする。
青メの方は,鱗を引いた後の肌合いが,ひげそり後のような寒色なのだ。そして,過去ログ「塩煮の世界」で述べたとおり,調理したときに,その差は更に明確になる。
茶と青を比較すると,茶メの身はしっとりしてコクがあるのに対し青メのそれは堅くパラパラしており味が薄い。茶メの皮は薄くて身との一体感があるのに対して,青メのそれは,加熱すると,身から離れようとするがごとくプリンと堅いのである。
それぞれに活かしようであるが,かつて過去ログ「メバルの3型とその味覚」で,青メの大判は夏に薄造りで,皮の湯引きを添えて食うに限る,と申し上げたのは,この特性にある。
話を戻し,
「ワカランことがあればいろんなかたちで触ってみる」,というのが基本であるから,次は胃内容物の調査などに突入していくのであるが,これによってようやく,メバルの型とそれらの行動特性,および棲み分けのメカニズムの一端が,見えたような結果となったのだ。
たとえば一昨日釣れたのは茶メが2尾に青メが1尾。いずれも23㎝前後で型揃い。15分の間に,同じ道具で,同じ立ち位置から狙った表層付近の,同じ層の同じ誘いで釣れてきたものだ。
当然のことながら,胃内容も同様と思っていたのだが,さにあらず。
結果は,青メの胃の9割以上が3㎝ほどのシラスおよび3~5㎝ほどのアイナメのなど(アイナメの稚仔魚期はイワシ類のような外観で表層生活をしている)で占められていたのに対し,茶メの胃内容は,水温上昇に伴って2㎝ほどまで成長した低層性のアミが7割で,青メの食っていたような小魚類は3割程度にとどまっていたのである。
横にいた青年二人に,釣り方を教えるから胃袋だけくれと頼んで調べてみたのだが,調べた青メ5尾,茶メ7尾とも,全て同様の傾向であった。
更に先日,もっと興味深いことがあって,いよいよ3型の特性が浮き彫りとなった。
******************************
【 出来事 その2 】 場所による同種型の差違
私は外灯のある漁場で,小メバルがライズする灯りの中心部に対して潮下の離れた暗がり表層下で23㎝前後を釣っていた。先週以来続いていた浮きメバルも潮回りが進むにつれて時合いが短くなりかつ散漫な釣れ方になっていたこともあり,もう一人の青年は少し離れたテトラ付近の暗い斜面を探って20~23㎝ほどのを3尾釣って戻った。コチラで釣ったのとアチラで釣ったの。その距離はテトラをはさんだ両側20m範囲。両方とも茶メの同サイズ。
しかしこれが,違うのである。
テトラ周りの茶メは,体に対して目が大きく,回復してきているとはいえ全体的に痩せ型で,コチラの表層茶メは体高があり相対的に目が小さく,痩せているのは体の後方のみ。胃内容はテトラ周りの斜面がアミ類であるのに対し,コチラはアミ7割+小魚3割でこのところの傾向と変わらず。
この時,これまで境港から島根半島で釣ってきたメバルの種型,形態的特徴,釣れ方,胃内容物,等々の記憶が,走馬燈のように脳裏を走った。
たとえば同じ茶メでも,半島の褐藻群落の間から釣れてくる引きの強いやつ。これは,お前はカエルか,というくらい相対的に目が大きく発達している。同じ場所で釣れる赤メでは,あのような違いは見られなかった。あれは何だったのか。
そして,ほとんど隣接した漁場であるにもかかわらず,エサが違い,外部形態(体型や各部の比率)まで違う茶メがいる。どうしてテトラ斜面の茶メは,回復途上にあるのだから,ひょいと20mばかり移動して,なぜ,もっと栄養のある小魚類を捕食に行かないのか。しかも,外観的な違いは,同時期同場所の赤メや青メでは見られず,なぜか茶メだけに起こっている。
******************************
さて,丁寧に整理してみよう
①今期接岸した茶メは,初期には底層の沿岸性アミ類を専食していたが,回復が進むにつれて,表層付近の小魚類に餌付くようになった。底層で釣れていたときには全てアミ類であったのに対し,青メと混じりで釣れ始めたときの胃内容物は,アミ7割,小魚3割となっていた。そして,時期が進むに従い,アミの比率は減り,小魚の割合が増えていった。
②同時期同場所の表層で,小魚類に餌付いていた青メは,回復期の茶メがまだ底層に貼り付いていた時期から,強い潮と共に来遊し,表層で短時間単発的に釣れていた。そして,胃内容物は,9割以上がシラスやアイナメの稚仔魚であって,アミ類はごくわずかであった。なお,青メは底層で釣れることはなかった。
③同時期同場所での底層では,茶メの回復接岸が始まった段階から赤メが釣れていたが,その後,茶メが表層に浮くようになっても,赤メが浮くことはなかった。胃内容物は,底層のアミ類に加え,海藻や岩礁に由来する固着性甲殻類(ヨコエビ類)であった。なお,この傾向は,茶メが浮いて底層で釣れなくなった後も,変化することはなかった。
④茶メが表層に浮いた漁場に隣接するテトラ帯の斜面漁場で同日に釣れた茶メは,同サイズであっても相対的に目が大きく,回復の度合いが遅いように見られた。なお,隣接するテトラ帯から目の大きい茶メが移動してきて表層の茶メに混じって釣れることはなかった。
⑤島根半島の褐藻帯から釣れる茶メは,今回観察されたテトラ帯の茶メよりも,更に相対的に目が大きい。ただし,同場所同時期に釣れる赤メでは,そのような差違は見られなかった。
*******************************
【 メバル3型にみられた行動・棲み分け・生活様式の違い 】
以上の事実から導き出される結論を要約すると,次のようになる。
● 赤メは海藻や瀬(構造物)に対する依存度が最も高く,中~低層の海藻や構造物に密接して生活圏を形成し,その範囲のエサを摂っている。形態的差違は少ない。
● 青メは潮に対する依存度が最も高く,表~中層,もしくは一時的に海藻や構造物にも生活圏を形成し,その範囲のエサを摂っている。形態的差違は少ない。
● 茶メは表・中・低層,構造物等,餌を採る手段を最も柔軟かつ合理的に選んでおり,状況に応じて生活圏を変える。赤メのように構造物に強くこだわるグループもいれば,こだわらないで動き回るグループもいる。そして,それら環境に応じて形態的差違が大きいのが特徴である。
● 更に茶メでは,繁殖後の回復に伴い,食べやすい底層性のアミから追いかけて食べる表層性の小魚類に向けて徐々に移行していく。つまり,回復期における茶メの摂餌形態は,個体の能力に応じて徐々に合理的な方向に変化することが推測される。なお,赤メや青メでは,そのような変化はみられなかった。
● 結果として,赤と青は生活圏レベルで完全に棲み分けているが,茶は成長もしくは回復の過程で両方の生活圏に参加している。
ここまでは,わかった。
が,,,
【 悩みは尽きぬ 】
しかし生じる更なる疑問は,,,
ここで得られた事実を見る限り,たしかに茶メはいかようにも摂餌行動およびそれに応じた生活圏を変えている,のであるが,では結果としてその生活様式が外部形態の差違に現れるのは,卵から老成魚までの,どの段階で生活様式が“染みついた”場合にそうなるのか。ということ。
まず,小メバルが毎年一定の場所で湧くところをみると,未成熟期に形質が固定されるわけではあるまい。ここから成長に伴い,それぞれに何らかの出来事があり,それぞれの生活様式およびそれに応じた形態になっていくと推測されるのだが,
しかしそのメバルは,ずっとそこにいて成長するわけではない。季節に応じた離岸・接岸がある。
2週間前には底でエサを摂っていたので眼が大きかったですけど,今週からは表層に浮いてるので眼は小さくなりました,などという器用なしくみのハズがないし,回復期の体型でさえ,いくらエサを食いまくったとて,太り具合でさえ,差が出てくるのに1週間はかかろう。
そうなると,先述した,底のアミ食いメバルとその後に釣れた表層アミ+小魚を食っていたメバルは,全く別の群れなのであろうか。今は,表層茶メが釣れ始めると同時に底層茶メがいなくなったことから,回復過程で底から表へエサを変えたものと解釈しているのだが,たしかに底と表層の茶メの体型は,別の群れかと思うほどに違っているのである。
接岸過程で変わる環境やエサに合わせて態を変える?
つまり,接岸した茶メの,場所による外部形態の差違は,毎年の繁殖~回復接岸過程で形成される???
そんな短期間に?
そしてもうひとつ気になることは,「進化」の問題。
これら3型が,その生活形態において,一部は重なるけれども異なる行動生態,あるいは生存戦略をもってサバイバルしていると。特に茶メは行動に伴い様々に外観の態を変えるとすると,それでは「進化」の過程として,赤・青・茶の,どれがどれに分化していったのか。
固定したところから多様化したのか。逆に多様の中から固定化していったのか。そして,今現在,どの課程にあるのか。一般進化論でふつうに考えれば順応性の高いものから派生して固定化し,遺伝的に隔絶されていくと考えがちだが,そうなると胸びれの条数との関係はどう解釈できるのか。茶17本→赤15本,青16本。軟条が少なくなるメリットなんてものは考えにくいし,これは退化???。 あるいは逆に,赤・青→茶???。
魚類学のレポートでは遺伝的にそれぞれ分離しているというのだが,実際に釣ってみると,3型としての外観的要件を満たしていても,その生活において,青のようにふるまう茶や,赤のように暮らす茶が存在することも,また事実。分化する前の昔の名残が生活に出ている???。 ワカランなあ~,はははのは。
でも,感触としては,形態を柔軟に変える「茶」の謎を追っかけること。これがこのテーマを紐解くカギになるのではないかと思っている。
といったようなことで,アレコレ悩ましいですね。
メバルの世界が奥深いのは釣りだけではない。こうなってくると,もうあくまでも学術的ロマンですな。我々人間の第4の欲求,すなわち“知りたい”というヤツだ。
******************************
【 メバル3型とワタクシ 】
でも,それよりなによりも,これまで過去ログでも述べ来たとおり,メバル3型には明らかに食味上の大きい違いがあるということが当方最大の関心事。こちらのほうが,やはり優先されるのです。
従って,メバル3型とワタクシの直接的な関係は,
ひとつの海から,
① 3型ごとに,それぞれ一番旨い時期に一番旨いサイズを選んで釣る。
② 混在している中から3型を釣り分ける。
③ そのための見識と技術を体得する。
というようなことで,これすなわちメバル釣りにおける「オカズ釣り道」の極めるべき道の果てであろうと思う次第。
こんなことが想定可能なのも,同場所で同時に3次元的に漁場を探れるメバルの疑似餌釣り=メバリング,ならではのこと。いろいろ使えてスバラシイですね。
ウエカツは所詮は食い気かよ →そのとおり。
食で自然界とつながってこその自分だ。
だからこそ,個として必要量を獲り,必要以上を獲らない。またそれが続けられるようにモノゴトを追求するし,それをわかった上で釣り方を変え,漁獲圧を調節する。
数やサイズを他人と競うような風潮とは無縁。相手はサカナだ。そして自分だ。
いずれにせよこの3型を追うテーマはオモシロイので,また何かわかってきたら続報いたしましょう。釣技の向上にもたいへん役立ちますしね。
今日のところは,これでおしまい!
2008年02月13日
境港発 今期のメバル事情2008(2月中旬現在)
先週末は,北西の風がパタリと凪いで,出張前仕事帰りの30分一本勝負。
それにしても,,,
「往復夜行バスを使った九州日帰り出張」なんてスケジュールは,いいかげんヤメにしたいものだ。夜行バスで行って一日仕事してその日の夜行バスで戻ってくるのは,→2泊1日??,これを日帰りと言っていいのかどうか。学生の貧乏旅行にしたってもう少し余裕があろうにと思う。
ともあれ当夜,25㎝ほどのメバル・カサゴ・ムラソイと3種型揃いで各1尾ずつ,きれいに釣れて,ハイ終了。オカズ釣りはかくありたいもの。最短時間の最大効果。この時期のいるべきところではないとはいえ,今年ならではの“いるべきところ”に,やはりいる。
なるほど。今期,産卵場も枯れており,群れで来遊する餌が少ない中,どこか餌のあるところは,となれば,こんなところでウロウロ餌探ししているわけね・・・,とは潮通しの良い平場の斜面で今期11月には30㎝越えのカサゴやヒラスズキが出たところなのだが,安定漁場なるかと喜んだのもつかの間,旨くないんだな,これが。
塩煮(過去ログ「塩煮の世界」参照)にしてみるとハッキリわかる。茶メだから身はしっとりしているものの,皮やヒレ際がムッチリしていない。煮汁に濃厚さが出ない。つまり“コラーゲン質”が足らんのです。
ね,繁殖力旺盛な人間のオス諸君,コラーゲンですぞ。オスだろうがメスだろうが,繁殖活動に全て使っちゃってるわけですよ。急流の淀みから出た体型のいい茶メバルの♂であったが,腹身が薄い,味が薄い,コクがない。男もコクがなくてはね。
資源維持の観点のみならず,食味の面からも,やっぱり産卵期まわりは釣るもんじゃない。せっかく味わっても寂しくなるだけでは悲しい。これじゃあ釣られたメバルがお気の毒。
かといって,定期的に探っておかねば動向がわかりにくい。さりとて釣って痛めて放す,というのも趣味に合わぬ。なら釣らなきゃいいじゃねえかと言われて当然だが,でも動向をつかんでおきませんと・・・。などとバカげた輪廻地獄にはまりつつも月日は過ぎてゆき,メバルの体も本調子が期待されるところ。
二匹めのドジョウを狙って翌週の凪を同じ場所でやったみたところ,数日来の冷たい雨でドカ濁り+急激な低水温+川のような潮流。今期,スパッと狙えるチャンスがどれほどあるものやら。とにかく今年はマイナス要因が多く,環境変化がめまぐるしいので狙い打ちが難しい。
いたしかたなく,帰り際の漁場に寄れば天は我を見放さず,期せずして25㎝前後のマアジ入れ食い。12月に来ていた同サイズのアジ群れは既に沖の深場に去ったハズ。こんな時期に,どこから来たものかと首をひねりつつ,さっさと1㎏ばかり蓄えて終了。この手返しと選択的型の良さがワームアジ釣りの骨頂。ただ,変則的なこの時期に好機に遭遇したとしても,次はいつ獲れるかわかりませんからね,これでしばらくは釣らなくても大丈夫。根魚だったら釣り過ぎは御法度なのでこうはいかない。青ザカナならではのこと。
案の定,この翌日には群れが消え,以来今までアジのアの字も見当たらぬ。
獲れるままに獲るのではなく,「今獲らなくては明日にはなくなってしまうのか」,逆に,「今獲らなくても明日もあるのか」,そして,「今獲ってしまっても差し支えない相手なのかどうか」。このへんの状況把握と判断が,計画の立ちにくい自然相手に安定的魚食生活を設計するオカズ釣り師の課題である。ま,ラックも重要な要素ではありますが。
さて本題。境港の今期のメバル,中間報告です。
問題は,「今年の“ナゼ”」,であって,境港のそのあたりを少々。
まだ十分に整理していないが,ご参考まで。
******************************
【 2007年10月~2008年2月上旬の概況 】
昨2007年,例年10月から始まる当地のメバル釣りは,過去ログでも述べたとおり,10月中~下旬に数日間連日の好釣果が得られたものの,11月中旬に入って低迷しはじめ,冬季産卵前の盛りたる12~1月も釣果はパッとしなかった。例年以上に海況が安定しないこともあり,連日で釣れる,ということが少ない。
粘れば大型が出ることもあるが,継続性に欠ける。島根半島や中・西部,鳥取県の東部などでは,ソコソコ釣れてますとは聞いているが,ここ境港界隈では,日々安定したオカズ獲りと言うにはほど遠い状況が続いた。粘って単発では意味がない。達人諸氏が活躍しておられるその他の日本海各地や瀬戸内海あたりではどうであろうか。
【 釣れるメバルと餌生物の状況 】
本年10月から2月現在までの期間を,サカナの釣れ方と胃内容物の状況から判断すると,概ね3期に分けることができる。
●「第1期」10月中~下旬
例年のこの時期ならば20㎝前半が少しずつ継続的に釣れるような実績ポイントでは,極めて短期あるいは単発で,数が釣れても1日で終わりとか,1尾で終了あとが続かず,といった調子で推移した。数が釣れるときの胃内容物はシラス,単発終了のみの場合はほぼ空胃であった。
この実績漁場での短期集中ぶりは,10月中旬に異例に早い時期の短期間,一時的に吹いた北の風によってシラス群が接岸し,これをメバルが追っていたことによって生じたもので,いわゆる“産卵接岸”ではなかった。その証拠に,生殖器官の熟度が極めて低かっただけでなく,まもなく今期冬の特徴であった東の強風が頻発するようになってシラス群れが離散すると,同時にメバルもいなくなった。
釣れたメバルは,ほとんどが青メであり,茶メは,ごくわずかであった。本来は青メが釣れる時期と場所ではない。
つまり,本来この時期にコンスタントに見られるべき「茶メ」の索餌接岸は,実質ほとんどなかったといえる。
実績場所で上記のような現象が見られた傍ら,相変わらずの高水温が続いていた中で連日数尾ずつ20~25㎝が釣れていた場所があった。
これは,過去4年間,メバルに関しては小型しか釣れないと見放されていた場所,あるいは砂泥底なので根魚はおらぬと言われていた場所の岸壁や小さな沈み瀬周り,などを再開拓した結果である。
これら再開拓漁場は,実績漁場よりも美保湾の沖側に位置しており,ここでは茶メが8割を占め,2割が青メ,岸壁沿では過去3年間この時期で初めて23㎝前後の赤メが混じったが,型も体型も安定していたわりには,胃内容物は全てメガロパ(カニの幼生)など粒型の走光性浮遊生物であり,シラス等魚類やゴカイ類は全く見られなかった。
●「第2期」11月初~1月初旬
10月に単発で終わった実績漁場には相変わらずメバルの集中的な来遊はみられず,底層を探れば小カサゴの山であった。
10月に良型メバルが連発していた再開拓漁場においてもキープサイズのメバルは消えて15㎝台の小型が主体となり,代わりに25~30㎝の抱卵カサゴ♂♀の集中漁獲があった。
例年,カサゴの抱卵はメバル産卵後の3月あたりでピークとなるはずであるが,実に2~3ヶ月ばかり産卵開始が早まったことになる。胃内容物は,全て小型のカニおよびテッポウエビなど底性甲殻類であった。
なお,この時期12月を中心に,マアジ実績漁場では例年通りワームに連日釣れ盛っており,25㎝オーバー主体に量的にはコンスタントに確保できたものの,本来この時期の脂の乗りではなくヤセ型主体。胃内容物はカニの幼生等に加え,ごく少量のシラス類であった。
●「第3期」1月中旬~2月上旬
1月中~下旬には実績漁場でようやく成熟した23㎝前後の抱卵♀メバルが散見されたものの,全て単発で終わる。胃内容は,ほぼ空胃。茶メと赤メ。ポイントは小さな沈み瀬のある平場ないしテトラ帯であった。
例年この時期,1月中旬をメドに数尾は釣れてくる尺クラスの♀は,今期は釣れていない。
また,2月に入ってから,既に産卵が終わっていなくなったと思われたカサゴの抱卵が実績漁場の小カサゴに見え始め,これも異例のことであった。
一方,再開拓した漁場では,良型カサゴは消え,かといって良型のメバルが来るわけでもなく,茶メの小型が山ほど。港湾奥の港内漁場も同様。
いわゆる春の雨後のタケノコのように湧き出る「タケノコメバル」というヤツだが,これは例年2月下旬あたりから出てくるもので,1ヶ月ほど早い。各漁場とも風向きによってはごく少量のシラスやシラウオなどサカナ系餌の来遊があったものの,これを追う良型メバルの浮上はなく,小型がこれを追いかけ回していた程度であった。
【 今年の“ナゼ”を考える 】
さて,
カサゴの産卵期のズレは昨年も同時期に1ヶ月早まった上に長期化していて気になっていたところであるし,マアジの体型のバラツキも昨年にもまして特にひどく,餌の量・質との関係上放っておけない現象ではあるが,ここではメバルを主体に有用な情報を整理してみよう。
まずは釣れ方について。
①10月に短期集中で釣れ盛ったメバルは,短期的に来遊したシラスを追って接岸したものであり,成熟しておらず,シラスの群れの離散に伴い,いなくなった。餌を求めて大きく索餌回遊することの多い青メ主体。
②再開拓漁場で釣れた胃内容が甲殻類の幼生主体であったこと,釣れたメバルの体型,および他漁場では青メ主体でしか釣れていなかった状況を合わせると,10月に釣れた茶メは,ほぼ前シーズンからの居付きであった可能性が高く,いわゆる索餌接岸ではなかったと推測される。
③11~12月にかけてシラス等の魚系餌を狙って接岸すべきメバルの来遊は少なく,釣れても単発,胃内容物は甲殻類の幼生などであった。茶メ主体。
④1月に入り,中~大型の抱卵個体が単発で見え始めたものの,釣獲頻度は更に低下し,平場の沈み瀬やテトラ帯が主体。型は良くとも空胃で,風向きによっては稀にサカナ系餌の接岸があったにもかかわらず,これを食ってはいなかった(ただし,湾奥の小メバル集中帯では頻繁に捕食がみられた)。
これに餌や海藻の発生,他生物の状況,気象など環境面の情報を加える。
⑤10月は夏場からの高水温が続いた中で,一時的に美保湾に対馬暖流の一部(相対的には冷水)が蛇行し,ここに時折北寄りの風が吹いたため,吹送流によって湾内へのシラス来遊となった。
⑥例年ならば10月上旬で姿を消すはずのマダイの幼魚が,場所によっては11月下旬まで釣れ続けていた(マダイの幼魚の沿岸での生活圏は,多くの場合メバルのそれとかなり重なっており,水温の季節的変化に伴い同じ空間を一部交代で利用している。つまり,子ダイが釣れ始めたらメバルは終わり,子ダイが消えたらメバルの始まり,というのがここ数年来のサイクルであった。つまり当地において,マダイ幼魚はメバル漁期終始の指標となり得る)。
⑦11~12月にかけて東系の風が吹き荒れ,北西風が安定せず,沿岸へのシラス来遊が阻害された(東系の風は,北東から南西まで風がめまぐるしく動いていくことが多いため,安定した表層吹送流が形成されず,シラス等表層生活を主とする餌の離散につながる)。
⑧12月あたりから繁茂を開始すべき冬の海草類が発生せず,海藻を生活基盤とする餌生物(ワレカラやエビ・アミ類)は見られなかった。一方,甲殻類の幼生の発生・着底,およびその他の底棲甲殻類の存在は,例年どおりであった。
⑨1月に入っても冬の海藻類の成長は停滞しており,実績漁場において例年産卵の拠り所となる海藻空間は形成されていなかった。一方,1月下旬あたりから,冬の海藻が十分発育しないままに春の海藻が出始めている。
⑩12~1月にかけての積雪は極めて少なく,冬型の低気圧が数回接近したが,雪として残ることはほとんどなく,冷たい降雨が続いた。山間部に積もる雪であれば森林の機能と併せて安定かつ緩やかな陸水栄養分の供給につながるが,低温の雨であれば,降雨後の塩分濃度の変化が大きく,かつ急激な水温の低下につながった。
更に,あまり行かないので断片的ではあるが,境港を少し出た美保湾に接する島根半島の一部およびその先の状況を記しておくと,
⑪11月にかけて,美保湾西部の端に位置する美保関港では,境港エリアの雑賀委託漁場同様,早期から抱卵カサゴ主体で釣れており,メバルはほぼ不在であった。
⑫12月に入り,美保関港では良型・良体型のメバルが単発的に見られたが,全て茶メで,胃内容は空であった。これらは1月に入ると暫時いなくなった。
⑬美保湾外を西へひとつはずれた七類港の褐藻帯では,12月中旬に小型に混じって23㎝前後の中型も出たが,胃は空であり,全てがガリガリの痩せメバルであった。
⑭冬の海藻の生育が悪いのは美保湾に面した側だけであって,島根半島方面になると,例年通りのホンダワラ等褐藻類の繁茂がほぼ例年並みであった。
さてさて,
これら当面14の事実を眺めてみたとき,なんとなく今期現在のメバルの事情が見えてくる。
● メバルの集中接岸を促す湾外部からのサカナ系餌の来遊は,冬季の風向きに支配されやすいということ。従って,今後も外部からの餌供給がない場合には,海岸性の餌の発生のみが索餌接岸のカギを握っているということ。
● シーズン初期の索餌接岸は外部からの餌供給によって決まり,その漁場(湾,堤防)の向きに伴う環流の形成状態によって魚体の差が決まるが,今期は風が変則的であったために各漁場への餌の配分が安定せず,場所(漁場)単位で勝ち組と負け組(太っている,痩せている)がはっきりしていたこと。
● ただし,沿岸性の甲殻類の発生は局所的に例年並みであり,それが漁場ごとの居付き度合いに表れたということ。
● 総じて夏から冬にかけての水温が,産卵接岸の引き金となる海藻帯の形成及び海藻由来の餌発生のカギを握っていること。
● 冬季の降雨・積雪の状況が,沿岸の水温のみならず(おそらくは)栄養塩類の供給という意味でも,海藻および沿岸性餌の発生に大きく影響しており,この点は,半島よりも特に陸水の影響が強い境港エリアで顕著であった
ここから,当地の漁場形成要因を考察し抽出していく。
《 風について 》
例年は安定した北西風が吹く時期に東風が吹き荒れたということなのだが,
まず,北を向いて口をあけている美保湾の沖には,東北東に上がっていく対馬暖流が恒常的に流れており,これの影響を受けた沿岸の潮が,反転流として湾の東端から時計回りに西向きに回っていく。美保湾のサカナは東から来る,と言われる所以だ。
通年ならば,冬季ここに北西風が吹くと,対馬暖流に対して斜め後方からの吹送流が生まれ,対馬暖流縁辺の中にいる西海域で孵化したシラスなどの餌生物が,美保湾の環流に巻き込まれてグルリと接岸し,サカナもこれに付いて移動するというわけだ。
ところが今期多かった東からの風,これは対馬暖流の流れに対して右斜めから押し返す風であるだけでなく,その結果,美保湾に入る反転流の形成を弱め,仮に合間に北寄りの風が吹いて餌が入ってきたとしても,再び東風に戻れば,餌およびそれを追うサカナの湾からの排出を追い風の形で早めてしまう。更に,この時期の東風は南西方向まで振れながら吹くため,せっかく岸に寄った餌を沖へ向けて離散させてしまう。
今期,釣れても短期集中あるいは単発であったひとつの要因が,これだ。
《 潮について 》
潮には,天体の動きに伴う「潮汐」によるものと,風による「吹送流」とがあるが,主に沿岸性餌生物の活動およびメバルの食い気を左右するのが前者,主に外部から供給される餌の種類と量を左右するのが後者である(これが一時的な活性化に貢献することもある)。
今期は,先述した不安定な風環境によって吹送流による餌供給が阻害され,更に後述する続いた冷雨によって湾内への流入水量の変化が激しく,漁場での実質的な潮の動きにも影響が出た。つまり,2タイプの潮の両方ともが変則的であったため,総じて潮汐表に基づいて過去の実績に照らして狙いを定めても不発が多く,その原因が特定しにくかったわけである。
《 水温について 》
水温は,上記,風と潮に加え,陸水の流入も大きく関与し,繊細な餌生物であるシラス等餌となる魚類の孵化率および成長に影響を与えるものであるが,それと並んで影響を受けやすいのが海藻の胞子であり,またそれら着床後の発育である。
これは,産卵環境という意味で,また,春に向けて発生する海藻依存型餌生物の基盤として最も重要。逆に,稚魚を放出する早春に,♀は,稚魚の餌となる生物が確保されやすい海藻帯を産卵場に選択するということでもある。
今期の産卵接岸の停滞は,11月までの高水温,および1~2月にかけての急激な冷水の流入によって,海藻帯が形成されなかったことが大きな原因であろう。
《 餌について 》
結局,釣りの原理を支える餌の事情は,上記相互に不可分の3点,「風・潮・水温」に全て支配されている。あとは元本すなわち親からの“タネ”があるかどうかだ。
とまあ,こうしてみると、なるほど自然は,何が先とは言わずグルグル回っている不可分の世界だ。
【 “それ”はどこにいるのか 】
さて,,,
釣れる釣れないは別にして,岸寄りでは影が薄い今期のメバルが,それではこの時期,どこで何をしているのか。これがやはり疑問として残る。
当然のことながら,どこかで餌を採り繁殖しようとしているのにちがいないのであって,諸事情により今年は産卵をとりやめましたのであしからず,などという器用なマネは,いかに適応性の高いメバルとて極端すぎて無理。
生物の本質をたどれば,「生まれてから死ぬまで食い,その間で子孫を残す」,ということであって,無論サカナも例外ではない。“食う・寝る・休む,子を作る”の4点セットを必ずどこかでやっている。そして我々釣り人からみれば“餌なきところにサカナなし”が基本ではあるが,しかし子作りが食欲より優先されることもあるのが生命の力たるところ。ソレとアレとをたぐっていくと,メバルの動きが見えてくる。端的に言うならば,サケを見よ。餌があろうがなかろうが,子を残すために行くところには行く。餌,ばかりではない。
『通常の索餌のための餌場はどこにできるか』,
『繁殖のために栄養をとる索餌をどこでおこなうか』
『交尾後の♀が産卵するための適地はどこか』
『回復のための索餌の餌場はどこでできるか』。
1月中旬,友人の船に頼んで調査範囲を広げてみたところ,ひとつのヒントが,意外とスンナリ出た。この時期メバルは,『沖で集まっていた』というのが結論だ。
正確に言うと,「集まっていた」のか,接岸のタイミングを「待っていた」のかはわからない。ここでは場所に関する詳細は書かないが,沖合の一定条件を満たした場所では,抱卵良型メバルが,ちゃんと例年並み繁殖期の1月に,しかも連発して釣れた。わかった,もうそれ以上触りなさんなと言って調査終了。
結局,
『メバルの感覚は例年並みであったが,今期の餌およびその他の環境が,索餌や繁殖にとって変則的で条件として整わなかったため,それに応じて許容範囲内での接岸にとどまった』 というのが解釈としては妥当であり,餌的にも,産卵的にも,それらに関わる水温等環境的にも,その限界が沖の漁場であったということなのだろうと推測される。
一度は岸に入ってきて環境が整わなかったから沖に戻ったのか,あるいは沖で必要十分な環境が整ってしまったのでそこから動かなかったのか,はたまた何らかの感受性で岸がダメであることを察知したのか,それはここからはわからない。
が,沖漁場の調査結果から推すれば,1月から2月上旬に単発で抱卵♀が釣れた状況は,メバルが岸寄りはダメだと察知したしたときに,DNAゆえか,それでも例年の場所に行きたくて我慢できず,たまたま体力的に劣環境を乗り越えることができた個体,逆に,よそに産卵適地を探すことが出来なかった個体,そんなヤツが,岸から竿が届く例年並みの範囲に接岸あるいは居残り,結果として単発に釣れていた,というのが真相だと思われる。
おもしろいことに,このような“やせ我慢”タイプはほとんどが赤メ,加えて若干の茶メであった。おしなべて赤メは,メバル3型のうち最も“場”に対する執着が強い。藻や構造物に対する依存度が一番高いのが,この型だ。
人間でも執着が強い人は難儀な目に遭ったりしてますねえ。などと言ったらメバルに失礼。
先述した沖漁場では,1月の中旬段階で既に完熟した放卵寸前個体を多く確認しているわけだが,2月初旬のいまだに♀が接岸していないところをみると,今年の抱卵メバルは,岸よりも“比較的”環境の安定していた沖の中深部海藻帯や構造物周りを中心に産卵を終える見込みだ。
従って,「これから季節が進むにつれて抱卵大型個体が接岸してくれるのではないか,水温が高かったので単に遅れているだけではないか」,といった期待は,すっかり崩れたことになる。
もし今後産卵接岸があるとすれば,ここしばらくのうちに岸寄りの海藻が急速に成長して環境が整ったところに産卵の遅れた♀が接岸する,というような淡い可能性が残されているのみで,今の状況からするとおそらく単発で終わるであろうし,それも,環境が整ったら,の話であって,当方のオカズ供給のアテにはならぬ。だいいち,抱卵メバルは旨くないのだから。
【 メバルは来るか 】
いずれにせよ,次なる懸案として「産卵後のメバルは接岸するやいなや」,という問題が浮上するのであるが,そのカギとなるのは,これまで整理してきたコレとソレとアレだ。
これらの状況によっては沖の漁場に停滞したまま,ということもあり得るはずだが,沖に回復するに足るだけの十分な餌がなければ,必ず岸に回ってくる。これは“来ざるを得ない”。さてどうなるか。
やはり当面の指標としては,海岸で発生する餌。
春の海藻がどこにどれだけ生えるか,そして今年はあるかどうかわからないけれど,稚アユの遡上に先立つ港内迷入,及び春のイカナゴの発生(これは昨年,境港では7年ぶりにあったのだが),これらがあるかどうかに期待している。シラスは既に成長してしまっており,その後どこに行ったのか音沙汰がない。外部から来遊する餌がこのまま入ってこないのであれば,岸寄りで発生する次の餌に期待するしかない。
境港はここ数日,今日も冷たい雨雪が降り続けており,餌にとっても海藻にとっても,当然メバルにとっても快適とは言い難い。しかし,釣りはせずとも日々の観察。ジグヘッドをはずし,糸の先にガン玉つけて,海底を触って歩くだけでもよいではないか。地道な努力はアトほど効いてくる。
*********************************
【 その後の話 】
上記を記した一週間後の今,2月中旬,実績場所で,まとまった数のメバルが出た。
23~25㎝の茶メが4つ,20㎝そこそこが3つ,うち赤メ1,あとは18㎝の茶メが2つ。ささやかではあるが,40分勝負の必要十分量。10月以来,久しぶりのまとまった接岸だ。これは次の時化が来るまでの3日間,潮汐に合わせてずれていったが,遜色ない漁獲が続いた。
胃内容は,茶メではたっぷりの浅海性のアミ類(1㎝前後)と,赤メでは岩礁由来のグソクムシの仲間が少し混じった。海岸由来の餌の発生が始まっている。
これらはいずれも運動能力が低く,特にアミ類は,緩い潮が効いてくると群れで海底から少し浮き上がって定位しながら植物プランクトンを補食する。力のないサカナにとっても苦労なく食える餌で,低水温下・回復期の弱ったメバルにとってはうってつけだ。従ってアタリ方は,ポク,と押さえてしばしじっと動かないような出方をする。
全て茶メの♂ということは,むろんもはや産卵接岸ではない。回復初期の索餌回遊が始まった。
交尾を終えた♀は卵の成熟を待ちつつ暫時沖の適地にて今も産卵中であり,♂は交尾を終えてしまえばフリーなので,回復するべく餌を求めてさっさと移動する,ということで,お先に到着いたしました,というわけだ。卵胎生のメバルならではの摂理と動き。
しかしながら、回復初期だけあって,型は良くても痩せているし,食いはあっても引きが弱い。水温も冷雨で低くなっているので,目の前に餌が来ないと難しい。従って,ベタ底を舐めるデッドスローが基本。
そして潮。一般的に潮が流れれば食いが立つと考えられがちであるが,沿岸性アミ類を食っているときのメバルは単純にそういうものでもない。むろん動かなければダメなのであるが、かといって一方的な強い潮であれば,アミ類は海底の淀みに沈んで固まるか一方向に流されてしまうので,結局潮が止まっても流れすぎても食いが悪い。従って,潮が小さく頻繁に行きつ戻りつしているとき,すなわち,日本海では大潮周りの潮位差が少ないとき,アミの群れは海底に立つ。これが時合いの狙い目だ。
それにしても大切なのは誘い。
早春に発生して潮に対して定位しながら底層に群れを形成するアミ類が,どのような動きをするか,皆様,ご存じでしょうか。これを竿で表現するのは,ちょいと難しい。まず長い竿ではできない。張りのない竿ではできない。かといって,アタリ方は小さいので穂先が繊細でなければいけない。そんな竿はあるのか?。
このお話は,まとめてまた後日。
先週、念のため,再び船を頼んで沖の漁場に行ってみると,♀の産卵が終盤になったとみえて,げっそり痩せた♀が見え始めた。やはり接岸しないまま沖で産卵を終えつつあるようだ。比較的藻場が形成されている半島方面では,どうであろうか。尺も出ているらしいのであるが,それが♂なのか♀なのか,型(3型)は、そして胃内容物は何なのか,そこがいちばん気になるところ。
境港は,西は宍道湖・中海・境水道,東は日野川から由来する大量の陸水の流入があり,また流入先である円弧型の美保湾は,島根半島と大山に挟まれて気象や海洋環境が独特だし,おそらくこの地から導き出された考察は,ここでは通用したとしても仮に日本海の近隣であっても適用できない可能性がある。とはいえ今日にあっては日本沿岸全体の連動的な海の変化も見逃せない状況なので,それだけに同時期の他の地域の状況が知りたいと思う次第,
全国メバル釣り師による状況分析ネットワーク,地域ごとの特派員,みたいな体制ができたら,もっといろんなオモシロイことが見えてくるのだが,誰か一緒にやらんかなあ。
特に気になるのは,日本海と瀬戸内海との連動性だ。両者とも,山脈を挟んで南北に並んだ大きな池みたいな海。たとえばアジ,シラス,これらの同時期の体長のバラツキは,日本海と瀬戸内海で時期が同じでなくとも,2年前からひとつの傾向として表れている。これが意味するところは何なのか。ひいては,これから変わって行くであろう海を相手に,釣り人は,漁師は,サカナを食べる我々は,何を考え,どうしていったらよいのか,それを釣りや食や水産業を通して模索するのが,当家の目下の課題だ。
ま,何事も変則的な今年ですから,せいぜいアタマを柔らかくして構えておきましょう。これからどうなるかは予断を許さぬところゆえ。
少なくとも春の餌は徐々に発生し始めたようなので,早晩まずまずのメバルは寄ると見ている。港湾オカズ釣り師としては,もう少し旨くなるまで,いましばらく,控えめにモニターしておくこととしたい。
それにしても,,,
「往復夜行バスを使った九州日帰り出張」なんてスケジュールは,いいかげんヤメにしたいものだ。夜行バスで行って一日仕事してその日の夜行バスで戻ってくるのは,→2泊1日??,これを日帰りと言っていいのかどうか。学生の貧乏旅行にしたってもう少し余裕があろうにと思う。
ともあれ当夜,25㎝ほどのメバル・カサゴ・ムラソイと3種型揃いで各1尾ずつ,きれいに釣れて,ハイ終了。オカズ釣りはかくありたいもの。最短時間の最大効果。この時期のいるべきところではないとはいえ,今年ならではの“いるべきところ”に,やはりいる。
なるほど。今期,産卵場も枯れており,群れで来遊する餌が少ない中,どこか餌のあるところは,となれば,こんなところでウロウロ餌探ししているわけね・・・,とは潮通しの良い平場の斜面で今期11月には30㎝越えのカサゴやヒラスズキが出たところなのだが,安定漁場なるかと喜んだのもつかの間,旨くないんだな,これが。
塩煮(過去ログ「塩煮の世界」参照)にしてみるとハッキリわかる。茶メだから身はしっとりしているものの,皮やヒレ際がムッチリしていない。煮汁に濃厚さが出ない。つまり“コラーゲン質”が足らんのです。
ね,繁殖力旺盛な人間のオス諸君,コラーゲンですぞ。オスだろうがメスだろうが,繁殖活動に全て使っちゃってるわけですよ。急流の淀みから出た体型のいい茶メバルの♂であったが,腹身が薄い,味が薄い,コクがない。男もコクがなくてはね。
資源維持の観点のみならず,食味の面からも,やっぱり産卵期まわりは釣るもんじゃない。せっかく味わっても寂しくなるだけでは悲しい。これじゃあ釣られたメバルがお気の毒。
かといって,定期的に探っておかねば動向がわかりにくい。さりとて釣って痛めて放す,というのも趣味に合わぬ。なら釣らなきゃいいじゃねえかと言われて当然だが,でも動向をつかんでおきませんと・・・。などとバカげた輪廻地獄にはまりつつも月日は過ぎてゆき,メバルの体も本調子が期待されるところ。
二匹めのドジョウを狙って翌週の凪を同じ場所でやったみたところ,数日来の冷たい雨でドカ濁り+急激な低水温+川のような潮流。今期,スパッと狙えるチャンスがどれほどあるものやら。とにかく今年はマイナス要因が多く,環境変化がめまぐるしいので狙い打ちが難しい。
いたしかたなく,帰り際の漁場に寄れば天は我を見放さず,期せずして25㎝前後のマアジ入れ食い。12月に来ていた同サイズのアジ群れは既に沖の深場に去ったハズ。こんな時期に,どこから来たものかと首をひねりつつ,さっさと1㎏ばかり蓄えて終了。この手返しと選択的型の良さがワームアジ釣りの骨頂。ただ,変則的なこの時期に好機に遭遇したとしても,次はいつ獲れるかわかりませんからね,これでしばらくは釣らなくても大丈夫。根魚だったら釣り過ぎは御法度なのでこうはいかない。青ザカナならではのこと。
案の定,この翌日には群れが消え,以来今までアジのアの字も見当たらぬ。
獲れるままに獲るのではなく,「今獲らなくては明日にはなくなってしまうのか」,逆に,「今獲らなくても明日もあるのか」,そして,「今獲ってしまっても差し支えない相手なのかどうか」。このへんの状況把握と判断が,計画の立ちにくい自然相手に安定的魚食生活を設計するオカズ釣り師の課題である。ま,ラックも重要な要素ではありますが。
さて本題。境港の今期のメバル,中間報告です。
問題は,「今年の“ナゼ”」,であって,境港のそのあたりを少々。
まだ十分に整理していないが,ご参考まで。
******************************
【 2007年10月~2008年2月上旬の概況 】
昨2007年,例年10月から始まる当地のメバル釣りは,過去ログでも述べたとおり,10月中~下旬に数日間連日の好釣果が得られたものの,11月中旬に入って低迷しはじめ,冬季産卵前の盛りたる12~1月も釣果はパッとしなかった。例年以上に海況が安定しないこともあり,連日で釣れる,ということが少ない。
粘れば大型が出ることもあるが,継続性に欠ける。島根半島や中・西部,鳥取県の東部などでは,ソコソコ釣れてますとは聞いているが,ここ境港界隈では,日々安定したオカズ獲りと言うにはほど遠い状況が続いた。粘って単発では意味がない。達人諸氏が活躍しておられるその他の日本海各地や瀬戸内海あたりではどうであろうか。
【 釣れるメバルと餌生物の状況 】
本年10月から2月現在までの期間を,サカナの釣れ方と胃内容物の状況から判断すると,概ね3期に分けることができる。
●「第1期」10月中~下旬
例年のこの時期ならば20㎝前半が少しずつ継続的に釣れるような実績ポイントでは,極めて短期あるいは単発で,数が釣れても1日で終わりとか,1尾で終了あとが続かず,といった調子で推移した。数が釣れるときの胃内容物はシラス,単発終了のみの場合はほぼ空胃であった。
この実績漁場での短期集中ぶりは,10月中旬に異例に早い時期の短期間,一時的に吹いた北の風によってシラス群が接岸し,これをメバルが追っていたことによって生じたもので,いわゆる“産卵接岸”ではなかった。その証拠に,生殖器官の熟度が極めて低かっただけでなく,まもなく今期冬の特徴であった東の強風が頻発するようになってシラス群れが離散すると,同時にメバルもいなくなった。
釣れたメバルは,ほとんどが青メであり,茶メは,ごくわずかであった。本来は青メが釣れる時期と場所ではない。
つまり,本来この時期にコンスタントに見られるべき「茶メ」の索餌接岸は,実質ほとんどなかったといえる。
実績場所で上記のような現象が見られた傍ら,相変わらずの高水温が続いていた中で連日数尾ずつ20~25㎝が釣れていた場所があった。
これは,過去4年間,メバルに関しては小型しか釣れないと見放されていた場所,あるいは砂泥底なので根魚はおらぬと言われていた場所の岸壁や小さな沈み瀬周り,などを再開拓した結果である。
これら再開拓漁場は,実績漁場よりも美保湾の沖側に位置しており,ここでは茶メが8割を占め,2割が青メ,岸壁沿では過去3年間この時期で初めて23㎝前後の赤メが混じったが,型も体型も安定していたわりには,胃内容物は全てメガロパ(カニの幼生)など粒型の走光性浮遊生物であり,シラス等魚類やゴカイ類は全く見られなかった。
●「第2期」11月初~1月初旬
10月に単発で終わった実績漁場には相変わらずメバルの集中的な来遊はみられず,底層を探れば小カサゴの山であった。
10月に良型メバルが連発していた再開拓漁場においてもキープサイズのメバルは消えて15㎝台の小型が主体となり,代わりに25~30㎝の抱卵カサゴ♂♀の集中漁獲があった。
例年,カサゴの抱卵はメバル産卵後の3月あたりでピークとなるはずであるが,実に2~3ヶ月ばかり産卵開始が早まったことになる。胃内容物は,全て小型のカニおよびテッポウエビなど底性甲殻類であった。
なお,この時期12月を中心に,マアジ実績漁場では例年通りワームに連日釣れ盛っており,25㎝オーバー主体に量的にはコンスタントに確保できたものの,本来この時期の脂の乗りではなくヤセ型主体。胃内容物はカニの幼生等に加え,ごく少量のシラス類であった。
●「第3期」1月中旬~2月上旬
1月中~下旬には実績漁場でようやく成熟した23㎝前後の抱卵♀メバルが散見されたものの,全て単発で終わる。胃内容は,ほぼ空胃。茶メと赤メ。ポイントは小さな沈み瀬のある平場ないしテトラ帯であった。
例年この時期,1月中旬をメドに数尾は釣れてくる尺クラスの♀は,今期は釣れていない。
また,2月に入ってから,既に産卵が終わっていなくなったと思われたカサゴの抱卵が実績漁場の小カサゴに見え始め,これも異例のことであった。
一方,再開拓した漁場では,良型カサゴは消え,かといって良型のメバルが来るわけでもなく,茶メの小型が山ほど。港湾奥の港内漁場も同様。
いわゆる春の雨後のタケノコのように湧き出る「タケノコメバル」というヤツだが,これは例年2月下旬あたりから出てくるもので,1ヶ月ほど早い。各漁場とも風向きによってはごく少量のシラスやシラウオなどサカナ系餌の来遊があったものの,これを追う良型メバルの浮上はなく,小型がこれを追いかけ回していた程度であった。
【 今年の“ナゼ”を考える 】
さて,
カサゴの産卵期のズレは昨年も同時期に1ヶ月早まった上に長期化していて気になっていたところであるし,マアジの体型のバラツキも昨年にもまして特にひどく,餌の量・質との関係上放っておけない現象ではあるが,ここではメバルを主体に有用な情報を整理してみよう。
まずは釣れ方について。
①10月に短期集中で釣れ盛ったメバルは,短期的に来遊したシラスを追って接岸したものであり,成熟しておらず,シラスの群れの離散に伴い,いなくなった。餌を求めて大きく索餌回遊することの多い青メ主体。
②再開拓漁場で釣れた胃内容が甲殻類の幼生主体であったこと,釣れたメバルの体型,および他漁場では青メ主体でしか釣れていなかった状況を合わせると,10月に釣れた茶メは,ほぼ前シーズンからの居付きであった可能性が高く,いわゆる索餌接岸ではなかったと推測される。
③11~12月にかけてシラス等の魚系餌を狙って接岸すべきメバルの来遊は少なく,釣れても単発,胃内容物は甲殻類の幼生などであった。茶メ主体。
④1月に入り,中~大型の抱卵個体が単発で見え始めたものの,釣獲頻度は更に低下し,平場の沈み瀬やテトラ帯が主体。型は良くとも空胃で,風向きによっては稀にサカナ系餌の接岸があったにもかかわらず,これを食ってはいなかった(ただし,湾奥の小メバル集中帯では頻繁に捕食がみられた)。
これに餌や海藻の発生,他生物の状況,気象など環境面の情報を加える。
⑤10月は夏場からの高水温が続いた中で,一時的に美保湾に対馬暖流の一部(相対的には冷水)が蛇行し,ここに時折北寄りの風が吹いたため,吹送流によって湾内へのシラス来遊となった。
⑥例年ならば10月上旬で姿を消すはずのマダイの幼魚が,場所によっては11月下旬まで釣れ続けていた(マダイの幼魚の沿岸での生活圏は,多くの場合メバルのそれとかなり重なっており,水温の季節的変化に伴い同じ空間を一部交代で利用している。つまり,子ダイが釣れ始めたらメバルは終わり,子ダイが消えたらメバルの始まり,というのがここ数年来のサイクルであった。つまり当地において,マダイ幼魚はメバル漁期終始の指標となり得る)。
⑦11~12月にかけて東系の風が吹き荒れ,北西風が安定せず,沿岸へのシラス来遊が阻害された(東系の風は,北東から南西まで風がめまぐるしく動いていくことが多いため,安定した表層吹送流が形成されず,シラス等表層生活を主とする餌の離散につながる)。
⑧12月あたりから繁茂を開始すべき冬の海草類が発生せず,海藻を生活基盤とする餌生物(ワレカラやエビ・アミ類)は見られなかった。一方,甲殻類の幼生の発生・着底,およびその他の底棲甲殻類の存在は,例年どおりであった。
⑨1月に入っても冬の海藻類の成長は停滞しており,実績漁場において例年産卵の拠り所となる海藻空間は形成されていなかった。一方,1月下旬あたりから,冬の海藻が十分発育しないままに春の海藻が出始めている。
⑩12~1月にかけての積雪は極めて少なく,冬型の低気圧が数回接近したが,雪として残ることはほとんどなく,冷たい降雨が続いた。山間部に積もる雪であれば森林の機能と併せて安定かつ緩やかな陸水栄養分の供給につながるが,低温の雨であれば,降雨後の塩分濃度の変化が大きく,かつ急激な水温の低下につながった。
更に,あまり行かないので断片的ではあるが,境港を少し出た美保湾に接する島根半島の一部およびその先の状況を記しておくと,
⑪11月にかけて,美保湾西部の端に位置する美保関港では,境港エリアの雑賀委託漁場同様,早期から抱卵カサゴ主体で釣れており,メバルはほぼ不在であった。
⑫12月に入り,美保関港では良型・良体型のメバルが単発的に見られたが,全て茶メで,胃内容は空であった。これらは1月に入ると暫時いなくなった。
⑬美保湾外を西へひとつはずれた七類港の褐藻帯では,12月中旬に小型に混じって23㎝前後の中型も出たが,胃は空であり,全てがガリガリの痩せメバルであった。
⑭冬の海藻の生育が悪いのは美保湾に面した側だけであって,島根半島方面になると,例年通りのホンダワラ等褐藻類の繁茂がほぼ例年並みであった。
さてさて,
これら当面14の事実を眺めてみたとき,なんとなく今期現在のメバルの事情が見えてくる。
● メバルの集中接岸を促す湾外部からのサカナ系餌の来遊は,冬季の風向きに支配されやすいということ。従って,今後も外部からの餌供給がない場合には,海岸性の餌の発生のみが索餌接岸のカギを握っているということ。
● シーズン初期の索餌接岸は外部からの餌供給によって決まり,その漁場(湾,堤防)の向きに伴う環流の形成状態によって魚体の差が決まるが,今期は風が変則的であったために各漁場への餌の配分が安定せず,場所(漁場)単位で勝ち組と負け組(太っている,痩せている)がはっきりしていたこと。
● ただし,沿岸性の甲殻類の発生は局所的に例年並みであり,それが漁場ごとの居付き度合いに表れたということ。
● 総じて夏から冬にかけての水温が,産卵接岸の引き金となる海藻帯の形成及び海藻由来の餌発生のカギを握っていること。
● 冬季の降雨・積雪の状況が,沿岸の水温のみならず(おそらくは)栄養塩類の供給という意味でも,海藻および沿岸性餌の発生に大きく影響しており,この点は,半島よりも特に陸水の影響が強い境港エリアで顕著であった
ここから,当地の漁場形成要因を考察し抽出していく。
《 風について 》
例年は安定した北西風が吹く時期に東風が吹き荒れたということなのだが,
まず,北を向いて口をあけている美保湾の沖には,東北東に上がっていく対馬暖流が恒常的に流れており,これの影響を受けた沿岸の潮が,反転流として湾の東端から時計回りに西向きに回っていく。美保湾のサカナは東から来る,と言われる所以だ。
通年ならば,冬季ここに北西風が吹くと,対馬暖流に対して斜め後方からの吹送流が生まれ,対馬暖流縁辺の中にいる西海域で孵化したシラスなどの餌生物が,美保湾の環流に巻き込まれてグルリと接岸し,サカナもこれに付いて移動するというわけだ。
ところが今期多かった東からの風,これは対馬暖流の流れに対して右斜めから押し返す風であるだけでなく,その結果,美保湾に入る反転流の形成を弱め,仮に合間に北寄りの風が吹いて餌が入ってきたとしても,再び東風に戻れば,餌およびそれを追うサカナの湾からの排出を追い風の形で早めてしまう。更に,この時期の東風は南西方向まで振れながら吹くため,せっかく岸に寄った餌を沖へ向けて離散させてしまう。
今期,釣れても短期集中あるいは単発であったひとつの要因が,これだ。
《 潮について 》
潮には,天体の動きに伴う「潮汐」によるものと,風による「吹送流」とがあるが,主に沿岸性餌生物の活動およびメバルの食い気を左右するのが前者,主に外部から供給される餌の種類と量を左右するのが後者である(これが一時的な活性化に貢献することもある)。
今期は,先述した不安定な風環境によって吹送流による餌供給が阻害され,更に後述する続いた冷雨によって湾内への流入水量の変化が激しく,漁場での実質的な潮の動きにも影響が出た。つまり,2タイプの潮の両方ともが変則的であったため,総じて潮汐表に基づいて過去の実績に照らして狙いを定めても不発が多く,その原因が特定しにくかったわけである。
《 水温について 》
水温は,上記,風と潮に加え,陸水の流入も大きく関与し,繊細な餌生物であるシラス等餌となる魚類の孵化率および成長に影響を与えるものであるが,それと並んで影響を受けやすいのが海藻の胞子であり,またそれら着床後の発育である。
これは,産卵環境という意味で,また,春に向けて発生する海藻依存型餌生物の基盤として最も重要。逆に,稚魚を放出する早春に,♀は,稚魚の餌となる生物が確保されやすい海藻帯を産卵場に選択するということでもある。
今期の産卵接岸の停滞は,11月までの高水温,および1~2月にかけての急激な冷水の流入によって,海藻帯が形成されなかったことが大きな原因であろう。
《 餌について 》
結局,釣りの原理を支える餌の事情は,上記相互に不可分の3点,「風・潮・水温」に全て支配されている。あとは元本すなわち親からの“タネ”があるかどうかだ。
とまあ,こうしてみると、なるほど自然は,何が先とは言わずグルグル回っている不可分の世界だ。
【 “それ”はどこにいるのか 】
さて,,,
釣れる釣れないは別にして,岸寄りでは影が薄い今期のメバルが,それではこの時期,どこで何をしているのか。これがやはり疑問として残る。
当然のことながら,どこかで餌を採り繁殖しようとしているのにちがいないのであって,諸事情により今年は産卵をとりやめましたのであしからず,などという器用なマネは,いかに適応性の高いメバルとて極端すぎて無理。
生物の本質をたどれば,「生まれてから死ぬまで食い,その間で子孫を残す」,ということであって,無論サカナも例外ではない。“食う・寝る・休む,子を作る”の4点セットを必ずどこかでやっている。そして我々釣り人からみれば“餌なきところにサカナなし”が基本ではあるが,しかし子作りが食欲より優先されることもあるのが生命の力たるところ。ソレとアレとをたぐっていくと,メバルの動きが見えてくる。端的に言うならば,サケを見よ。餌があろうがなかろうが,子を残すために行くところには行く。餌,ばかりではない。
『通常の索餌のための餌場はどこにできるか』,
『繁殖のために栄養をとる索餌をどこでおこなうか』
『交尾後の♀が産卵するための適地はどこか』
『回復のための索餌の餌場はどこでできるか』。
1月中旬,友人の船に頼んで調査範囲を広げてみたところ,ひとつのヒントが,意外とスンナリ出た。この時期メバルは,『沖で集まっていた』というのが結論だ。
正確に言うと,「集まっていた」のか,接岸のタイミングを「待っていた」のかはわからない。ここでは場所に関する詳細は書かないが,沖合の一定条件を満たした場所では,抱卵良型メバルが,ちゃんと例年並み繁殖期の1月に,しかも連発して釣れた。わかった,もうそれ以上触りなさんなと言って調査終了。
結局,
『メバルの感覚は例年並みであったが,今期の餌およびその他の環境が,索餌や繁殖にとって変則的で条件として整わなかったため,それに応じて許容範囲内での接岸にとどまった』 というのが解釈としては妥当であり,餌的にも,産卵的にも,それらに関わる水温等環境的にも,その限界が沖の漁場であったということなのだろうと推測される。
一度は岸に入ってきて環境が整わなかったから沖に戻ったのか,あるいは沖で必要十分な環境が整ってしまったのでそこから動かなかったのか,はたまた何らかの感受性で岸がダメであることを察知したのか,それはここからはわからない。
が,沖漁場の調査結果から推すれば,1月から2月上旬に単発で抱卵♀が釣れた状況は,メバルが岸寄りはダメだと察知したしたときに,DNAゆえか,それでも例年の場所に行きたくて我慢できず,たまたま体力的に劣環境を乗り越えることができた個体,逆に,よそに産卵適地を探すことが出来なかった個体,そんなヤツが,岸から竿が届く例年並みの範囲に接岸あるいは居残り,結果として単発に釣れていた,というのが真相だと思われる。
おもしろいことに,このような“やせ我慢”タイプはほとんどが赤メ,加えて若干の茶メであった。おしなべて赤メは,メバル3型のうち最も“場”に対する執着が強い。藻や構造物に対する依存度が一番高いのが,この型だ。
人間でも執着が強い人は難儀な目に遭ったりしてますねえ。などと言ったらメバルに失礼。
先述した沖漁場では,1月の中旬段階で既に完熟した放卵寸前個体を多く確認しているわけだが,2月初旬のいまだに♀が接岸していないところをみると,今年の抱卵メバルは,岸よりも“比較的”環境の安定していた沖の中深部海藻帯や構造物周りを中心に産卵を終える見込みだ。
従って,「これから季節が進むにつれて抱卵大型個体が接岸してくれるのではないか,水温が高かったので単に遅れているだけではないか」,といった期待は,すっかり崩れたことになる。
もし今後産卵接岸があるとすれば,ここしばらくのうちに岸寄りの海藻が急速に成長して環境が整ったところに産卵の遅れた♀が接岸する,というような淡い可能性が残されているのみで,今の状況からするとおそらく単発で終わるであろうし,それも,環境が整ったら,の話であって,当方のオカズ供給のアテにはならぬ。だいいち,抱卵メバルは旨くないのだから。
【 メバルは来るか 】
いずれにせよ,次なる懸案として「産卵後のメバルは接岸するやいなや」,という問題が浮上するのであるが,そのカギとなるのは,これまで整理してきたコレとソレとアレだ。
これらの状況によっては沖の漁場に停滞したまま,ということもあり得るはずだが,沖に回復するに足るだけの十分な餌がなければ,必ず岸に回ってくる。これは“来ざるを得ない”。さてどうなるか。
やはり当面の指標としては,海岸で発生する餌。
春の海藻がどこにどれだけ生えるか,そして今年はあるかどうかわからないけれど,稚アユの遡上に先立つ港内迷入,及び春のイカナゴの発生(これは昨年,境港では7年ぶりにあったのだが),これらがあるかどうかに期待している。シラスは既に成長してしまっており,その後どこに行ったのか音沙汰がない。外部から来遊する餌がこのまま入ってこないのであれば,岸寄りで発生する次の餌に期待するしかない。
境港はここ数日,今日も冷たい雨雪が降り続けており,餌にとっても海藻にとっても,当然メバルにとっても快適とは言い難い。しかし,釣りはせずとも日々の観察。ジグヘッドをはずし,糸の先にガン玉つけて,海底を触って歩くだけでもよいではないか。地道な努力はアトほど効いてくる。
*********************************
【 その後の話 】
上記を記した一週間後の今,2月中旬,実績場所で,まとまった数のメバルが出た。
23~25㎝の茶メが4つ,20㎝そこそこが3つ,うち赤メ1,あとは18㎝の茶メが2つ。ささやかではあるが,40分勝負の必要十分量。10月以来,久しぶりのまとまった接岸だ。これは次の時化が来るまでの3日間,潮汐に合わせてずれていったが,遜色ない漁獲が続いた。
胃内容は,茶メではたっぷりの浅海性のアミ類(1㎝前後)と,赤メでは岩礁由来のグソクムシの仲間が少し混じった。海岸由来の餌の発生が始まっている。
これらはいずれも運動能力が低く,特にアミ類は,緩い潮が効いてくると群れで海底から少し浮き上がって定位しながら植物プランクトンを補食する。力のないサカナにとっても苦労なく食える餌で,低水温下・回復期の弱ったメバルにとってはうってつけだ。従ってアタリ方は,ポク,と押さえてしばしじっと動かないような出方をする。
全て茶メの♂ということは,むろんもはや産卵接岸ではない。回復初期の索餌回遊が始まった。
交尾を終えた♀は卵の成熟を待ちつつ暫時沖の適地にて今も産卵中であり,♂は交尾を終えてしまえばフリーなので,回復するべく餌を求めてさっさと移動する,ということで,お先に到着いたしました,というわけだ。卵胎生のメバルならではの摂理と動き。
しかしながら、回復初期だけあって,型は良くても痩せているし,食いはあっても引きが弱い。水温も冷雨で低くなっているので,目の前に餌が来ないと難しい。従って,ベタ底を舐めるデッドスローが基本。
そして潮。一般的に潮が流れれば食いが立つと考えられがちであるが,沿岸性アミ類を食っているときのメバルは単純にそういうものでもない。むろん動かなければダメなのであるが、かといって一方的な強い潮であれば,アミ類は海底の淀みに沈んで固まるか一方向に流されてしまうので,結局潮が止まっても流れすぎても食いが悪い。従って,潮が小さく頻繁に行きつ戻りつしているとき,すなわち,日本海では大潮周りの潮位差が少ないとき,アミの群れは海底に立つ。これが時合いの狙い目だ。
それにしても大切なのは誘い。
早春に発生して潮に対して定位しながら底層に群れを形成するアミ類が,どのような動きをするか,皆様,ご存じでしょうか。これを竿で表現するのは,ちょいと難しい。まず長い竿ではできない。張りのない竿ではできない。かといって,アタリ方は小さいので穂先が繊細でなければいけない。そんな竿はあるのか?。
このお話は,まとめてまた後日。
先週、念のため,再び船を頼んで沖の漁場に行ってみると,♀の産卵が終盤になったとみえて,げっそり痩せた♀が見え始めた。やはり接岸しないまま沖で産卵を終えつつあるようだ。比較的藻場が形成されている半島方面では,どうであろうか。尺も出ているらしいのであるが,それが♂なのか♀なのか,型(3型)は、そして胃内容物は何なのか,そこがいちばん気になるところ。
境港は,西は宍道湖・中海・境水道,東は日野川から由来する大量の陸水の流入があり,また流入先である円弧型の美保湾は,島根半島と大山に挟まれて気象や海洋環境が独特だし,おそらくこの地から導き出された考察は,ここでは通用したとしても仮に日本海の近隣であっても適用できない可能性がある。とはいえ今日にあっては日本沿岸全体の連動的な海の変化も見逃せない状況なので,それだけに同時期の他の地域の状況が知りたいと思う次第,
全国メバル釣り師による状況分析ネットワーク,地域ごとの特派員,みたいな体制ができたら,もっといろんなオモシロイことが見えてくるのだが,誰か一緒にやらんかなあ。
特に気になるのは,日本海と瀬戸内海との連動性だ。両者とも,山脈を挟んで南北に並んだ大きな池みたいな海。たとえばアジ,シラス,これらの同時期の体長のバラツキは,日本海と瀬戸内海で時期が同じでなくとも,2年前からひとつの傾向として表れている。これが意味するところは何なのか。ひいては,これから変わって行くであろう海を相手に,釣り人は,漁師は,サカナを食べる我々は,何を考え,どうしていったらよいのか,それを釣りや食や水産業を通して模索するのが,当家の目下の課題だ。
ま,何事も変則的な今年ですから,せいぜいアタマを柔らかくして構えておきましょう。これからどうなるかは予断を許さぬところゆえ。
少なくとも春の餌は徐々に発生し始めたようなので,早晩まずまずのメバルは寄ると見ている。港湾オカズ釣り師としては,もう少し旨くなるまで,いましばらく,控えめにモニターしておくこととしたい。
2007年12月12日
境港発 今期のメバルをとりまく事情 2007
フト気づけば,あれまあ,2ヶ月も更新できていなかったという現実。まことにお恥ずかしい次第。本業に追われていたこともあるが,それよりも,今期のメバル事情の異変を追究するのに余念がなかった,というのも事実。今回はそのへんのお話を少し。
【昨今の海】
今年の冬は水温低下が極めて遅い。漁師も釣り人も,口を揃えて水温高いと言っている。むろん気温の低下が遅いこともあるし,気温が高ければ当然それに伴い風や雨なども影響を受ける。このところ年毎に台風は大型化し,かつ9月を過ぎてもダラダラやってくるようになった。
境港を出入港するカニカゴ船や,大型底引き網,まき網など,そこそこ遠方までサカナを獲りに行く漁船は,いよいよ天候と潮との勝負が深刻である。それだけに,変化しつつある気象を読んで他の船が出漁せぬタイミングでうまくサカナを獲って入れる船は,いい稼ぎができる。漁業にも,これまでとは頭ひとつ別のセンスが求められる時代となったということか。さておき・・・,
もはや「地球温暖化」というやつが陸・海・空に影響しているのは明らかで,この用語も今では半ば常識化してしまった感がある。海洋におけるその予兆は,思い起こせば捕鯨船に乗っていた10年ほど前から既に徐々に始まっていた。
たとえば,南氷洋の氷山が崩壊する量が増えて氷原となって船の航行を妨げたり,太陽光が突き刺すように肌を刺し,日焼けの跡がシミとなる,といった具合で,当時は,オゾンホールが大きくなってるのかね,くらいなもので,半年の航海を経て日本に戻れば極めていつもの懐かしい日本の四季であったのであるが,その後,マグロはえ縄船に乗るようになって3年目,太平洋南東部のメバチ漁船の船頭達が,これまで蓄積したデータが役に立たんと言い出したのが,今につながる急激な変化の始まりだった。
マグロ船の船頭は,360度水平線,水深1,000m以上の大海原でマグロの通り道を探し当てそれを釣る。であるから当然,漁師のカンだけでは獲れるわけがなく,過去の経験・知識の蓄積量がものを言う漁業なだけに大きな海洋環境の変化は商売上深刻であったと思う。ちょうど5年前,2002年あたりであったろうか。
同時期,夏場に手伝いに行っていた長崎県野母崎のイセエビ刺し網に「スジアラ」だとか,「キハッソク」といった,その道60年の地元ベテラン漁師でも見たことさえない南方系というか,むしろ熱帯魚のようなサカナが掛かり始め,その後日本海の仕事で境港に移ってきた3年前あたりからは,山陰沖のまき網に「スギ」とか「オキアジ」などという,これまた南の連中が頻繁に入るようになり,島根県の隠岐島では,本来“死滅回遊”であるはずの「アイゴ」が,とうとう越冬するに至った。同様に,今年はあのハリセンボンまでが境の港内で越冬している。
ちなみに“死滅回遊”とは,南方系のサカナが潮流に乗って北上したとき,低水温のため南に戻って来れずに死滅する,いわば死出の旅のことをいい,これまで長きにわたり多くの南方系魚類が潮に流され北上しては順調(?)に死亡していたのである。
現在のところ,越冬はできても繁殖までしているかどうかは定かでないが,もしそうなれば,それはもうそのサカナの“種”としての「分布・繁殖水域」が塗り変られるということなのだ。
更に時期を同じくして,瀬戸内海でもおかしなことが始まった。それが2年前の春あたりからで,当地の春の味覚であるシラス(主にカタクチイワシの稚魚)やイカナゴのサイズが揃わなくなってきたのである。つまり,通常であればこれらのサカナは,漁期が始まるとまず小さいものが獲れ始め,時期が進むにつれ徐々に大型化してくるのだが,初めから大小“混じり”で獲れるようになり,この傾向は今年も続いている。これはイケナイ。
煮上がった姿が曲がった錆び釘に似る,いわゆる「釘煮」というイカナゴの佃煮は,兵庫県播磨地方一帯の季節の風物としてつとに有名であるが,これは材料とするサカナのサイズが揃っているのが前提で,バラバラであれば煮上がりにムラを生じる。煮ムラがあれば,同じ鍋で煮ても魚体が折れてしまって“釘”にならない。従ってサイズがバラバラだと値段が低くなってしまうわけだが,かといって2㎝ばかりの細いサカナを選別するわけにもいかない。
振り返って境港。
瀬戸内海で稚魚類の成長にバラツキが見られた同年,隠岐島のまき網で獲れるマアジのサイズにもバラツキが出た。その傾向は春を過ぎ夏になってもおさまらず,秋になった。
秋から釣れ始めてロングランとなったアオリイカの群れも,必ずしも順調に成長したわけではなく,冬の気配がした頃に,なんでこんなサイズが,と思うような小型個体がチョロチョロしていた。推するに,群れごとに産卵が分かれて長期化したか,あるいは,考えにくいことではあるが,本来は年に1回しか産卵しないはずのイカが,多回産卵していたのか,ということだ。
それだけではない。例年,同じマアジでも,沖合いを通過していく“クロアジ系”の抱卵は初夏,沿岸に居付く“キアジ系”のそれは晩夏であったが,クロアジの抱卵が早まり,キアジのそれは遅れて秋にもつれ込んだ。そのせいもあり,例年冬場にワームで欲しいだけ入れ食いとなる中型キアジの脂の乗りは,ここ4年間で過去最低だ。このまま太らぬまま沖へ去るのか,それとも漁期が遅くまでズレ込むのか。
一方,根魚であるカサゴの抱卵が1ヶ月早まり,アカミズのそれは1ヶ月遅れた。アジも根魚も,その抱卵は二極化し,あたかも記録的な猛暑を迎えた今年の夏の高水温を避けるが如くであった。
「南方からの来遊魚の増加」,「潮流に乗って運ばれる稚魚のサイズのバラツキ」,そして「親魚の産卵時期のズレ」,これらを総合的にみて推測できるのは,まず「潮が乱れている」ということだ。それも,魚釣りで言う潮のヨレといった小さなレベルではなく,たとえば日本海を北上する対馬暖流の勢いや,それが沖合い通過時に生じる大型の反転流の数々といった規模で。このところ釣り場の潮の緩・急が激しくなっていることからみても,おそらく間違いなかろう。なぜなら,日ごろ我々が釣っている沿岸の漁場は,沖合いの海洋構造の末端であるからだ。
ここで思い当たるのが,このところ各所でささやかれる高水温の問題で,たとえば,高い気温で暖められた水が表層を流れるとき,通り過ぎたあとには下にある冷たい海水が上がってくるといった現象が見られるが,そのエネルギーは,両者の温度差が大きいほど,大きくなる。三次元的に,かき回され,乱れる,といった強さが,より大きくなる。これが大規模に起こるとすれば,それぞれの場所で,例年と違う水温の潮が入ってきて,そこにいる親魚の産卵期が局所的にズレたり,本来ならば一定に近い順調な潮に流されながら孵化し成長する稚魚が,水温の異なる潮に巻き込まれて一部成長不良を起こしたり,死滅したり,あるいは還流によって押し戻されたり,てなことが起こっても不思議ではない。
いずれにしても,自然界というものは,よく観察していると,すべからく“安定”の方向に動いているので,おそらくこれらの乱れはひとつの安定に至るための過程に過ぎないであろう。
しかし問題は,自然界の“ひとつの過程”,“一時的なもの”,という時間の大きさが,必ずしも人間にとって一時的に感じるとは限らない,ということであって,少なくともこのところの急激な海・陸の環境変化は,かつて人間が体験したことのない事態であることに変りはないし,また,これから行き着こうとしている自然界としての安定が,必ずしも今のニンゲンにとって都合の良い状態とは限らない。
これまで自然界も我慢をして緩やかに変化する程度で収まってきたが,いよいよそれではもたなくなってきた,ということか。簡単に言えば,我々人間の“ツケ”が溜まってしまった,ということではないかと思う。自然界というものは,極めて合理的にできており,ツケは本来許されない。それをちゃんと払わなければ,恩恵ももたらさぬ。ね,オトーサン,夜の巷のバーだって,最近はそうではないか。ニコニコ現金払い。これが大切。
******************************
【境港におけるメバルの状況】
あ,前置きが長くなり恐縮。“今期のメバル”,の話です。
以上述べてきたかかる状況の中,湧きに湧いて,今年から初めました!というジーちゃん・お子様までこぞって釣った今年の秋のアオリイカが終盤となり,11月中旬あたりから,メバルを狙う若者がポツポツお目見えし,地元の釣具屋にもモエビを置くようになった。遅れに遅れたメバル釣り,いよいよ開幕か?,と思いきや,当地境港から島根半島にかけての情報はパッとしないのである。半島方面でさえ,いわく,20cm止まりですな,と。
確かにウチの手持ち実績漁場のひとつでも,過去三年間を通じて12月に入れば確実に20cm超え型揃いのメバルが1時間ほどで10尾ばかりは釣れるはずのピンスポットでは,いまだに18cm止まりがポツリポツリであるし,同じ場所で,例年この時期定番の沖目の離れ瀬をデッドスローで舐めてみても,尺前後の“ビッグワン”が出ない。出ないどころか,連発で掛かってくるのは18㎝に満たないマイクロカサゴ。
実は同場所に毎日来ている餌釣り師に,同じ場所で2回だけ10月上旬に大釣りがあって,25cmを頭に15尾,といったこともあったが,その後全く安定せず,また,この時期にして2回だけ,という単発さは異常であった。
しかもこの時期,例年ならほとんど茶メバルで占められているはずのところ,青(クロ)が,かなり混じっているのである。
同時期10月中旬,私は,今年新たに開拓した場所,といっても,他の過去実績場所ではほとんどといっていいくらいにメバルが釣れなかったので新規開拓に漕ぎ着けた場所なのであるが,そこで,23~27cmを,2週間にわたり,毎日のように3尾ずつ釣ってはオカズ場としていた。一日3尾にとどめたのは,今シーズンの持続的漁場,すなわち,“冷蔵庫がわり”になると踏んだからだ。
不思議なことに,例年実績のある場所はカラッキシダメ,であり,その場所だけでしか釣れなかった。そこしか釣れなかったけれど,そこでは確実に釣ることができた。ただし,胃内容物は,全て1㎜ほどのカニのメガロパ幼生で,いわば“粒食”みたいなもの。これを食っているメバルを釣るには,通常のワーム釣りではダメで,ちょいとしたコツがいるのだったが。
その後,11月半ばには別場所で20~30cmのマアジが入れ食いシーズンに入ったので,そちらで日々の糊口をしのいでいたが,過日,久しぶりにメバルを食いたくなって,その場所に行ってみた。
ところが,10月にあの調子だったのだから,さぞかし12月は・・・,と期待してやってみたところ・・・,最大でも20cm,それどころか,10cmほどの“マイクロメバル”が多数つついてくるではないか。え?こんなものがこの時期に??・・・。そして,期せずして20~25cmの肥えたカサゴがバタバタと・・・。
これはオカズ的には嬉しくはあるが,やはりオカシイ。というか,今年は,他にもうひとつ新規開拓した急流停滞漁場で尺前後のカサゴが2発出ているのだが,本来,良型のカサゴの接岸は年明けて,初春,それも2月に入ってからが最盛期ではなかったか。
そもそも例年,シーズンはじめにはそこそこの型のメバルがしっかり接岸し,それを釣っているうちに抱卵成熟が始まるので,メスの抱卵モノをリリースする分をカサゴで補って,カサゴが産卵期を迎えるとメバルでは産卵後の回復が始まって,いよいよ春の最盛期を迎え,カサゴは沖に去り,メバルの一部は居つき,尺も出るし,それぞれ初夏にかけていよいよ肥えて旨みを増す,というような感じなのだが,今年はハナッからこのローテーションが通用しない様子だ。
******************************
さてさて,これから先,どうなるものやら。
昨年を振り返ってみると,周年けっこうイイカンジで釣っていたようだ。
10月中旬に中型茶メバルが始まり,11月は合間に金アジ(キアジ系マアジ)をやりつつ12~2月はカサゴ混じり,3月あたりから小さい赤メバルが湧いてくるので沖の離れ瀬に居付く大型茶メバルに移行し,4~5月は潮目付きの中型茶メバルと海藻着きの赤メバルを型揃いで毎日釣って,6~8月は急流場所で脂が乗った小・中型茶~青メバルの数釣りと副産物のスズキとアカミズ,別の深場に大型黒メバルが付いたらそれを獲り,9月に入ったらスズキでヒマをつぶしたり,たまには船で大アカミズや大カサゴ,片手間にワタリガニやトビウオを掬ったり,ということで,オカズに困ることは,まずなかった。
メバルに限定して言えば,使用漁場は4カ所のみ。いずれも境港周辺で,いわゆる“スキマ”開拓で得た優良漁場である。たまにおつきあいで島根半島に行ったり,イカやサワラにちょっかいを出したりすることもあったが,数えるほどでもない。私のメインターゲットは,その時期に応じた旨いメバル(3型とサイズの選択)とカサゴ,そして冬場に接岸する脂の乗ったキアジ,この3種である。これだけで1年が回っていくのだから,境港の底力もたいしたものだ。
境港に来て3年が経ち,時期ごと・魚種ごとの漁場の確保とそれらの使いまわしも安定し,ようやく周年を通じてサカナの供給に心配がなくなった矢先,今年の異変は痛かった。これまでのところ,かろうじてオカズ確保はできているが,このままの状況が続くのであれば,漁場利用計画を設計しなおさねばならない。あるいは毎年更新しなければならない可能性も出てくる。
いかなる状況になろうとも,釣りというものは,漁であり,すなわち変化する自然に則さねば成立しない。初心に戻り,今年を新たにメバル釣り元年とするのもよい。各地のメバル狙う諸氏は,そのへんの諸事情如何。まだ来ていないとみるか,あるいは思わぬところに,メバルはいるのかも知れぬ。
と,いうような状況であるから,ここしばらくは日々の釣行1回ごとの観察および考察が,今期(来年の夏まで)のサカナ供給につながる。要は,「何を見るか」だ。漁場成立の目安となるのは何か,ということ。
******************************
【漁場の指標】
たとえば,境港界隈とひとことに言っても,地形や海況によって,指標となるものが違う。どのような状態のどのようなサイズがどれだけ釣れるか,ということは直接的な指標であってわかりやすくはあるが,釣れない=良くない漁場,釣れる=良い漁場,といった型にはまり込みやすい。ひいては,釣れない=サカナがいない,ということにもなりかねない。つまり,直接的な指標のみでは,その漁場の対象魚の現状はわかっても,今後の可能性についてまでは推測しにくいのである。
そこで,どのようなものを見ていくかと言えば,まず生物と非生物の2つに大別できる。①その他の生物の状況。たとえばあるサカナが釣れている限りは水温がまだ高いのでメバルは来ない,あるいはあるサカナが出現したらメバルの漁期は終わり,といった具合。これは,実体験上,かなり相関性が高い。“あるサカナ”は,サカナとは限らない。海藻であったり,その他の生物であったり。また,ひと目でそれと確認できる大きな生物とも限らない。
なぜ,このような視点が有効かというと,ひとえに“自然界は全てが網の目のように連鎖して動いている”からである。当然のことながら,目的のサカナがそこに居て,かつ釣れてくれるためには,そのサカナがそこで餌を追っている必要がある。その餌はどこか。その餌の拠り所となる環境は何か。そして餌の蝟集・拡散と連動する指標は何か,といったことを丁寧に見つめていくと,その延長に,目的のサカナは居る。あとは,どのように釣るかである。
そして,②餌生物の動向に影響をもたらす非生物的要因。これは,たとえば風向きによってはシラスがある特定の場所に吹き溜まる,とか,波が岸壁を叩いて餌生物が落下・漂流しやすい潮位・流向とか,餌生物が発生したり,目的のサカナが警戒心を解きやすい潮の濁りや雨・雪など,等々。これらも,またひとつの指標となる。
いずれにせよ,短絡に陥ることなく,急がず騒がず,丁寧・つぶさに見てみること,これに尽きる。
その中で,毎年,何がカギとなる要素か,がだんだんわかってくるというものだ。そのカギは,大量の観察を通していくつか端的に集約される。
参考までに申し上げると,今期のメバルに関する私のカギは,
①昨シーズン7年ぶりに湧いたイカナゴが,今年も湧くか。
②春の海藻,初夏の海藻の成長如何。
③北西風主体の天候となるのはいつか。
漁場は既に押さえてあるのだから,あとはこの3点を中心にその周辺を追究し、状況に合わせて場所と釣り方を変えていく。
******************************
釣魚をオカズという位置づけにし,必要十分量をいかに確実に獲るかをテーマとして釣りを続けていくと,やもすると,釣りを始めた初心のヨロコビ,たとえば単純に釣れてウレシイ,大きくてウレシイ,たくさん釣れてウレシイ,といったような童心を忘れがちのようにも思う。
だが一方,過去ログ“スキマの釣り”でも書いたかもしれないが,生物としての自己認識,生きている核心および食いつ食われつする生命のせめぎ合いから発生する力,といったものが静かに自分の中に湧き出でて,これまた別の次元のヨロコビを味わうことができるものだ。
このヨロコビとは何だろな,と思いめぐらしてみると,意外や,気の遠くなるような広大な世界の中で,いつか死ぬために他の生き物を食って生きている,極めて小さな自分の確認だったりする。これが動かぬ事実だ。それ以外のことは,実はおそらく,我々の勝手な錯覚・妄想の類なのではあるまいか。
しかし時にはそれに支えられて生きてゆくのも,またニンゲンだ。けなげにも思えるし,そう悪いことばかりではない。かく言う私も,釣りをしながらこんなことを書きつつ死に向かって生きている。
愉快なり。
【昨今の海】
今年の冬は水温低下が極めて遅い。漁師も釣り人も,口を揃えて水温高いと言っている。むろん気温の低下が遅いこともあるし,気温が高ければ当然それに伴い風や雨なども影響を受ける。このところ年毎に台風は大型化し,かつ9月を過ぎてもダラダラやってくるようになった。
境港を出入港するカニカゴ船や,大型底引き網,まき網など,そこそこ遠方までサカナを獲りに行く漁船は,いよいよ天候と潮との勝負が深刻である。それだけに,変化しつつある気象を読んで他の船が出漁せぬタイミングでうまくサカナを獲って入れる船は,いい稼ぎができる。漁業にも,これまでとは頭ひとつ別のセンスが求められる時代となったということか。さておき・・・,
もはや「地球温暖化」というやつが陸・海・空に影響しているのは明らかで,この用語も今では半ば常識化してしまった感がある。海洋におけるその予兆は,思い起こせば捕鯨船に乗っていた10年ほど前から既に徐々に始まっていた。
たとえば,南氷洋の氷山が崩壊する量が増えて氷原となって船の航行を妨げたり,太陽光が突き刺すように肌を刺し,日焼けの跡がシミとなる,といった具合で,当時は,オゾンホールが大きくなってるのかね,くらいなもので,半年の航海を経て日本に戻れば極めていつもの懐かしい日本の四季であったのであるが,その後,マグロはえ縄船に乗るようになって3年目,太平洋南東部のメバチ漁船の船頭達が,これまで蓄積したデータが役に立たんと言い出したのが,今につながる急激な変化の始まりだった。
マグロ船の船頭は,360度水平線,水深1,000m以上の大海原でマグロの通り道を探し当てそれを釣る。であるから当然,漁師のカンだけでは獲れるわけがなく,過去の経験・知識の蓄積量がものを言う漁業なだけに大きな海洋環境の変化は商売上深刻であったと思う。ちょうど5年前,2002年あたりであったろうか。
同時期,夏場に手伝いに行っていた長崎県野母崎のイセエビ刺し網に「スジアラ」だとか,「キハッソク」といった,その道60年の地元ベテラン漁師でも見たことさえない南方系というか,むしろ熱帯魚のようなサカナが掛かり始め,その後日本海の仕事で境港に移ってきた3年前あたりからは,山陰沖のまき網に「スギ」とか「オキアジ」などという,これまた南の連中が頻繁に入るようになり,島根県の隠岐島では,本来“死滅回遊”であるはずの「アイゴ」が,とうとう越冬するに至った。同様に,今年はあのハリセンボンまでが境の港内で越冬している。
ちなみに“死滅回遊”とは,南方系のサカナが潮流に乗って北上したとき,低水温のため南に戻って来れずに死滅する,いわば死出の旅のことをいい,これまで長きにわたり多くの南方系魚類が潮に流され北上しては順調(?)に死亡していたのである。
現在のところ,越冬はできても繁殖までしているかどうかは定かでないが,もしそうなれば,それはもうそのサカナの“種”としての「分布・繁殖水域」が塗り変られるということなのだ。
更に時期を同じくして,瀬戸内海でもおかしなことが始まった。それが2年前の春あたりからで,当地の春の味覚であるシラス(主にカタクチイワシの稚魚)やイカナゴのサイズが揃わなくなってきたのである。つまり,通常であればこれらのサカナは,漁期が始まるとまず小さいものが獲れ始め,時期が進むにつれ徐々に大型化してくるのだが,初めから大小“混じり”で獲れるようになり,この傾向は今年も続いている。これはイケナイ。
煮上がった姿が曲がった錆び釘に似る,いわゆる「釘煮」というイカナゴの佃煮は,兵庫県播磨地方一帯の季節の風物としてつとに有名であるが,これは材料とするサカナのサイズが揃っているのが前提で,バラバラであれば煮上がりにムラを生じる。煮ムラがあれば,同じ鍋で煮ても魚体が折れてしまって“釘”にならない。従ってサイズがバラバラだと値段が低くなってしまうわけだが,かといって2㎝ばかりの細いサカナを選別するわけにもいかない。
振り返って境港。
瀬戸内海で稚魚類の成長にバラツキが見られた同年,隠岐島のまき網で獲れるマアジのサイズにもバラツキが出た。その傾向は春を過ぎ夏になってもおさまらず,秋になった。
秋から釣れ始めてロングランとなったアオリイカの群れも,必ずしも順調に成長したわけではなく,冬の気配がした頃に,なんでこんなサイズが,と思うような小型個体がチョロチョロしていた。推するに,群れごとに産卵が分かれて長期化したか,あるいは,考えにくいことではあるが,本来は年に1回しか産卵しないはずのイカが,多回産卵していたのか,ということだ。
それだけではない。例年,同じマアジでも,沖合いを通過していく“クロアジ系”の抱卵は初夏,沿岸に居付く“キアジ系”のそれは晩夏であったが,クロアジの抱卵が早まり,キアジのそれは遅れて秋にもつれ込んだ。そのせいもあり,例年冬場にワームで欲しいだけ入れ食いとなる中型キアジの脂の乗りは,ここ4年間で過去最低だ。このまま太らぬまま沖へ去るのか,それとも漁期が遅くまでズレ込むのか。
一方,根魚であるカサゴの抱卵が1ヶ月早まり,アカミズのそれは1ヶ月遅れた。アジも根魚も,その抱卵は二極化し,あたかも記録的な猛暑を迎えた今年の夏の高水温を避けるが如くであった。
「南方からの来遊魚の増加」,「潮流に乗って運ばれる稚魚のサイズのバラツキ」,そして「親魚の産卵時期のズレ」,これらを総合的にみて推測できるのは,まず「潮が乱れている」ということだ。それも,魚釣りで言う潮のヨレといった小さなレベルではなく,たとえば日本海を北上する対馬暖流の勢いや,それが沖合い通過時に生じる大型の反転流の数々といった規模で。このところ釣り場の潮の緩・急が激しくなっていることからみても,おそらく間違いなかろう。なぜなら,日ごろ我々が釣っている沿岸の漁場は,沖合いの海洋構造の末端であるからだ。
ここで思い当たるのが,このところ各所でささやかれる高水温の問題で,たとえば,高い気温で暖められた水が表層を流れるとき,通り過ぎたあとには下にある冷たい海水が上がってくるといった現象が見られるが,そのエネルギーは,両者の温度差が大きいほど,大きくなる。三次元的に,かき回され,乱れる,といった強さが,より大きくなる。これが大規模に起こるとすれば,それぞれの場所で,例年と違う水温の潮が入ってきて,そこにいる親魚の産卵期が局所的にズレたり,本来ならば一定に近い順調な潮に流されながら孵化し成長する稚魚が,水温の異なる潮に巻き込まれて一部成長不良を起こしたり,死滅したり,あるいは還流によって押し戻されたり,てなことが起こっても不思議ではない。
いずれにしても,自然界というものは,よく観察していると,すべからく“安定”の方向に動いているので,おそらくこれらの乱れはひとつの安定に至るための過程に過ぎないであろう。
しかし問題は,自然界の“ひとつの過程”,“一時的なもの”,という時間の大きさが,必ずしも人間にとって一時的に感じるとは限らない,ということであって,少なくともこのところの急激な海・陸の環境変化は,かつて人間が体験したことのない事態であることに変りはないし,また,これから行き着こうとしている自然界としての安定が,必ずしも今のニンゲンにとって都合の良い状態とは限らない。
これまで自然界も我慢をして緩やかに変化する程度で収まってきたが,いよいよそれではもたなくなってきた,ということか。簡単に言えば,我々人間の“ツケ”が溜まってしまった,ということではないかと思う。自然界というものは,極めて合理的にできており,ツケは本来許されない。それをちゃんと払わなければ,恩恵ももたらさぬ。ね,オトーサン,夜の巷のバーだって,最近はそうではないか。ニコニコ現金払い。これが大切。
******************************
【境港におけるメバルの状況】
あ,前置きが長くなり恐縮。“今期のメバル”,の話です。
以上述べてきたかかる状況の中,湧きに湧いて,今年から初めました!というジーちゃん・お子様までこぞって釣った今年の秋のアオリイカが終盤となり,11月中旬あたりから,メバルを狙う若者がポツポツお目見えし,地元の釣具屋にもモエビを置くようになった。遅れに遅れたメバル釣り,いよいよ開幕か?,と思いきや,当地境港から島根半島にかけての情報はパッとしないのである。半島方面でさえ,いわく,20cm止まりですな,と。
確かにウチの手持ち実績漁場のひとつでも,過去三年間を通じて12月に入れば確実に20cm超え型揃いのメバルが1時間ほどで10尾ばかりは釣れるはずのピンスポットでは,いまだに18cm止まりがポツリポツリであるし,同じ場所で,例年この時期定番の沖目の離れ瀬をデッドスローで舐めてみても,尺前後の“ビッグワン”が出ない。出ないどころか,連発で掛かってくるのは18㎝に満たないマイクロカサゴ。
実は同場所に毎日来ている餌釣り師に,同じ場所で2回だけ10月上旬に大釣りがあって,25cmを頭に15尾,といったこともあったが,その後全く安定せず,また,この時期にして2回だけ,という単発さは異常であった。
しかもこの時期,例年ならほとんど茶メバルで占められているはずのところ,青(クロ)が,かなり混じっているのである。
同時期10月中旬,私は,今年新たに開拓した場所,といっても,他の過去実績場所ではほとんどといっていいくらいにメバルが釣れなかったので新規開拓に漕ぎ着けた場所なのであるが,そこで,23~27cmを,2週間にわたり,毎日のように3尾ずつ釣ってはオカズ場としていた。一日3尾にとどめたのは,今シーズンの持続的漁場,すなわち,“冷蔵庫がわり”になると踏んだからだ。
不思議なことに,例年実績のある場所はカラッキシダメ,であり,その場所だけでしか釣れなかった。そこしか釣れなかったけれど,そこでは確実に釣ることができた。ただし,胃内容物は,全て1㎜ほどのカニのメガロパ幼生で,いわば“粒食”みたいなもの。これを食っているメバルを釣るには,通常のワーム釣りではダメで,ちょいとしたコツがいるのだったが。
その後,11月半ばには別場所で20~30cmのマアジが入れ食いシーズンに入ったので,そちらで日々の糊口をしのいでいたが,過日,久しぶりにメバルを食いたくなって,その場所に行ってみた。
ところが,10月にあの調子だったのだから,さぞかし12月は・・・,と期待してやってみたところ・・・,最大でも20cm,それどころか,10cmほどの“マイクロメバル”が多数つついてくるではないか。え?こんなものがこの時期に??・・・。そして,期せずして20~25cmの肥えたカサゴがバタバタと・・・。
これはオカズ的には嬉しくはあるが,やはりオカシイ。というか,今年は,他にもうひとつ新規開拓した急流停滞漁場で尺前後のカサゴが2発出ているのだが,本来,良型のカサゴの接岸は年明けて,初春,それも2月に入ってからが最盛期ではなかったか。
そもそも例年,シーズンはじめにはそこそこの型のメバルがしっかり接岸し,それを釣っているうちに抱卵成熟が始まるので,メスの抱卵モノをリリースする分をカサゴで補って,カサゴが産卵期を迎えるとメバルでは産卵後の回復が始まって,いよいよ春の最盛期を迎え,カサゴは沖に去り,メバルの一部は居つき,尺も出るし,それぞれ初夏にかけていよいよ肥えて旨みを増す,というような感じなのだが,今年はハナッからこのローテーションが通用しない様子だ。
******************************
さてさて,これから先,どうなるものやら。
昨年を振り返ってみると,周年けっこうイイカンジで釣っていたようだ。
10月中旬に中型茶メバルが始まり,11月は合間に金アジ(キアジ系マアジ)をやりつつ12~2月はカサゴ混じり,3月あたりから小さい赤メバルが湧いてくるので沖の離れ瀬に居付く大型茶メバルに移行し,4~5月は潮目付きの中型茶メバルと海藻着きの赤メバルを型揃いで毎日釣って,6~8月は急流場所で脂が乗った小・中型茶~青メバルの数釣りと副産物のスズキとアカミズ,別の深場に大型黒メバルが付いたらそれを獲り,9月に入ったらスズキでヒマをつぶしたり,たまには船で大アカミズや大カサゴ,片手間にワタリガニやトビウオを掬ったり,ということで,オカズに困ることは,まずなかった。
メバルに限定して言えば,使用漁場は4カ所のみ。いずれも境港周辺で,いわゆる“スキマ”開拓で得た優良漁場である。たまにおつきあいで島根半島に行ったり,イカやサワラにちょっかいを出したりすることもあったが,数えるほどでもない。私のメインターゲットは,その時期に応じた旨いメバル(3型とサイズの選択)とカサゴ,そして冬場に接岸する脂の乗ったキアジ,この3種である。これだけで1年が回っていくのだから,境港の底力もたいしたものだ。
境港に来て3年が経ち,時期ごと・魚種ごとの漁場の確保とそれらの使いまわしも安定し,ようやく周年を通じてサカナの供給に心配がなくなった矢先,今年の異変は痛かった。これまでのところ,かろうじてオカズ確保はできているが,このままの状況が続くのであれば,漁場利用計画を設計しなおさねばならない。あるいは毎年更新しなければならない可能性も出てくる。
いかなる状況になろうとも,釣りというものは,漁であり,すなわち変化する自然に則さねば成立しない。初心に戻り,今年を新たにメバル釣り元年とするのもよい。各地のメバル狙う諸氏は,そのへんの諸事情如何。まだ来ていないとみるか,あるいは思わぬところに,メバルはいるのかも知れぬ。
と,いうような状況であるから,ここしばらくは日々の釣行1回ごとの観察および考察が,今期(来年の夏まで)のサカナ供給につながる。要は,「何を見るか」だ。漁場成立の目安となるのは何か,ということ。
******************************
【漁場の指標】
たとえば,境港界隈とひとことに言っても,地形や海況によって,指標となるものが違う。どのような状態のどのようなサイズがどれだけ釣れるか,ということは直接的な指標であってわかりやすくはあるが,釣れない=良くない漁場,釣れる=良い漁場,といった型にはまり込みやすい。ひいては,釣れない=サカナがいない,ということにもなりかねない。つまり,直接的な指標のみでは,その漁場の対象魚の現状はわかっても,今後の可能性についてまでは推測しにくいのである。
そこで,どのようなものを見ていくかと言えば,まず生物と非生物の2つに大別できる。①その他の生物の状況。たとえばあるサカナが釣れている限りは水温がまだ高いのでメバルは来ない,あるいはあるサカナが出現したらメバルの漁期は終わり,といった具合。これは,実体験上,かなり相関性が高い。“あるサカナ”は,サカナとは限らない。海藻であったり,その他の生物であったり。また,ひと目でそれと確認できる大きな生物とも限らない。
なぜ,このような視点が有効かというと,ひとえに“自然界は全てが網の目のように連鎖して動いている”からである。当然のことながら,目的のサカナがそこに居て,かつ釣れてくれるためには,そのサカナがそこで餌を追っている必要がある。その餌はどこか。その餌の拠り所となる環境は何か。そして餌の蝟集・拡散と連動する指標は何か,といったことを丁寧に見つめていくと,その延長に,目的のサカナは居る。あとは,どのように釣るかである。
そして,②餌生物の動向に影響をもたらす非生物的要因。これは,たとえば風向きによってはシラスがある特定の場所に吹き溜まる,とか,波が岸壁を叩いて餌生物が落下・漂流しやすい潮位・流向とか,餌生物が発生したり,目的のサカナが警戒心を解きやすい潮の濁りや雨・雪など,等々。これらも,またひとつの指標となる。
いずれにせよ,短絡に陥ることなく,急がず騒がず,丁寧・つぶさに見てみること,これに尽きる。
その中で,毎年,何がカギとなる要素か,がだんだんわかってくるというものだ。そのカギは,大量の観察を通していくつか端的に集約される。
参考までに申し上げると,今期のメバルに関する私のカギは,
①昨シーズン7年ぶりに湧いたイカナゴが,今年も湧くか。
②春の海藻,初夏の海藻の成長如何。
③北西風主体の天候となるのはいつか。
漁場は既に押さえてあるのだから,あとはこの3点を中心にその周辺を追究し、状況に合わせて場所と釣り方を変えていく。
******************************
釣魚をオカズという位置づけにし,必要十分量をいかに確実に獲るかをテーマとして釣りを続けていくと,やもすると,釣りを始めた初心のヨロコビ,たとえば単純に釣れてウレシイ,大きくてウレシイ,たくさん釣れてウレシイ,といったような童心を忘れがちのようにも思う。
だが一方,過去ログ“スキマの釣り”でも書いたかもしれないが,生物としての自己認識,生きている核心および食いつ食われつする生命のせめぎ合いから発生する力,といったものが静かに自分の中に湧き出でて,これまた別の次元のヨロコビを味わうことができるものだ。
このヨロコビとは何だろな,と思いめぐらしてみると,意外や,気の遠くなるような広大な世界の中で,いつか死ぬために他の生き物を食って生きている,極めて小さな自分の確認だったりする。これが動かぬ事実だ。それ以外のことは,実はおそらく,我々の勝手な錯覚・妄想の類なのではあるまいか。
しかし時にはそれに支えられて生きてゆくのも,またニンゲンだ。けなげにも思えるし,そう悪いことばかりではない。かく言う私も,釣りをしながらこんなことを書きつつ死に向かって生きている。
愉快なり。
2007年07月13日
梅雨の真水を、飲むサカナ
本年初夏の雨不足を反省したのか,このところ天もドシドシ雨を注ぎ,九州などではいささかやりすぎ。過ぎタルは及ばざるどころか,被害が及び過ぎで困っている。
ここ境港も雨続きで釣行のタイミングを逃し気味。こんな状況の中,やはりいかにコンスタントにオカズを確保するか,が重要課題。我が家のサカナ在庫はチヌ半身とメバル3尾であったが,昨夜は松江の釣天狗兄弟の訪問があり,全て食ってしまった。もうこれは出漁せざるをえない。サカナ在庫がないこと自体,我が家では由々しきことなのだ。
ところで余談になりますが,前回「末期のサカナ」と書いた表題を「マッキノサカナ?」と読んだ人が,びっくりするくらい結構いた。「マツゴ」のサカナですね,念のため。まさか今回も「梅雨」を「バイウ」などと読む人はサスガにいないとは思うが,念のため。けして間違いとは言えないが,やはり言葉も状況によって適正表音がある,ということで・・・。
***************************
さて本題。
“○○は梅雨の水を飲んで旨くなる”という言い習わしは,全国各地,特に関東以西の沿岸で聞くことができる。○○,は当然サカナであり,カレイであったり,タコであったり,キスであったり,アナゴであったり,シャコであったり,イサキやメバルなどなど,探せばもっとあると思う。いったいどういう意味なのであろうか。単によく釣れる時期を言っているとも思えない。たしかに,ここに掲げたサカナ達は,梅雨の雨が降るごとに,なぜか旨味を増す感じがするし,脂を乗せてくる。成長もいい。
数ヶ月も前になると思うが,国営放送が「富山湾」の豊饒さの謎を科学的に追跡したドキュメンタリーを発表し,何らかの賞に輝いたと記憶している。その中で,急峻な能登半島の豊かな森林が蓄える地下水が,川や井戸のみならず沿岸の海底からユラユラと湧き出ており,周囲にカレイなどの底棲魚類が蝟集して餌をとっている光景が報じられた。いわく,この真水が魚族を涵養するということであった。
「城下(しろした)カレイ」で有名な,大分県瀬戸内海側のマコガレイも同じ理屈で説明されており,沿海に臨む日出(ひじ)町は暘谷(ようこく)城跡の前浜の海底に真水が湧き出ているがために,カレイの味が良いのだと言われている。その理由は明らかにされていないが,経験的になぜかそう言われている。
毎日のように海を見,釣りをしていると,晴天から転じて降雨し,雨が上がってその後どのように海が変化していき,サカナの所在や行動状況がどう変わるかといったこと,すなわち雨の海に対する影響が,なんとなくわかってくる。釣果にも影響が出るのでお気づきの方も多いと思う。
川釣り師であれば,水の出所に近いこともあって,もっとハッキリと認識している。釣りをしている現在地が晴天であっても,水温や濁りの変化で上流部の状態を推測し,また,熟練した釣り師は変化する状況に合わせて釣り場所と釣り方を変えてゆく。海の釣りではどうであろうか。
****************************
最近もっぱら冷蔵庫がわりに通っているメバル・スズキ・キジハタ等の安定漁場の例で言うと,ドッと雨が降ると,少し遅れて笹濁りが始まるが,透明度があまり落ちない状態がしばらく続く。いわゆる“笹濁り”だ。この過程で一時的にサカナの活性が上がるタイミングがある。それを越えると,それまで釣れていた魚は移動し,あるいは沈滞し,索餌活性は低下する。そして,雨が止んだ翌日ないし数日後に,グッと濁って透明度が著しく低下し,サカナの活性は最低となり。その後更に晴天が続くと暫時透明度が戻り,サカナも通常の状態に戻る。
具体的な魚種で言えば,スズキなどは雨が降って濁り始めた頃,その後に来る強い濁りまでの間に特に激しく餌をとる。メバルやキジハタ,アジなどは,雨が続くに従って活性が低下し,グッと濁ったあとに透明度が復活する初期の頃に荒食いする。キスやカレイでは,濁りのピークを越えて透明度がかなり回復したあたりで盛んに口を使い始める。
よく観察してみると,濁り好きと言われるスズキにせよ,濁りのピークに濁りの中で釣れてくることは稀である。濁りと濁りの合間に釣れたり,濁りが生じたり消えたりする途中のどこかに,よく食ってくるタイミングがある。サカナの索餌行動と濁りに,何らかの因果関係があるには違いない。
まず視覚的に考えてみると,フィッシュイーターが追いかけ回すシラスなどの小型魚にとって,濁りは我が身を隠してくれるベールのように機能する反面,捕食者から見れば,餌に近づきやすくなる隠れ蓑にもなるわけだ。ただ,これも濁り過ぎれば餌を見つけにくいということになり,逆効果となる。
従って捕食者であるスズキやアジなどの活は,雨が降り始めてから濁りがピークになるまでの一時期,結構早い段階で高まるのは,そういうわけではないかと推測している。スズキは視覚的にちょうどよい濁りを利用して餌を効率よく取ろうとしている。
では,小魚を追いかけ回すわけではないカレイやキスやアナゴはどうであろうか。
これは生態系の中の栄養の流れを考えてみれば説明がつく。富山湾を思い出していただきたい。山から流れ出る川水や地下水には,様々なミネラル分が溶け込んでおり,海洋生産の基礎となる植物プランクトンが育つために不可欠な窒素,リン,カリウムといった成分も多く含まれる。降雨があれば,陸上から更に多くの栄養物質が洗い流され,河川を経て海へ流入する。
雨が降り始めても,土砂が混じらない限り,海水はあくまでも薄濁り程度であるが,濁りがピークになるのは,雨が止み,次の日照が続いたときだ。
すなわちこの濁りは,植物プランクトンが雨水に流された栄養物質を吸収し,太陽エネルギーを得て増殖した結果なのである。そして,増殖した植物プランクトンを動物プランクトンが捕食していくと,次第に水は澄んでくる。また,植物プランクトンが増殖のピークを越えて自然に死滅して沈殿すれば,彼らが吸収した栄養物質は,有機物として海底に帰る。
結果として動物プランクトンに形を変えた海の濁りは,イワシの稚魚であるシラスをはじめ,様々な小生物に補食されていき,更にこれらはより大きな生物に補食されていく。たとえばアジやメバルやスズキなど。
一方,植物プランクトンが死滅して海底に沈殿してできた栄養物質は,付着性の生物や貝類やゴカイの仲間などに消費され,これらもまた,より大きな生物に補食されていく。たとえばカレイやキスやクロダイなど。
冒頭に書いた,“サカナは梅雨の水を飲んで旨くなる”,の一件は,つまるところ,こういうわけではないかと思う。当然ながら、けして雨水を飲んで旨くなるわけではない。この表現は,あくまでも経験則であり比喩である。
梅雨のまとまった雨水によって栄養が海に供給され,食物連鎖によってそれが循環的に消費され,より高次な捕食者であるサカナの餌となる。結果,サカナが肥え,味が良くなってゆく。
逆に言えば,断続的な雨と比較的強い日照の両方が交互に得られる梅雨時期こそ,このようなことが起こりうるということだ。
ただし,これも,雨が運んだ陸の栄養を循環させる「健全な食物連鎖」があってこそだ。
干潟が消え,渚に道路が通り,磯がコンクリート護岸となりつつある現代の海において,連鎖を担う生物の種類も数も減っている。梅雨の水を飲んで旨くなるサカナのその旨さは,この説に照らせば明らかに質が落ちているはずだ。昔日の自然が存在した豊かな海の,梅雨のサカナの旨さは,いかばかりであったろうか。
****************************
さて,ここ数日雨が続いた。今日は少し晴れ間も見えたが,濁り初めのチャンスを狙うには雨が続きすぎた。次の照りが来れば,グッと濁る。そのアトのひとチャンスで勝負だ。
既に述べたように,梅雨の雨による濁りはサカナにとって恵みの濁りだ。ただ,釣りによってサカナを追いかける我々としては,今見ている海の濁りが,どの段階の濁りなのかを前後の状況から見極め,食い気のあるサカナの所在を探すことが肝要となる。
濁りにチャンスあり。しかし,魚種によって濁りに対する行動や活性は異なる。狙うサカナが今の濁りに対してどこでどのようにしているのか,これを考え推測し,つかむことが安定したオカズ供給につながる。
この時期,メバルも相変わらず旨いのだが,何せこのところスズキがメキメキと味を上げている。特に40~50㎝くらいのがよい。栄養豊富な真水が育てたプランクトンを餌とする小イワシに脂が乗ってくるからであって,これを食べるスズキも当然良くなる。体高も幅も広くなり,風味のある脂が乗り,なんといっても塩焼きが最高に旨い。旨いのだから,この時期は,けして“またスズキが釣れてしまった”などとは言わない。
もちろん,当家の過去ブログ「スズキの臭味」にて述べたとおり,下処理が肝心だ。現場で活け締めして,台所でウロコと内臓を取ったら体表を塩ずりし,酒を振りかけてから水で洗い,切れ目をいくつか入れたら塩をまんべんなく薄くあてて暫く置き,焼く前にあらためて振り塩をする。表をちょっと焼いたあと,裏で7割を焼き,再び表にかえして3割を焼き上げる。表面はパリッと,中はジューシーに仕上げる。身肉もさることながら,ヒレの根元,シッポのキワなどにムッチリとした旨味を湛え,春の痩せスズキとは比較にならない別物だ。
まさに“梅雨の雨を飲むごとに”,スズキも旨くなってゆく。いいですな。
ここ境港も雨続きで釣行のタイミングを逃し気味。こんな状況の中,やはりいかにコンスタントにオカズを確保するか,が重要課題。我が家のサカナ在庫はチヌ半身とメバル3尾であったが,昨夜は松江の釣天狗兄弟の訪問があり,全て食ってしまった。もうこれは出漁せざるをえない。サカナ在庫がないこと自体,我が家では由々しきことなのだ。
ところで余談になりますが,前回「末期のサカナ」と書いた表題を「マッキノサカナ?」と読んだ人が,びっくりするくらい結構いた。「マツゴ」のサカナですね,念のため。まさか今回も「梅雨」を「バイウ」などと読む人はサスガにいないとは思うが,念のため。けして間違いとは言えないが,やはり言葉も状況によって適正表音がある,ということで・・・。
***************************
さて本題。
“○○は梅雨の水を飲んで旨くなる”という言い習わしは,全国各地,特に関東以西の沿岸で聞くことができる。○○,は当然サカナであり,カレイであったり,タコであったり,キスであったり,アナゴであったり,シャコであったり,イサキやメバルなどなど,探せばもっとあると思う。いったいどういう意味なのであろうか。単によく釣れる時期を言っているとも思えない。たしかに,ここに掲げたサカナ達は,梅雨の雨が降るごとに,なぜか旨味を増す感じがするし,脂を乗せてくる。成長もいい。
数ヶ月も前になると思うが,国営放送が「富山湾」の豊饒さの謎を科学的に追跡したドキュメンタリーを発表し,何らかの賞に輝いたと記憶している。その中で,急峻な能登半島の豊かな森林が蓄える地下水が,川や井戸のみならず沿岸の海底からユラユラと湧き出ており,周囲にカレイなどの底棲魚類が蝟集して餌をとっている光景が報じられた。いわく,この真水が魚族を涵養するということであった。
「城下(しろした)カレイ」で有名な,大分県瀬戸内海側のマコガレイも同じ理屈で説明されており,沿海に臨む日出(ひじ)町は暘谷(ようこく)城跡の前浜の海底に真水が湧き出ているがために,カレイの味が良いのだと言われている。その理由は明らかにされていないが,経験的になぜかそう言われている。
毎日のように海を見,釣りをしていると,晴天から転じて降雨し,雨が上がってその後どのように海が変化していき,サカナの所在や行動状況がどう変わるかといったこと,すなわち雨の海に対する影響が,なんとなくわかってくる。釣果にも影響が出るのでお気づきの方も多いと思う。
川釣り師であれば,水の出所に近いこともあって,もっとハッキリと認識している。釣りをしている現在地が晴天であっても,水温や濁りの変化で上流部の状態を推測し,また,熟練した釣り師は変化する状況に合わせて釣り場所と釣り方を変えてゆく。海の釣りではどうであろうか。
****************************
最近もっぱら冷蔵庫がわりに通っているメバル・スズキ・キジハタ等の安定漁場の例で言うと,ドッと雨が降ると,少し遅れて笹濁りが始まるが,透明度があまり落ちない状態がしばらく続く。いわゆる“笹濁り”だ。この過程で一時的にサカナの活性が上がるタイミングがある。それを越えると,それまで釣れていた魚は移動し,あるいは沈滞し,索餌活性は低下する。そして,雨が止んだ翌日ないし数日後に,グッと濁って透明度が著しく低下し,サカナの活性は最低となり。その後更に晴天が続くと暫時透明度が戻り,サカナも通常の状態に戻る。
具体的な魚種で言えば,スズキなどは雨が降って濁り始めた頃,その後に来る強い濁りまでの間に特に激しく餌をとる。メバルやキジハタ,アジなどは,雨が続くに従って活性が低下し,グッと濁ったあとに透明度が復活する初期の頃に荒食いする。キスやカレイでは,濁りのピークを越えて透明度がかなり回復したあたりで盛んに口を使い始める。
よく観察してみると,濁り好きと言われるスズキにせよ,濁りのピークに濁りの中で釣れてくることは稀である。濁りと濁りの合間に釣れたり,濁りが生じたり消えたりする途中のどこかに,よく食ってくるタイミングがある。サカナの索餌行動と濁りに,何らかの因果関係があるには違いない。
まず視覚的に考えてみると,フィッシュイーターが追いかけ回すシラスなどの小型魚にとって,濁りは我が身を隠してくれるベールのように機能する反面,捕食者から見れば,餌に近づきやすくなる隠れ蓑にもなるわけだ。ただ,これも濁り過ぎれば餌を見つけにくいということになり,逆効果となる。
従って捕食者であるスズキやアジなどの活は,雨が降り始めてから濁りがピークになるまでの一時期,結構早い段階で高まるのは,そういうわけではないかと推測している。スズキは視覚的にちょうどよい濁りを利用して餌を効率よく取ろうとしている。
では,小魚を追いかけ回すわけではないカレイやキスやアナゴはどうであろうか。
これは生態系の中の栄養の流れを考えてみれば説明がつく。富山湾を思い出していただきたい。山から流れ出る川水や地下水には,様々なミネラル分が溶け込んでおり,海洋生産の基礎となる植物プランクトンが育つために不可欠な窒素,リン,カリウムといった成分も多く含まれる。降雨があれば,陸上から更に多くの栄養物質が洗い流され,河川を経て海へ流入する。
雨が降り始めても,土砂が混じらない限り,海水はあくまでも薄濁り程度であるが,濁りがピークになるのは,雨が止み,次の日照が続いたときだ。
すなわちこの濁りは,植物プランクトンが雨水に流された栄養物質を吸収し,太陽エネルギーを得て増殖した結果なのである。そして,増殖した植物プランクトンを動物プランクトンが捕食していくと,次第に水は澄んでくる。また,植物プランクトンが増殖のピークを越えて自然に死滅して沈殿すれば,彼らが吸収した栄養物質は,有機物として海底に帰る。
結果として動物プランクトンに形を変えた海の濁りは,イワシの稚魚であるシラスをはじめ,様々な小生物に補食されていき,更にこれらはより大きな生物に補食されていく。たとえばアジやメバルやスズキなど。
一方,植物プランクトンが死滅して海底に沈殿してできた栄養物質は,付着性の生物や貝類やゴカイの仲間などに消費され,これらもまた,より大きな生物に補食されていく。たとえばカレイやキスやクロダイなど。
冒頭に書いた,“サカナは梅雨の水を飲んで旨くなる”,の一件は,つまるところ,こういうわけではないかと思う。当然ながら、けして雨水を飲んで旨くなるわけではない。この表現は,あくまでも経験則であり比喩である。
梅雨のまとまった雨水によって栄養が海に供給され,食物連鎖によってそれが循環的に消費され,より高次な捕食者であるサカナの餌となる。結果,サカナが肥え,味が良くなってゆく。
逆に言えば,断続的な雨と比較的強い日照の両方が交互に得られる梅雨時期こそ,このようなことが起こりうるということだ。
ただし,これも,雨が運んだ陸の栄養を循環させる「健全な食物連鎖」があってこそだ。
干潟が消え,渚に道路が通り,磯がコンクリート護岸となりつつある現代の海において,連鎖を担う生物の種類も数も減っている。梅雨の水を飲んで旨くなるサカナのその旨さは,この説に照らせば明らかに質が落ちているはずだ。昔日の自然が存在した豊かな海の,梅雨のサカナの旨さは,いかばかりであったろうか。
****************************
さて,ここ数日雨が続いた。今日は少し晴れ間も見えたが,濁り初めのチャンスを狙うには雨が続きすぎた。次の照りが来れば,グッと濁る。そのアトのひとチャンスで勝負だ。
既に述べたように,梅雨の雨による濁りはサカナにとって恵みの濁りだ。ただ,釣りによってサカナを追いかける我々としては,今見ている海の濁りが,どの段階の濁りなのかを前後の状況から見極め,食い気のあるサカナの所在を探すことが肝要となる。
濁りにチャンスあり。しかし,魚種によって濁りに対する行動や活性は異なる。狙うサカナが今の濁りに対してどこでどのようにしているのか,これを考え推測し,つかむことが安定したオカズ供給につながる。
この時期,メバルも相変わらず旨いのだが,何せこのところスズキがメキメキと味を上げている。特に40~50㎝くらいのがよい。栄養豊富な真水が育てたプランクトンを餌とする小イワシに脂が乗ってくるからであって,これを食べるスズキも当然良くなる。体高も幅も広くなり,風味のある脂が乗り,なんといっても塩焼きが最高に旨い。旨いのだから,この時期は,けして“またスズキが釣れてしまった”などとは言わない。
もちろん,当家の過去ブログ「スズキの臭味」にて述べたとおり,下処理が肝心だ。現場で活け締めして,台所でウロコと内臓を取ったら体表を塩ずりし,酒を振りかけてから水で洗い,切れ目をいくつか入れたら塩をまんべんなく薄くあてて暫く置き,焼く前にあらためて振り塩をする。表をちょっと焼いたあと,裏で7割を焼き,再び表にかえして3割を焼き上げる。表面はパリッと,中はジューシーに仕上げる。身肉もさることながら,ヒレの根元,シッポのキワなどにムッチリとした旨味を湛え,春の痩せスズキとは比較にならない別物だ。
まさに“梅雨の雨を飲むごとに”,スズキも旨くなってゆく。いいですな。