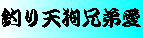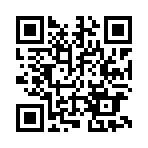2007年07月25日
アカミズ三昧
アカミズを知る人が表題を聞けば,アカミズを?三昧?そりゃケシカラン,となるでしょうな。釣る意味でも,食う意味でも。それほどに“宝石のような”高級魚だ。
そのようなサカナを存分に食う,というような状況も,長い人生たまにはあるのだなあ,というのが今回のお話。すみません。
こちら山陰で言うこところの“アカミズ”とは,標準和名を「キジハタ」,瀬戸内海の名を“アコウ”という。周年釣れなくはないが,梅雨が過ぎて暑くなる頃に活発化して旨くなる夏の魚である。内海であれ日本海であれ,その肉は極めて上品な甘みをたたえた「根魚白身界の帝王」であることに変わりはなく,瀬戸内海などでは狙ったところでなかなか釣れぬ幻(?)に近いサカナであるし,山陰では魚影が比較的濃いとはいえ,最近のワーム釣りブームで小型が数釣れることはあっても,キロ超えが数まとまって釣れることはありえないであろう。現に,一本釣りや延縄でがんばる職漁師でさえ,アカミズは混じることはあっても狙い釣りはありえん,と言うのである。
さて,私の少し年上の友人で,ベニズワイガニを“かご”で獲る,いわゆる“カニカゴ漁業”の船主を境港でやっているヒトがいる。このヒトは,島根半島笠浦の出であり,幼少のころからさまざまなサカナを追いかけて成長し,長じて漁労長となり,今では100余トンのカニカゴ船「第78漁徳丸」の船主なのであるが,このヒトは,根っからサカナを獲るのが好きな“漁り人”(←読めるかな?2つ読み方アリ)だ。
ひとくちに漁村の出で漁師をしているといっても,漁師誰もがどっぷりサカナ好きかといえば,そうとは限らず,一般的にはむしろその逆だ。オカに上がればパチンコばかりしている者もいれば,ネーちゃんのいるところへ出かけてセッセと金を使う者もおり,そもそも趣味の少ない漁師連中の中にあって,本業以外までサカナを追いかけるこのヒトのようなケースは,意外と少ない。
これは,料理人が,仕事を離れれば普段はあまり自分で作っては食わない,などと言うのと似ているかもしれないが,そんな料理人は意外と本業もたいしたことないものだ。料理人は人生を貫いて料理を作り自らも食い続けてこそ進歩大成するのであって,漁師もまた然り。本当に上手な漁師は,日常もサカナを追う感覚を忘れない。漁村に育ったからといって漁師の血が流れているわけではない。本当にサカナを狩るセンスが体に染みついている者を,結果として「漁師」と呼ぶのだ。そういう意味で,今は漁師も料理人もピンキリだ。
友人「長崎さん」は,そのような中でも稀な,本当の漁師のうちの一人だと思う。かつてカニカゴ船の漁労長をしていた頃,自身の出所である笠浦に小船を持ち,ベニズワイガニの休漁期7~8月の2ヶ月間の釣りだけで120万円を毎年コンスタントに稼いだツワモノだ。しかも,アカミズだけで。水揚げのたびに周りの漁師がビックリ仰天して真似しようとするが,ムリ,であったという。そりゃそうだ。一本釣りだけでそれだけの水揚げをできるのであれば,年収約1千万。食っていけるどころか,セガレを大学にやっても,なお家が建つ。
今のところ長崎さんは船主業が主であって,魚釣りで稼ごうとは思っていない。カニカゴ漁船の経営のほか,境港の商店街でカニも売っている。が,やはりサカナ獲りから離れることができず,昨年,50馬力の船外機船を中古で買い,しばらくやめていたアカミズ釣りを再開した。そして今年,「ワシのウデを見せてあげーけん,たまには行かんかや」ということで,誘われ行ってきたのである。
長崎さんの漁場は笠浦沖から西は多古鼻,東は片句沖までの狭い範囲だ。行動範囲が狭くても,その中を徹底的に深く探求しているが故に,それで十分獲れる。従って遠出の必要がない。これは,私の漁場開拓にも共通するところがある。より経費がかからない範囲でスキマを釣る。合理性と経済性を追求すると,おのずからこうなる。
共に出漁する一週間前,長崎さんは今年最初の試験操業の成果を見せてくれた。夕方の1時間半でアカミズの2キロ級3尾,800g前後が4尾,ボッカ(カサゴ)の500g前後が5~6尾。一人での釣果だ。なかなかヤル。
前夜,私は,期せずして,まだ見ぬヨロコビに目が冴えた。その期待は,見せられた釣果に対してではなく,そのような釣果を確実に獲ってみせる長崎さんと共に釣りをできることに対して。
最後にこのような思いをしたのはいつだったろうか。漁師稼業を去って十数年,学生のころ,初めて漁船に乗って働いたときの前夜を思い出した。
いくつになっても胸膨らむ想いを乗せられる対象があるのは,いいものだ。
それを,どれだけ,いつまで,持ち続けられるか。それが人生の“輝き”というものなのかもしれない。
****************************
さて当日,出港して漁場に着いたのが朝6時。周りには既にポツポツと釣り漁船やプレジャー船が見えるが,皆,錨をおろして釣っている。各船とも竿はほとんど曲がっていない様子。さてさて。
長崎さんの釣りは,位置測定のためのGPSプロッターをほとんど使わない。全て2点ないし3点の陸の景色を記憶して船位を決める“山立て”による,昔ながらの方法だ。そして漁場に着くと,錨は打たず,エンジンのスロットルと舵を握りながら,ひたすら魚探とニラメッコとなる。まず海底の微妙な形状がカギなのだ。アカミズが潜む海底地形をピンポイントで探す。
そうして探し当てたポイント(=“穴”あるいは“山”)をいくつ持っているかが釣果を左右するのであって,長崎さんはそのような自分の穴を100ほども持っているという。
餌は前日に釣っておいた小アジ。2本針,錘30号の胴突き仕掛けだ。
長崎さんは3.2mの固い振り出し投げ竿に,PEライン5号を巻いた大きな投げ釣り用スピニングリール。これで,合わせと同時にグイグイとアカミズをスバヤク根から離し,ゴリゴリ揚げてしまう。数を獲るための合理的な道具立てだ。
片や私は10~50号まで背負える全調子の細手のチューブラ2.1mに,PEライン2号を巻いたバス釣り用の小型両軸受けリール。波の動揺を消し,食わせを重視。かつ錘が根に触れるのを感知して微調整できる繊細な道具立てだ。
これまで陸からのワーム釣りで釣れてくるアカミズの35cmまではメバル竿にフロロ4lbで十分獲ってきたので,強度的には不安はない。要は竿の弾力を活かしきれるかどうかにかかっている。
ちなみに私が主に使っているメバル竿は「根魚権蔵チタン8.1ft」であり,チューブラ全調子でかなりペナペナしているが,イザというときの“腰”,にかなりの信頼を置いている。「全調子では根に潜られませんか」と言う人がいるし,かつては私もそうではないかと思っていたが,それは掛けてから次の瞬間のリールの巻き方と竿の操作を合わせることでカバーできる。あとは,そこそこのレベルの竿であれば,竿がサカナを浮かしてくれる。また,そうしてくれない竿ではダメなのだ。この竿とレブロスの2500番の組み合わせで,スズキ70㎝程度なら楽に獲れる。
****************************
出港まもなく小手調べで始めた近場から,いきなりアカミズとカサゴが連発し,その後,場所を変えるたびに食うこと食うこと。底ではアカミズやらカサゴやらが,口をあけて待っているのではないか,と思うほど安易に釣れる。アカミズは全て1キロ前後,カサゴは20~30cmといったところ。潮が悪くなるとオコゼやマトウダイやらが顔を出したが,場所をちょっと変わればまたアカミズだ。ひとわたり釣ったところで,長崎船頭いわく,“ウエちゃん,これの親玉がおるとこに連れてくけん”といって少し走り,そこでは予定通り2キロ級が2尾出た。
結局,餌がなくなる昼前までに,全部で2キロ大を2尾に1キロ前後を18尾,ホンカナ(マハタ)が2尾,カサゴは多数。これにはたまげた。世間並みで言えば大漁も大漁,水揚げ金額にして活魚であれば10万円近い。筋金入りの漁師の実力とはこういうものかと思い知らされた。彼の,サカナを追跡する姿勢とそこから出る結果には,驚嘆を通り越し,ただ感動あるのみ。
ただし,このような漁師は,私が知る限り,島根から石川県まで7府県を歩いてみても聞いたことがない。おそらく山陰ナンバー1だと思う。しかもこれが今は本業ではないというのだから,これまた・・・。その上,これだけ釣っても「今日は潮が悪かったしサカナがこまい。またこんど釣らせるけん」と渋い顔なのだから恐れ入る。大きいアカミズとは3キロ越えを言うのだそうだ。3キロ数本に2キロ級が10ばかりも混じればまずまずだけど,なんてことを平気で言う。
****************************
この日の釣りを振り返ってみてアカミズについて思うことは,けして釣ることがそれほどおもしろいサカナではない,ということだ。実際に潜って観察するとわかることだが,彼らは自分の穴を中心に縄張りをもっているので,潮が動いていてその範囲内に餌ないしルアーを落とすことができればほぼ確実に食う。その穴から釣ってしまっても,しばらくすると次のアカミズが入る。先述した“持ち穴の数が勝負どころ”というのは,ここだ。
従って船のアカミズ釣りの場合,そのピンポイントに船を持っていく船頭の技術が9割を占め,釣り手の技術は残り1割だ。根掛かりをうまく避けつつ,食わせてから穴に入らぬよう最初にうまく引き剥がすことができれば,あとはゴンゴンと重く竿を叩くのみ。最後まで抵抗することは少なく,水面に釣り上がってしまえばほとんど暴れない。更に船上に横たわればおとなしいものだ。 “根”に依存して生活しているだけに,とにかく“根”から引き離されると意外なまでに情けない。アカミズに限らず,ハタ類は全てそうだ。
そういうわけだから,竿は堅く強い必要はない。むしろ柔軟で食い込みが良く,しかし掛かったあと根に引きずり込むのを阻止できる粘り腰がある竿がよいとみた。そういう意味では今回の道具立ては的を得ていたと言ってよいであろう。軟・硬両方試してみたが,先調子や堅い竿では波の動揺を消すことができずに警戒心を与え,従って,アタリ始めてから離してしまうことも多い。ここに差が出る。また,ハリスの太さは思いのほか影響があるようだ。これはアカミズに対してというより,餌の動きを左右するという意味で。5号と6号のフロロを使ってみたが,わずか1号差にもかかわらず,アタリの回数では断然5号に分があった。
引きの強さという点では,今回,水面付近までドラグを引き出すような引き方をしたのは2キロ級だけであり,このときは上針に2キロ,下針に1キロのアカミズが掛かっていた。結局,釣り自体の味わいとしては,小さくても日ごろ追っかけているメバルの方が断然おもしろい。ただ,なんといってもアカミズの食味には捨てがたいものがある。それどころか,山陰のサカナの中では,ノドクロ(アカムツ)を超える高級魚である。これは味の真価を追求しないわけにはいくまい。
沖上がり後,長崎さんが,アカミズは刺身以外にどんな食い方があるだろうか,と言うので,それでは今夜ウチにおいでませとお誘いし,いくつか作ってみた。
なにせ,アカミズもカサゴも売るほどある。急遽,松江から当ブログの大家さんである釣り天狗兄弟とノリちゃんも呼び寄せて,総勢7名の“アカミズの宴”と相成った。
さてその内容をご紹介すると・・・,
一, 造り
二, 昆布締め
三, 焼きちり
四, カルパッチョ
五, 塩焼き(カサゴ)
六, 野菜蒸し
七, アカミズ飯
今回は,アカミズの「可能性」というよりは「真価」を探ることが目的であるため,いずれの料理もほとんど手を加えず,加えるとしても日本,あるいは外国の古来よりある調理法を基本とし,あくまでも素材の味を尊重するかたちにとどめた。
以下,詳細を書いてみよう。
一,【アカミズの造り】
アカミズは,白身の肉に独特の甘味と,淡泊なようで舌にうっすらと良くなじむ脂を乗せている。その上なんといっても,肉の腰が秀逸である。その点,1~2㎏の太めのものが特によい。
当然ながら,釣り上げたものをイケスで餌吐きさせ,しかる後に即殺・放血,すなわち“活け締め”とし,濡れ新聞にくるんで氷をあまり打たずにおく。こうしておけば,身が白く濁らず,刺身にしても美しい半透明に保たれる。
洗いにするのであれば,硬直が起こる前に薄くそぎ切りして氷水にさらせばよい(過去ログ「スズキの臭味」参照)。
タイやヒラメなど多くの上級白身魚で共通していることだが,アカミズも刺身として旨いタイミングは2度ある。
一回目は硬直が起こりかけのときで,上手に締められた身であれば,刺身にひくときヒリヒリっと心地よい微振動が刃先に伝わる。三枚におろし,皮をひいて背・腹のサクに分けたら,体の表側を下にして,尾のほうからそぎ切っていく。薄造りや洗いのときより若干厚めがよい。目安としては,身を包丁で削ぐとき,かすかに刀身が透けて見える程度。厚さにして4~5㎜。1枚ごとにナナメに寝かせた引き包丁で切っていくが,毎回最後の一皮分を包丁を立ててクッと押し切ってやると,並べたときにカドがきれいに立って凛々しく映える。噛み下すと,身が口の中で踊り,やがて切れのいい甘味と脂が伝わってくる。
二回目は,硬直が続いて終わりかけの頃で,肉は若干軟らかくなっているが,旨味は断然増している。じわりと甘く,しっとりと歯に絡む。これは,活け締めした1㎏前後であれば2日,2㎏前後であれば3日,きれいに下処理したアカミズをペーパーでくるみ,ラップをして冷蔵庫で寝かせる。これを造るときは,一回目の場合より若干包丁を立てた少し小さいそぎ切りとし,厚さは7~8㎜程度と少し厚め。“ポッテリと”切りつける。
書いてしまえばわずかな手法の差ではあるが,これが,味のバランスに出るのである。割烹の“割”すなわち包丁技術は,このようなところにその意味を見出すことができる。お試しあれ。
合わせるのはワサビ,そして,できれば甘くない上質の醤油がよい。たまり醤油や刺身醤油はアカミズの甘味を殺す。
二,【アカミズの昆布締め】
素の味を刺身で味わったら,少し手を加えてみる。
白身で定番の「昆布締め」であるが,これについては,“昆布締めの味に2極あり”,と申し上げたい。漬け物に例えるならば“浅漬け”と“古漬け”だ。2極というのは両の極端であって,実はその中間は味覚上中途半端でツマラナイのである。諸説あるにせよ,私はこう思う。さてその内容とは,,,
●浅漬け
①サクにとったアカミズは,5㎜程度のそぎ切りにしておく。
②できれば利尻昆布,なければ他の昆布を酢にくぐらせてから拭きとり,柔らかくしておく。酢で拭くことによって,身を締めると同時に,昆布のヌメリを除くことができる
③昆布の上に,アカミズの刺身を,半分ずつ重なるようウロコ状に並べていく。
④びっしり並べ終わったら,手の平を水で湿らし,そこに薄く粗塩をなすりつけ,並べた刺身の表面をまんべんなく軽く叩いてやる。こうすることによって,均一かつほどよい塩分が片面のみに回り,ちょうどよく身が締まる。塩の当て方と加減については,職人であれば振り塩を当てるところであろうが,我々ノンプロはこのやり方のほうがうまくいく。
⑤塩を当て終わった上から,もう一枚,同様に柔らかくしておいた昆布をかぶせ,これをラップで包み,砥石などの重しを乗せて冷蔵庫で15分。
⑥上側の昆布をはずし,このまま皿に乗せればよい。
この程度の浅漬けだと,昆布の風味と旨味がうっすらと身に移った加減となり,アカミズの旨味の邪魔をせずに盛り立ててくれる。これは,醤油は使わずワサビだけで食べるのがよい。
ところで,寝かせる時間をこれ以上かけると,こんどは“昆布風味”が“昆布臭さ”に変わり,昆布の“旨味”が“嫌み”となってアカミズの味を殺してしまう。
そう言う点では,ヒラメにせよタイにせよ,世の多くの昆布締めは寝かせ過ぎであると思う。
そこで,どうせ昆布味になるのなら徹底的にやってしまうと,これはこれで別物として味わえるからオモシロイ。これが古漬けだ。
●古漬け
①浅漬けの作り方の①から⑤まで同様。
②押しをかけて寝かせる時間を丸一日以上とする。そうすると,身はベッコウ色に透き通ってくる。これを昆布からはがし,皿に盛る。
こうすると,こんどは味の主役が魚から昆布へと変換する。これは,魚肉を媒体として昆布の旨味を味わう昆布締め,というわけだ。これは,ワサビよりも和辛子が合う。これも醤油は用いない。ビールでやるなら,ゴマ油に先っちょを浸して食うのもオツだ。
ただし,アカミズで古漬けをやるのは,もったいない。余れば別の話だが。
せいぜいイシガレイとか,スズキ,イシモチなどの,ワンランク下の白身でツマミ作りと割り切ってやるのが妥当と思う。
三,【アカミズの焼きちり】
「焼きちり」とはなんぞや?というとき,すぐに思い出す「ちり鍋」。これは身を熱い鍋に投じたときにチリッとそっくりかえって弾力が増す様を言ったものだ。
従って,焼きちりとは,生の魚肉を焼いてチリッとさせたものを指す。チリッというからには,さっと火を通し中身は生であることが前提。そして,身の固い,鮮度のよい白身の魚でなければチリッとはならない。それでは,カツオのタタキやチヌおよびグレなどの「焼き切り」はどうなのかといえば,これはチリッではないから,焼きちりにはあたらない,ということになる。
この料理は,鮮度のよいアカミズやその他のハタ類でやると最高だ。鮮度のよいマゴチやタイでもよろしい。では作り方を。
①まず氷水を用意しておく。
②サクに切って皮をひかないアカミズを,幅1.5㎝,長さ3センチ程度にずんぐり切り分け,皮を上にして,わずかに間隔をあけて耐熱皿もしくは焼き網の上に並べておく。
③簡易バーナーで皮側から火を当てるが,アカミズの皮は固いので,火の先端から少し話した距離で,皮目の脂がジリッと音を立てるまで炙ってやる。バーナーがないときは,切り身を串に刺して,皮側からガスレンジの強火で炙る。焼き加減は同様。
④すぐさま氷水に放ちあら熱をとる。
⑤ザルに上げ,フキンにくるんで軽く叩くように水気をとり,盛りつけて冷蔵庫で冷やす。
これは,洗いと並ぶ,まさに夏の一品。カイワレ大根や千切りキュウリなどを合わせ,ポン酢でやる。同じく表面だけに熱を通す「湯引き」があり,こちらも涼しげではあるが,焼きちりは,皮目の香ばしさと弾力の強い白身の合わせ技で,カラリと旨い。
四,【アカミズのカルパッチョ】
既に当家過去ログ「カルパッチョについて,ひとこと」で,本来のカルパッチョがどのようなものであるかを述べた。あらためてポイントを書いておく。
①三枚におろしサクにとったアカミズは,皮をひき,たっぷりの粗塩をまぶして皿に置く
②水分が滲出してきたら,手早く流水で塩を洗い流し,フキンで水気をよくとっておく。
③皿に,水でさらしたスライスタマネギを敷き,その上に薄くそぎ切りにした切り身を重ねずにまんべんなく乗せていく。魚の厚さは,3~4㎜程度と薄くする。
④黒コショウを挽き,身の上にまんべんなく振ったあと,ライムもしくはレモンの汁を細くまんべんなくたらしかける。
⑤ここでは彩りと夏のほろ苦みを補うために,極薄く輪切りにスライスして水でさらした緑のピーマンを散らした。
⑥最後にバージンオリーブ油を細く全体にかけまわし,これを冷蔵庫で冷やす。
過去ログでも申し上げたが,とにかく塩でちゃんと締めること,そして,調味料をかける順番を間違わないことが肝要。少なくともカルパッチョは,刺身にドレッシングみたいなものをかけただけの料理ではない。先人の知恵が詰まった郷土料理である。
五,【カサゴの塩焼き】
アカミズではないが,釣りボッカ(カサゴ)がある以上,これだけは欠かせない料理だと,今は思っている。
“今は”,というのは,長崎の出である私は,ついこのあいだまで,アラカブ(カサゴ)=味噌汁,という構図を完全に信奉しており,いつでもどこでも常にそれに忠実であった。煮付け,唐揚げなどはカサゴの味として格下であった。
なにせ,長崎では,カサゴの尾頭付き味噌汁専用の広口大型の塗り椀が存在するくらいだ。祝いだろうが法事だろうが,これでアラカブの味噌汁が出てくるのであり,ちゃんとしたアラカブ汁を出さないと,“あン家の法事のアラカブ汁はウマかったとバッテン,今日ンとはマズかのう”,とかなんとか,陰口をささやかれるのである。
が,昨年,当家ブログ大家の釣り天狗兄弟にカサゴの塩焼きが旨いと聞いて,試しにやってみたところ,これにはビックリ仰天しましたね!
焼くときの匂いといい,香ばしく新鮮な身と皮のはじけた旨さといい,ヒレ際や頭の肉の各部位の歯ごたえ・甘味といい,野趣に富んだ味わいに,引きずり込まれる思いがしたものだ。今まで吸ってきたカサゴの味噌汁も当然旨かったのであるが,これまで食ったカサゴの数の半分くらいは,過去に戻って塩焼きで食いたかったと,少しだけ思った。
それほどいい。
総合点の高いカサゴの塩焼きであるが,その詳細を述べると,わずか20㎝やそこらの小柄な体の中に,次に掲げる様々な美味を秘めている。
①背肉
②腹肉
③尾肉
④各ヒレ際の肉
⑤こんがり焼けた各ヒレ
これらを全て食べ尽くしナメ尽くしたら,頭を持って腹側を上にして,
⑥背骨に沿ってついているむっちりした浮き袋
⑦背骨と頭をつなぐ,首を動かす細長い筋肉2本(これがカサゴの身の中で最も旨い)
⑧目の裏側にある動眼筋2片(これがカサゴの身の中で最も歯ごたえがよい)
⑨目
⑩脳みそ(背骨をはずした頭から吸い出す)
⑪ほお肉およびその周辺
⑫唇
⑬舌
ね,スゴイでしょう?それぞれのパーツが全部味が違う。
更に,これらを全て味わい尽くしたら,全ての残骸を椀に入れて熱湯を注ぎ,アラを箸で突きほぐし、しばし待つ。これに薄口醤油数滴をたらしてズーッと吸って,完了,となるのである。
以前ご紹介したノドグロの塩焼きとは別の意味で,こんな塩焼き,ほかにありませんよ。
①カサゴは大きすぎるとやはり身がゆるくなるので,20㎝前後がよい。体側に肩から尻ビレにかけて背骨に到達する包丁を入れ,あらかじめ薄く塩をまぶして暫く置く。このときに,のど元から腹の中までも塩を当てることが大切。要は,全体に,塩をまわしてやることが肝要。
②目が塩分でうっすらと白くなったところであらためて各ヒレに化粧塩を施し,身の両面にも軽く塩を振る。このときの塩の振り方は,湿った手に付着した塩を,指をパッパッと開いて飛び散る程度,これでよい。
③まず,背を向こうに頭は左,つまり表側をちょっと焼く。そうすると,釣った当日のカサゴであれば,グリルの中で上方に反り返りはじめるので,すかさずひっくり返す。そして7割焼き,表に戻して3割を焼き上げる。
コツはこんなところ。反り返るのをそのままにしておくと,ひっくり返せなくなるのです。これは高鮮度の証であるわけですが,ちょっと困る。
六,【アカミズの野菜蒸し】
香港および上海あたりで,何が高級海鮮料理かといえば,アカミズを含むハタ類の蒸しもの,これに尽きます。清蒸(チンジャオ)という料理で,白髪ネギや香草と共に,塩と老酒少々で蒸し上げる。これにはイセエビやワタリガニ,その他の魚をはるかに凌ぐ値段がついている。イケスに泳がせてあるアカミズを指名(?)すると,彼は料理人の手によって速やかに拉致され,下処理され,速やかに蒸されて出てくる。万事が速やか,なのである。
過去ログで書いたかもしれないが,本格の中華料理店には,この蒸し魚専門の職人がおり,最上級の給料が与えられているという。魚のサイズ,脂の乗り,時期,肉質などをグッとにらんで見極め,1分と違わずピタリと最適な蒸し加減に仕上げる。横浜あたりには,いるのですね,こういう4000年の歴史を感じさせるそのような料理人が。
では我々家庭人がやる場合,いくら活け締めしたところで活魚にはかなうべくもない。それならいっそ,たっぷりの野菜の力を借りて,そしてアカミズの旨味も野菜に吸ってもらって,家庭的で豊かな一品に仕上げようというわけだ。
ところで,大きなサカナを蒸すときに,ウチには蒸し器もないし,大きな皿もない,と諦めていないだろうか。いい方法がありますヨ。
番外【蒸し器がなくても蒸す方法】
①アルミホイル4枚を同大に切り,重ねる。
②四辺のうち一辺を2㎝ほど折る。折った部分を更に半分に折る,そして更に半分に。これで,重ね折りした部分は5㎜ほどになっているはず。
③ここでアルミホイルを左右2枚ずつに広げ,真ん中の折った部分をキッチリ押して平らにすると,アルミホイル2枚重ねの大きなシートができあがる。
④この両端を絞って,舟状に整形する。これにサカナなどを入れ,大きなフタつきフライパンに半分ほど水を沸騰させ,舟をそこに浮かせてフタをすれば,立派に蒸すことができる。
⑤大皿に乗せかえる場合は、ホイルのまま乗せ、ホイルの中央付近に切れ目を入れ、そこから両端を引っぱるように破ってホイルだけ抜けば(コンビニの握り飯で、ビニールをぎゅっと引くと、海苔とご飯が一緒になる、あの感じ)、サカナは崩れずそのままの姿で大皿に残る、という次第。
さて,蒸す道具の問題もクリアしたところで,野菜蒸しの作り方だ。
①野菜は,ニンジンは千切り,細ネギ・エノキは5㎝,シメジはばらし,これらをボウルの中で,少量の塩を振って混ぜておく。
②アカミズはウロコをとり,頭つきのままエラ・腹を除き,全体の水気をよく拭いておく。
③アカミズの体側に両面とも3カ所,背骨に到達する程度の包丁を入れ,全体に塩をまぶして30分置く。若干強めに塩をしてよい。
④アルミホイルで作った舟に野菜を少し敷き,口や腹に野菜を詰め入れたアカミズを寝かせ,その上に更に野菜をかぶせる。最後に少量のサラダ油をアカミズにかけてやる。
⑤フライパンに3㎝ほどの水を沸かし,舟を入れフタをする。そのまま強火で15分程度蒸し上げる。フライパンの水が少なくなくなったら足せばよい。包丁目の間から骨が見えたら完成。
アカミズに入れる包丁目は,火の通りをよくすることと,食べるときに肉をとりわけやすくすることが目的だ。
この料理のポイントは,酒を使わないこと,そして,野菜とサカナの塩加減を,出来上がりを想像して調節することにある。
この料理も,おわかりと思うが,和・洋・中,自在である。過去ログ「塩煮の世界」を参考とされたし。
七,【アカミズ飯】
一般的に知られているサカナの飯といえば、マダイを使った「タイ飯」だが,これには2タイプある。
瀬戸内海中西部を中心とした漁師料理であるタイ飯は,海水で研いだ米を硬めに水加減し,下処理したタイを丸ごと入れて炊き込んだもの。タイをあらかじめ焼いてから入れる場合もあるが,これは漁師料理を陸上でやるようになってからのこと。炊き上がったら,骨を取り除いて身だけを飯に混ぜ込む。マダイのほかに,クロダイやキダイでやる地方もある。
もうひとつは愛媛県の豊後水道に面した宇和島周辺におけるタイ飯で,これは刺身状に切ったサカナを薬味と共に醤油ベースの下地に漬けた,ヅケの一種である。これを飯に乗せて食う。豊後水道エリアの各県にはサカナのヅケでを食う文化が広がっており,たとえば大分県佐賀関では,醤油とミリンを合わせて刻みネギとすりゴマ,唐辛子を混ぜた下地にサバの刺身を漬けたものを「リュウキュウ」というし,大分と愛媛の中間にある日振島では,アジなどの青魚を薬味と共にヅケにしてご飯の上に乗せ,卵の黄身を落としたものを「日向(ひゅうが)飯」と呼んでいる。これは宇和島水軍の食習慣の名残だ。
更に宇和島中南部に下ると,そこで「タイ飯」となる。原理は同じで,要は,「その土地でなじみの深いサカナを刺身に切って,薬味と共に醤油地に漬け込み,それで飯を食う習慣」が,豊後水道には根強いということだ。
ついでながら,同じ愛媛県内でも,豊後水道側ではヅケ飯のことだが,瀬戸内海に面した今治あたりでタイ飯といえば炊き込みになる。このへんの分水嶺がどこにあるかは定かでないが,やはり食習慣というものは,その風土・生活から発生し,伝播して形成される。
ともあれ,ここでは宇和島流の「アカミズ飯」だ。しかし言葉の響きがマズそうですな。瀬戸内海の呼称で「アコウ飯」のほうが,何やらうまそうに聞こえるが,瀬戸内海に斯様な食い方はない。もっとも,高級なアカミズをヅケで食うなんて人は,おそらくおらんでしょう。
名称はどうでもいいが,とにかく旨い。当然,タイやヒラメのヅケにはない白身の旨さがある。アカミズが手に入らなければ,ほかのハタ類でもやる価値アリだ。では作り方を。
①アカミズは皮をひき、サクにとり,5㎜程度のそぎ切りにしておく。
②ボウルに入れた醤油に徐々にミリンを加えていき,塩辛さの“カド”がとれる瞬間で加えるのをやめる。甘すぎれば身の味を損なうし、足りなければ塩がきつい。
③下地に大葉を刻み入れ,そこにすりゴマ(白)を,ドロッとするくらい多めに加えて混ぜておく。
④この中にアカミズを投入してざっくり和え,暫くののちに,これを熱い白飯の上に敷き詰める。
これだけです。
アカミズ自体が大変味の深いサカナなので,“リュウキュウ”のようなネギも,“日向飯”のような卵も加えない。下地はシンプルでよい。薬味は大葉だけ。欠かせないのはすりゴマ。
ヅケが残ったら,翌朝,ワサビを添えて茶漬けにするのがいい。一日の始まりとしては気持ちがよいものだ。
****************************
さて,この日に作らなかった料理で気になるものがある。
お集まりの皆様が,既に満腹してしまったから作れなかったわけで,残った骨・頭,すなわちアラを使った料理を少し書いておく。
【塩煮,およびマース煮】
いずれも適する。調理方法については過去ログ「塩煮の世界」および「もうひとつの塩煮」を参照されたし。これはアラのみならず,一尾づけでやっても当然おいしい。
【煮付け】
一尾をまるまる煮付けてしまうと,意外と月並みな味だ。残りアラでやるのはよい。
鍋に酒と水を半々で割って沸騰させ,ミリン少々を加えて際沸騰したらアラを投入。火が通ったら,3回くらいに分けて醤油を加えていく。
【酒蒸し】
これも残りアラでやるのがよい。頭は半割し,背骨は適当に切り分け,塩をして暫く置く。鍋に酒を2㎝くらい注いで強火にかけ,沸騰し始めたらアラを投入してフタをする。煮立つ泡がアラをかぶるくらいに火加減し,10分でできあがる。
これは熱いうちにポン酢をかけまわし、刻みネギで食うのがよい。
【焼き】
頭を半割して塩をあて,しばらく置いてから焼く。
頭まわりの肉は,特に弾力に富み,かつ歯切れ良く,さっぱりとした味だ。
今回はカサゴを焼いたが,この代わりに出してもよかろう。
****************************
やはりアカミズは,体の隅々まで,真の実力者だと思う。値段が高いだけのことはある。実は,内臓や皮まで,捨てるところがない。これらはアラと共に煮付けにするのがいい。けして捨ててはいけない。捨てるのは,結局ウロコとエラだけだ。
このたびのアカミズの宴は,延々5時間に及んだ。
使用したアカミズは2キロ級1尾,1キロ級5尾,800グラム級2尾。あとはカサゴを7尾。
残りのアカミズは皆で分けて持ち帰った。
山陰の海では,こんなことも,たまには,ある。
今年の夏も暑くなりそうだ。うっとうしいスズキの野郎はとりあえず置いといて,沖でアカミズとじっくりつき合うのもよい。
そのようなサカナを存分に食う,というような状況も,長い人生たまにはあるのだなあ,というのが今回のお話。すみません。
こちら山陰で言うこところの“アカミズ”とは,標準和名を「キジハタ」,瀬戸内海の名を“アコウ”という。周年釣れなくはないが,梅雨が過ぎて暑くなる頃に活発化して旨くなる夏の魚である。内海であれ日本海であれ,その肉は極めて上品な甘みをたたえた「根魚白身界の帝王」であることに変わりはなく,瀬戸内海などでは狙ったところでなかなか釣れぬ幻(?)に近いサカナであるし,山陰では魚影が比較的濃いとはいえ,最近のワーム釣りブームで小型が数釣れることはあっても,キロ超えが数まとまって釣れることはありえないであろう。現に,一本釣りや延縄でがんばる職漁師でさえ,アカミズは混じることはあっても狙い釣りはありえん,と言うのである。
さて,私の少し年上の友人で,ベニズワイガニを“かご”で獲る,いわゆる“カニカゴ漁業”の船主を境港でやっているヒトがいる。このヒトは,島根半島笠浦の出であり,幼少のころからさまざまなサカナを追いかけて成長し,長じて漁労長となり,今では100余トンのカニカゴ船「第78漁徳丸」の船主なのであるが,このヒトは,根っからサカナを獲るのが好きな“漁り人”(←読めるかな?2つ読み方アリ)だ。
ひとくちに漁村の出で漁師をしているといっても,漁師誰もがどっぷりサカナ好きかといえば,そうとは限らず,一般的にはむしろその逆だ。オカに上がればパチンコばかりしている者もいれば,ネーちゃんのいるところへ出かけてセッセと金を使う者もおり,そもそも趣味の少ない漁師連中の中にあって,本業以外までサカナを追いかけるこのヒトのようなケースは,意外と少ない。
これは,料理人が,仕事を離れれば普段はあまり自分で作っては食わない,などと言うのと似ているかもしれないが,そんな料理人は意外と本業もたいしたことないものだ。料理人は人生を貫いて料理を作り自らも食い続けてこそ進歩大成するのであって,漁師もまた然り。本当に上手な漁師は,日常もサカナを追う感覚を忘れない。漁村に育ったからといって漁師の血が流れているわけではない。本当にサカナを狩るセンスが体に染みついている者を,結果として「漁師」と呼ぶのだ。そういう意味で,今は漁師も料理人もピンキリだ。
友人「長崎さん」は,そのような中でも稀な,本当の漁師のうちの一人だと思う。かつてカニカゴ船の漁労長をしていた頃,自身の出所である笠浦に小船を持ち,ベニズワイガニの休漁期7~8月の2ヶ月間の釣りだけで120万円を毎年コンスタントに稼いだツワモノだ。しかも,アカミズだけで。水揚げのたびに周りの漁師がビックリ仰天して真似しようとするが,ムリ,であったという。そりゃそうだ。一本釣りだけでそれだけの水揚げをできるのであれば,年収約1千万。食っていけるどころか,セガレを大学にやっても,なお家が建つ。
今のところ長崎さんは船主業が主であって,魚釣りで稼ごうとは思っていない。カニカゴ漁船の経営のほか,境港の商店街でカニも売っている。が,やはりサカナ獲りから離れることができず,昨年,50馬力の船外機船を中古で買い,しばらくやめていたアカミズ釣りを再開した。そして今年,「ワシのウデを見せてあげーけん,たまには行かんかや」ということで,誘われ行ってきたのである。
長崎さんの漁場は笠浦沖から西は多古鼻,東は片句沖までの狭い範囲だ。行動範囲が狭くても,その中を徹底的に深く探求しているが故に,それで十分獲れる。従って遠出の必要がない。これは,私の漁場開拓にも共通するところがある。より経費がかからない範囲でスキマを釣る。合理性と経済性を追求すると,おのずからこうなる。
共に出漁する一週間前,長崎さんは今年最初の試験操業の成果を見せてくれた。夕方の1時間半でアカミズの2キロ級3尾,800g前後が4尾,ボッカ(カサゴ)の500g前後が5~6尾。一人での釣果だ。なかなかヤル。
前夜,私は,期せずして,まだ見ぬヨロコビに目が冴えた。その期待は,見せられた釣果に対してではなく,そのような釣果を確実に獲ってみせる長崎さんと共に釣りをできることに対して。
最後にこのような思いをしたのはいつだったろうか。漁師稼業を去って十数年,学生のころ,初めて漁船に乗って働いたときの前夜を思い出した。
いくつになっても胸膨らむ想いを乗せられる対象があるのは,いいものだ。
それを,どれだけ,いつまで,持ち続けられるか。それが人生の“輝き”というものなのかもしれない。
****************************
さて当日,出港して漁場に着いたのが朝6時。周りには既にポツポツと釣り漁船やプレジャー船が見えるが,皆,錨をおろして釣っている。各船とも竿はほとんど曲がっていない様子。さてさて。
長崎さんの釣りは,位置測定のためのGPSプロッターをほとんど使わない。全て2点ないし3点の陸の景色を記憶して船位を決める“山立て”による,昔ながらの方法だ。そして漁場に着くと,錨は打たず,エンジンのスロットルと舵を握りながら,ひたすら魚探とニラメッコとなる。まず海底の微妙な形状がカギなのだ。アカミズが潜む海底地形をピンポイントで探す。
そうして探し当てたポイント(=“穴”あるいは“山”)をいくつ持っているかが釣果を左右するのであって,長崎さんはそのような自分の穴を100ほども持っているという。
餌は前日に釣っておいた小アジ。2本針,錘30号の胴突き仕掛けだ。
長崎さんは3.2mの固い振り出し投げ竿に,PEライン5号を巻いた大きな投げ釣り用スピニングリール。これで,合わせと同時にグイグイとアカミズをスバヤク根から離し,ゴリゴリ揚げてしまう。数を獲るための合理的な道具立てだ。
片や私は10~50号まで背負える全調子の細手のチューブラ2.1mに,PEライン2号を巻いたバス釣り用の小型両軸受けリール。波の動揺を消し,食わせを重視。かつ錘が根に触れるのを感知して微調整できる繊細な道具立てだ。
これまで陸からのワーム釣りで釣れてくるアカミズの35cmまではメバル竿にフロロ4lbで十分獲ってきたので,強度的には不安はない。要は竿の弾力を活かしきれるかどうかにかかっている。
ちなみに私が主に使っているメバル竿は「根魚権蔵チタン8.1ft」であり,チューブラ全調子でかなりペナペナしているが,イザというときの“腰”,にかなりの信頼を置いている。「全調子では根に潜られませんか」と言う人がいるし,かつては私もそうではないかと思っていたが,それは掛けてから次の瞬間のリールの巻き方と竿の操作を合わせることでカバーできる。あとは,そこそこのレベルの竿であれば,竿がサカナを浮かしてくれる。また,そうしてくれない竿ではダメなのだ。この竿とレブロスの2500番の組み合わせで,スズキ70㎝程度なら楽に獲れる。
****************************
出港まもなく小手調べで始めた近場から,いきなりアカミズとカサゴが連発し,その後,場所を変えるたびに食うこと食うこと。底ではアカミズやらカサゴやらが,口をあけて待っているのではないか,と思うほど安易に釣れる。アカミズは全て1キロ前後,カサゴは20~30cmといったところ。潮が悪くなるとオコゼやマトウダイやらが顔を出したが,場所をちょっと変わればまたアカミズだ。ひとわたり釣ったところで,長崎船頭いわく,“ウエちゃん,これの親玉がおるとこに連れてくけん”といって少し走り,そこでは予定通り2キロ級が2尾出た。
結局,餌がなくなる昼前までに,全部で2キロ大を2尾に1キロ前後を18尾,ホンカナ(マハタ)が2尾,カサゴは多数。これにはたまげた。世間並みで言えば大漁も大漁,水揚げ金額にして活魚であれば10万円近い。筋金入りの漁師の実力とはこういうものかと思い知らされた。彼の,サカナを追跡する姿勢とそこから出る結果には,驚嘆を通り越し,ただ感動あるのみ。
ただし,このような漁師は,私が知る限り,島根から石川県まで7府県を歩いてみても聞いたことがない。おそらく山陰ナンバー1だと思う。しかもこれが今は本業ではないというのだから,これまた・・・。その上,これだけ釣っても「今日は潮が悪かったしサカナがこまい。またこんど釣らせるけん」と渋い顔なのだから恐れ入る。大きいアカミズとは3キロ越えを言うのだそうだ。3キロ数本に2キロ級が10ばかりも混じればまずまずだけど,なんてことを平気で言う。
****************************
この日の釣りを振り返ってみてアカミズについて思うことは,けして釣ることがそれほどおもしろいサカナではない,ということだ。実際に潜って観察するとわかることだが,彼らは自分の穴を中心に縄張りをもっているので,潮が動いていてその範囲内に餌ないしルアーを落とすことができればほぼ確実に食う。その穴から釣ってしまっても,しばらくすると次のアカミズが入る。先述した“持ち穴の数が勝負どころ”というのは,ここだ。
従って船のアカミズ釣りの場合,そのピンポイントに船を持っていく船頭の技術が9割を占め,釣り手の技術は残り1割だ。根掛かりをうまく避けつつ,食わせてから穴に入らぬよう最初にうまく引き剥がすことができれば,あとはゴンゴンと重く竿を叩くのみ。最後まで抵抗することは少なく,水面に釣り上がってしまえばほとんど暴れない。更に船上に横たわればおとなしいものだ。 “根”に依存して生活しているだけに,とにかく“根”から引き離されると意外なまでに情けない。アカミズに限らず,ハタ類は全てそうだ。
そういうわけだから,竿は堅く強い必要はない。むしろ柔軟で食い込みが良く,しかし掛かったあと根に引きずり込むのを阻止できる粘り腰がある竿がよいとみた。そういう意味では今回の道具立ては的を得ていたと言ってよいであろう。軟・硬両方試してみたが,先調子や堅い竿では波の動揺を消すことができずに警戒心を与え,従って,アタリ始めてから離してしまうことも多い。ここに差が出る。また,ハリスの太さは思いのほか影響があるようだ。これはアカミズに対してというより,餌の動きを左右するという意味で。5号と6号のフロロを使ってみたが,わずか1号差にもかかわらず,アタリの回数では断然5号に分があった。
引きの強さという点では,今回,水面付近までドラグを引き出すような引き方をしたのは2キロ級だけであり,このときは上針に2キロ,下針に1キロのアカミズが掛かっていた。結局,釣り自体の味わいとしては,小さくても日ごろ追っかけているメバルの方が断然おもしろい。ただ,なんといってもアカミズの食味には捨てがたいものがある。それどころか,山陰のサカナの中では,ノドクロ(アカムツ)を超える高級魚である。これは味の真価を追求しないわけにはいくまい。
沖上がり後,長崎さんが,アカミズは刺身以外にどんな食い方があるだろうか,と言うので,それでは今夜ウチにおいでませとお誘いし,いくつか作ってみた。
なにせ,アカミズもカサゴも売るほどある。急遽,松江から当ブログの大家さんである釣り天狗兄弟とノリちゃんも呼び寄せて,総勢7名の“アカミズの宴”と相成った。
さてその内容をご紹介すると・・・,
一, 造り
二, 昆布締め
三, 焼きちり
四, カルパッチョ
五, 塩焼き(カサゴ)
六, 野菜蒸し
七, アカミズ飯
今回は,アカミズの「可能性」というよりは「真価」を探ることが目的であるため,いずれの料理もほとんど手を加えず,加えるとしても日本,あるいは外国の古来よりある調理法を基本とし,あくまでも素材の味を尊重するかたちにとどめた。
以下,詳細を書いてみよう。
一,【アカミズの造り】
アカミズは,白身の肉に独特の甘味と,淡泊なようで舌にうっすらと良くなじむ脂を乗せている。その上なんといっても,肉の腰が秀逸である。その点,1~2㎏の太めのものが特によい。
当然ながら,釣り上げたものをイケスで餌吐きさせ,しかる後に即殺・放血,すなわち“活け締め”とし,濡れ新聞にくるんで氷をあまり打たずにおく。こうしておけば,身が白く濁らず,刺身にしても美しい半透明に保たれる。
洗いにするのであれば,硬直が起こる前に薄くそぎ切りして氷水にさらせばよい(過去ログ「スズキの臭味」参照)。
タイやヒラメなど多くの上級白身魚で共通していることだが,アカミズも刺身として旨いタイミングは2度ある。
一回目は硬直が起こりかけのときで,上手に締められた身であれば,刺身にひくときヒリヒリっと心地よい微振動が刃先に伝わる。三枚におろし,皮をひいて背・腹のサクに分けたら,体の表側を下にして,尾のほうからそぎ切っていく。薄造りや洗いのときより若干厚めがよい。目安としては,身を包丁で削ぐとき,かすかに刀身が透けて見える程度。厚さにして4~5㎜。1枚ごとにナナメに寝かせた引き包丁で切っていくが,毎回最後の一皮分を包丁を立ててクッと押し切ってやると,並べたときにカドがきれいに立って凛々しく映える。噛み下すと,身が口の中で踊り,やがて切れのいい甘味と脂が伝わってくる。
二回目は,硬直が続いて終わりかけの頃で,肉は若干軟らかくなっているが,旨味は断然増している。じわりと甘く,しっとりと歯に絡む。これは,活け締めした1㎏前後であれば2日,2㎏前後であれば3日,きれいに下処理したアカミズをペーパーでくるみ,ラップをして冷蔵庫で寝かせる。これを造るときは,一回目の場合より若干包丁を立てた少し小さいそぎ切りとし,厚さは7~8㎜程度と少し厚め。“ポッテリと”切りつける。
書いてしまえばわずかな手法の差ではあるが,これが,味のバランスに出るのである。割烹の“割”すなわち包丁技術は,このようなところにその意味を見出すことができる。お試しあれ。
合わせるのはワサビ,そして,できれば甘くない上質の醤油がよい。たまり醤油や刺身醤油はアカミズの甘味を殺す。
二,【アカミズの昆布締め】
素の味を刺身で味わったら,少し手を加えてみる。
白身で定番の「昆布締め」であるが,これについては,“昆布締めの味に2極あり”,と申し上げたい。漬け物に例えるならば“浅漬け”と“古漬け”だ。2極というのは両の極端であって,実はその中間は味覚上中途半端でツマラナイのである。諸説あるにせよ,私はこう思う。さてその内容とは,,,
●浅漬け
①サクにとったアカミズは,5㎜程度のそぎ切りにしておく。
②できれば利尻昆布,なければ他の昆布を酢にくぐらせてから拭きとり,柔らかくしておく。酢で拭くことによって,身を締めると同時に,昆布のヌメリを除くことができる
③昆布の上に,アカミズの刺身を,半分ずつ重なるようウロコ状に並べていく。
④びっしり並べ終わったら,手の平を水で湿らし,そこに薄く粗塩をなすりつけ,並べた刺身の表面をまんべんなく軽く叩いてやる。こうすることによって,均一かつほどよい塩分が片面のみに回り,ちょうどよく身が締まる。塩の当て方と加減については,職人であれば振り塩を当てるところであろうが,我々ノンプロはこのやり方のほうがうまくいく。
⑤塩を当て終わった上から,もう一枚,同様に柔らかくしておいた昆布をかぶせ,これをラップで包み,砥石などの重しを乗せて冷蔵庫で15分。
⑥上側の昆布をはずし,このまま皿に乗せればよい。
この程度の浅漬けだと,昆布の風味と旨味がうっすらと身に移った加減となり,アカミズの旨味の邪魔をせずに盛り立ててくれる。これは,醤油は使わずワサビだけで食べるのがよい。
ところで,寝かせる時間をこれ以上かけると,こんどは“昆布風味”が“昆布臭さ”に変わり,昆布の“旨味”が“嫌み”となってアカミズの味を殺してしまう。
そう言う点では,ヒラメにせよタイにせよ,世の多くの昆布締めは寝かせ過ぎであると思う。
そこで,どうせ昆布味になるのなら徹底的にやってしまうと,これはこれで別物として味わえるからオモシロイ。これが古漬けだ。
●古漬け
①浅漬けの作り方の①から⑤まで同様。
②押しをかけて寝かせる時間を丸一日以上とする。そうすると,身はベッコウ色に透き通ってくる。これを昆布からはがし,皿に盛る。
こうすると,こんどは味の主役が魚から昆布へと変換する。これは,魚肉を媒体として昆布の旨味を味わう昆布締め,というわけだ。これは,ワサビよりも和辛子が合う。これも醤油は用いない。ビールでやるなら,ゴマ油に先っちょを浸して食うのもオツだ。
ただし,アカミズで古漬けをやるのは,もったいない。余れば別の話だが。
せいぜいイシガレイとか,スズキ,イシモチなどの,ワンランク下の白身でツマミ作りと割り切ってやるのが妥当と思う。
三,【アカミズの焼きちり】
「焼きちり」とはなんぞや?というとき,すぐに思い出す「ちり鍋」。これは身を熱い鍋に投じたときにチリッとそっくりかえって弾力が増す様を言ったものだ。
従って,焼きちりとは,生の魚肉を焼いてチリッとさせたものを指す。チリッというからには,さっと火を通し中身は生であることが前提。そして,身の固い,鮮度のよい白身の魚でなければチリッとはならない。それでは,カツオのタタキやチヌおよびグレなどの「焼き切り」はどうなのかといえば,これはチリッではないから,焼きちりにはあたらない,ということになる。
この料理は,鮮度のよいアカミズやその他のハタ類でやると最高だ。鮮度のよいマゴチやタイでもよろしい。では作り方を。
①まず氷水を用意しておく。
②サクに切って皮をひかないアカミズを,幅1.5㎝,長さ3センチ程度にずんぐり切り分け,皮を上にして,わずかに間隔をあけて耐熱皿もしくは焼き網の上に並べておく。
③簡易バーナーで皮側から火を当てるが,アカミズの皮は固いので,火の先端から少し話した距離で,皮目の脂がジリッと音を立てるまで炙ってやる。バーナーがないときは,切り身を串に刺して,皮側からガスレンジの強火で炙る。焼き加減は同様。
④すぐさま氷水に放ちあら熱をとる。
⑤ザルに上げ,フキンにくるんで軽く叩くように水気をとり,盛りつけて冷蔵庫で冷やす。
これは,洗いと並ぶ,まさに夏の一品。カイワレ大根や千切りキュウリなどを合わせ,ポン酢でやる。同じく表面だけに熱を通す「湯引き」があり,こちらも涼しげではあるが,焼きちりは,皮目の香ばしさと弾力の強い白身の合わせ技で,カラリと旨い。
四,【アカミズのカルパッチョ】
既に当家過去ログ「カルパッチョについて,ひとこと」で,本来のカルパッチョがどのようなものであるかを述べた。あらためてポイントを書いておく。
①三枚におろしサクにとったアカミズは,皮をひき,たっぷりの粗塩をまぶして皿に置く
②水分が滲出してきたら,手早く流水で塩を洗い流し,フキンで水気をよくとっておく。
③皿に,水でさらしたスライスタマネギを敷き,その上に薄くそぎ切りにした切り身を重ねずにまんべんなく乗せていく。魚の厚さは,3~4㎜程度と薄くする。
④黒コショウを挽き,身の上にまんべんなく振ったあと,ライムもしくはレモンの汁を細くまんべんなくたらしかける。
⑤ここでは彩りと夏のほろ苦みを補うために,極薄く輪切りにスライスして水でさらした緑のピーマンを散らした。
⑥最後にバージンオリーブ油を細く全体にかけまわし,これを冷蔵庫で冷やす。
過去ログでも申し上げたが,とにかく塩でちゃんと締めること,そして,調味料をかける順番を間違わないことが肝要。少なくともカルパッチョは,刺身にドレッシングみたいなものをかけただけの料理ではない。先人の知恵が詰まった郷土料理である。
五,【カサゴの塩焼き】
アカミズではないが,釣りボッカ(カサゴ)がある以上,これだけは欠かせない料理だと,今は思っている。
“今は”,というのは,長崎の出である私は,ついこのあいだまで,アラカブ(カサゴ)=味噌汁,という構図を完全に信奉しており,いつでもどこでも常にそれに忠実であった。煮付け,唐揚げなどはカサゴの味として格下であった。
なにせ,長崎では,カサゴの尾頭付き味噌汁専用の広口大型の塗り椀が存在するくらいだ。祝いだろうが法事だろうが,これでアラカブの味噌汁が出てくるのであり,ちゃんとしたアラカブ汁を出さないと,“あン家の法事のアラカブ汁はウマかったとバッテン,今日ンとはマズかのう”,とかなんとか,陰口をささやかれるのである。
が,昨年,当家ブログ大家の釣り天狗兄弟にカサゴの塩焼きが旨いと聞いて,試しにやってみたところ,これにはビックリ仰天しましたね!
焼くときの匂いといい,香ばしく新鮮な身と皮のはじけた旨さといい,ヒレ際や頭の肉の各部位の歯ごたえ・甘味といい,野趣に富んだ味わいに,引きずり込まれる思いがしたものだ。今まで吸ってきたカサゴの味噌汁も当然旨かったのであるが,これまで食ったカサゴの数の半分くらいは,過去に戻って塩焼きで食いたかったと,少しだけ思った。
それほどいい。
総合点の高いカサゴの塩焼きであるが,その詳細を述べると,わずか20㎝やそこらの小柄な体の中に,次に掲げる様々な美味を秘めている。
①背肉
②腹肉
③尾肉
④各ヒレ際の肉
⑤こんがり焼けた各ヒレ
これらを全て食べ尽くしナメ尽くしたら,頭を持って腹側を上にして,
⑥背骨に沿ってついているむっちりした浮き袋
⑦背骨と頭をつなぐ,首を動かす細長い筋肉2本(これがカサゴの身の中で最も旨い)
⑧目の裏側にある動眼筋2片(これがカサゴの身の中で最も歯ごたえがよい)
⑨目
⑩脳みそ(背骨をはずした頭から吸い出す)
⑪ほお肉およびその周辺
⑫唇
⑬舌
ね,スゴイでしょう?それぞれのパーツが全部味が違う。
更に,これらを全て味わい尽くしたら,全ての残骸を椀に入れて熱湯を注ぎ,アラを箸で突きほぐし、しばし待つ。これに薄口醤油数滴をたらしてズーッと吸って,完了,となるのである。
以前ご紹介したノドグロの塩焼きとは別の意味で,こんな塩焼き,ほかにありませんよ。
①カサゴは大きすぎるとやはり身がゆるくなるので,20㎝前後がよい。体側に肩から尻ビレにかけて背骨に到達する包丁を入れ,あらかじめ薄く塩をまぶして暫く置く。このときに,のど元から腹の中までも塩を当てることが大切。要は,全体に,塩をまわしてやることが肝要。
②目が塩分でうっすらと白くなったところであらためて各ヒレに化粧塩を施し,身の両面にも軽く塩を振る。このときの塩の振り方は,湿った手に付着した塩を,指をパッパッと開いて飛び散る程度,これでよい。
③まず,背を向こうに頭は左,つまり表側をちょっと焼く。そうすると,釣った当日のカサゴであれば,グリルの中で上方に反り返りはじめるので,すかさずひっくり返す。そして7割焼き,表に戻して3割を焼き上げる。
コツはこんなところ。反り返るのをそのままにしておくと,ひっくり返せなくなるのです。これは高鮮度の証であるわけですが,ちょっと困る。
六,【アカミズの野菜蒸し】
香港および上海あたりで,何が高級海鮮料理かといえば,アカミズを含むハタ類の蒸しもの,これに尽きます。清蒸(チンジャオ)という料理で,白髪ネギや香草と共に,塩と老酒少々で蒸し上げる。これにはイセエビやワタリガニ,その他の魚をはるかに凌ぐ値段がついている。イケスに泳がせてあるアカミズを指名(?)すると,彼は料理人の手によって速やかに拉致され,下処理され,速やかに蒸されて出てくる。万事が速やか,なのである。
過去ログで書いたかもしれないが,本格の中華料理店には,この蒸し魚専門の職人がおり,最上級の給料が与えられているという。魚のサイズ,脂の乗り,時期,肉質などをグッとにらんで見極め,1分と違わずピタリと最適な蒸し加減に仕上げる。横浜あたりには,いるのですね,こういう4000年の歴史を感じさせるそのような料理人が。
では我々家庭人がやる場合,いくら活け締めしたところで活魚にはかなうべくもない。それならいっそ,たっぷりの野菜の力を借りて,そしてアカミズの旨味も野菜に吸ってもらって,家庭的で豊かな一品に仕上げようというわけだ。
ところで,大きなサカナを蒸すときに,ウチには蒸し器もないし,大きな皿もない,と諦めていないだろうか。いい方法がありますヨ。
番外【蒸し器がなくても蒸す方法】
①アルミホイル4枚を同大に切り,重ねる。
②四辺のうち一辺を2㎝ほど折る。折った部分を更に半分に折る,そして更に半分に。これで,重ね折りした部分は5㎜ほどになっているはず。
③ここでアルミホイルを左右2枚ずつに広げ,真ん中の折った部分をキッチリ押して平らにすると,アルミホイル2枚重ねの大きなシートができあがる。
④この両端を絞って,舟状に整形する。これにサカナなどを入れ,大きなフタつきフライパンに半分ほど水を沸騰させ,舟をそこに浮かせてフタをすれば,立派に蒸すことができる。
⑤大皿に乗せかえる場合は、ホイルのまま乗せ、ホイルの中央付近に切れ目を入れ、そこから両端を引っぱるように破ってホイルだけ抜けば(コンビニの握り飯で、ビニールをぎゅっと引くと、海苔とご飯が一緒になる、あの感じ)、サカナは崩れずそのままの姿で大皿に残る、という次第。
さて,蒸す道具の問題もクリアしたところで,野菜蒸しの作り方だ。
①野菜は,ニンジンは千切り,細ネギ・エノキは5㎝,シメジはばらし,これらをボウルの中で,少量の塩を振って混ぜておく。
②アカミズはウロコをとり,頭つきのままエラ・腹を除き,全体の水気をよく拭いておく。
③アカミズの体側に両面とも3カ所,背骨に到達する程度の包丁を入れ,全体に塩をまぶして30分置く。若干強めに塩をしてよい。
④アルミホイルで作った舟に野菜を少し敷き,口や腹に野菜を詰め入れたアカミズを寝かせ,その上に更に野菜をかぶせる。最後に少量のサラダ油をアカミズにかけてやる。
⑤フライパンに3㎝ほどの水を沸かし,舟を入れフタをする。そのまま強火で15分程度蒸し上げる。フライパンの水が少なくなくなったら足せばよい。包丁目の間から骨が見えたら完成。
アカミズに入れる包丁目は,火の通りをよくすることと,食べるときに肉をとりわけやすくすることが目的だ。
この料理のポイントは,酒を使わないこと,そして,野菜とサカナの塩加減を,出来上がりを想像して調節することにある。
この料理も,おわかりと思うが,和・洋・中,自在である。過去ログ「塩煮の世界」を参考とされたし。
七,【アカミズ飯】
一般的に知られているサカナの飯といえば、マダイを使った「タイ飯」だが,これには2タイプある。
瀬戸内海中西部を中心とした漁師料理であるタイ飯は,海水で研いだ米を硬めに水加減し,下処理したタイを丸ごと入れて炊き込んだもの。タイをあらかじめ焼いてから入れる場合もあるが,これは漁師料理を陸上でやるようになってからのこと。炊き上がったら,骨を取り除いて身だけを飯に混ぜ込む。マダイのほかに,クロダイやキダイでやる地方もある。
もうひとつは愛媛県の豊後水道に面した宇和島周辺におけるタイ飯で,これは刺身状に切ったサカナを薬味と共に醤油ベースの下地に漬けた,ヅケの一種である。これを飯に乗せて食う。豊後水道エリアの各県にはサカナのヅケでを食う文化が広がっており,たとえば大分県佐賀関では,醤油とミリンを合わせて刻みネギとすりゴマ,唐辛子を混ぜた下地にサバの刺身を漬けたものを「リュウキュウ」というし,大分と愛媛の中間にある日振島では,アジなどの青魚を薬味と共にヅケにしてご飯の上に乗せ,卵の黄身を落としたものを「日向(ひゅうが)飯」と呼んでいる。これは宇和島水軍の食習慣の名残だ。
更に宇和島中南部に下ると,そこで「タイ飯」となる。原理は同じで,要は,「その土地でなじみの深いサカナを刺身に切って,薬味と共に醤油地に漬け込み,それで飯を食う習慣」が,豊後水道には根強いということだ。
ついでながら,同じ愛媛県内でも,豊後水道側ではヅケ飯のことだが,瀬戸内海に面した今治あたりでタイ飯といえば炊き込みになる。このへんの分水嶺がどこにあるかは定かでないが,やはり食習慣というものは,その風土・生活から発生し,伝播して形成される。
ともあれ,ここでは宇和島流の「アカミズ飯」だ。しかし言葉の響きがマズそうですな。瀬戸内海の呼称で「アコウ飯」のほうが,何やらうまそうに聞こえるが,瀬戸内海に斯様な食い方はない。もっとも,高級なアカミズをヅケで食うなんて人は,おそらくおらんでしょう。
名称はどうでもいいが,とにかく旨い。当然,タイやヒラメのヅケにはない白身の旨さがある。アカミズが手に入らなければ,ほかのハタ類でもやる価値アリだ。では作り方を。
①アカミズは皮をひき、サクにとり,5㎜程度のそぎ切りにしておく。
②ボウルに入れた醤油に徐々にミリンを加えていき,塩辛さの“カド”がとれる瞬間で加えるのをやめる。甘すぎれば身の味を損なうし、足りなければ塩がきつい。
③下地に大葉を刻み入れ,そこにすりゴマ(白)を,ドロッとするくらい多めに加えて混ぜておく。
④この中にアカミズを投入してざっくり和え,暫くののちに,これを熱い白飯の上に敷き詰める。
これだけです。
アカミズ自体が大変味の深いサカナなので,“リュウキュウ”のようなネギも,“日向飯”のような卵も加えない。下地はシンプルでよい。薬味は大葉だけ。欠かせないのはすりゴマ。
ヅケが残ったら,翌朝,ワサビを添えて茶漬けにするのがいい。一日の始まりとしては気持ちがよいものだ。
****************************
さて,この日に作らなかった料理で気になるものがある。
お集まりの皆様が,既に満腹してしまったから作れなかったわけで,残った骨・頭,すなわちアラを使った料理を少し書いておく。
【塩煮,およびマース煮】
いずれも適する。調理方法については過去ログ「塩煮の世界」および「もうひとつの塩煮」を参照されたし。これはアラのみならず,一尾づけでやっても当然おいしい。
【煮付け】
一尾をまるまる煮付けてしまうと,意外と月並みな味だ。残りアラでやるのはよい。
鍋に酒と水を半々で割って沸騰させ,ミリン少々を加えて際沸騰したらアラを投入。火が通ったら,3回くらいに分けて醤油を加えていく。
【酒蒸し】
これも残りアラでやるのがよい。頭は半割し,背骨は適当に切り分け,塩をして暫く置く。鍋に酒を2㎝くらい注いで強火にかけ,沸騰し始めたらアラを投入してフタをする。煮立つ泡がアラをかぶるくらいに火加減し,10分でできあがる。
これは熱いうちにポン酢をかけまわし、刻みネギで食うのがよい。
【焼き】
頭を半割して塩をあて,しばらく置いてから焼く。
頭まわりの肉は,特に弾力に富み,かつ歯切れ良く,さっぱりとした味だ。
今回はカサゴを焼いたが,この代わりに出してもよかろう。
****************************
やはりアカミズは,体の隅々まで,真の実力者だと思う。値段が高いだけのことはある。実は,内臓や皮まで,捨てるところがない。これらはアラと共に煮付けにするのがいい。けして捨ててはいけない。捨てるのは,結局ウロコとエラだけだ。
このたびのアカミズの宴は,延々5時間に及んだ。
使用したアカミズは2キロ級1尾,1キロ級5尾,800グラム級2尾。あとはカサゴを7尾。
残りのアカミズは皆で分けて持ち帰った。
山陰の海では,こんなことも,たまには,ある。
今年の夏も暑くなりそうだ。うっとうしいスズキの野郎はとりあえず置いといて,沖でアカミズとじっくりつき合うのもよい。
2007年07月13日
梅雨の真水を、飲むサカナ
本年初夏の雨不足を反省したのか,このところ天もドシドシ雨を注ぎ,九州などではいささかやりすぎ。過ぎタルは及ばざるどころか,被害が及び過ぎで困っている。
ここ境港も雨続きで釣行のタイミングを逃し気味。こんな状況の中,やはりいかにコンスタントにオカズを確保するか,が重要課題。我が家のサカナ在庫はチヌ半身とメバル3尾であったが,昨夜は松江の釣天狗兄弟の訪問があり,全て食ってしまった。もうこれは出漁せざるをえない。サカナ在庫がないこと自体,我が家では由々しきことなのだ。
ところで余談になりますが,前回「末期のサカナ」と書いた表題を「マッキノサカナ?」と読んだ人が,びっくりするくらい結構いた。「マツゴ」のサカナですね,念のため。まさか今回も「梅雨」を「バイウ」などと読む人はサスガにいないとは思うが,念のため。けして間違いとは言えないが,やはり言葉も状況によって適正表音がある,ということで・・・。
***************************
さて本題。
“○○は梅雨の水を飲んで旨くなる”という言い習わしは,全国各地,特に関東以西の沿岸で聞くことができる。○○,は当然サカナであり,カレイであったり,タコであったり,キスであったり,アナゴであったり,シャコであったり,イサキやメバルなどなど,探せばもっとあると思う。いったいどういう意味なのであろうか。単によく釣れる時期を言っているとも思えない。たしかに,ここに掲げたサカナ達は,梅雨の雨が降るごとに,なぜか旨味を増す感じがするし,脂を乗せてくる。成長もいい。
数ヶ月も前になると思うが,国営放送が「富山湾」の豊饒さの謎を科学的に追跡したドキュメンタリーを発表し,何らかの賞に輝いたと記憶している。その中で,急峻な能登半島の豊かな森林が蓄える地下水が,川や井戸のみならず沿岸の海底からユラユラと湧き出ており,周囲にカレイなどの底棲魚類が蝟集して餌をとっている光景が報じられた。いわく,この真水が魚族を涵養するということであった。
「城下(しろした)カレイ」で有名な,大分県瀬戸内海側のマコガレイも同じ理屈で説明されており,沿海に臨む日出(ひじ)町は暘谷(ようこく)城跡の前浜の海底に真水が湧き出ているがために,カレイの味が良いのだと言われている。その理由は明らかにされていないが,経験的になぜかそう言われている。
毎日のように海を見,釣りをしていると,晴天から転じて降雨し,雨が上がってその後どのように海が変化していき,サカナの所在や行動状況がどう変わるかといったこと,すなわち雨の海に対する影響が,なんとなくわかってくる。釣果にも影響が出るのでお気づきの方も多いと思う。
川釣り師であれば,水の出所に近いこともあって,もっとハッキリと認識している。釣りをしている現在地が晴天であっても,水温や濁りの変化で上流部の状態を推測し,また,熟練した釣り師は変化する状況に合わせて釣り場所と釣り方を変えてゆく。海の釣りではどうであろうか。
****************************
最近もっぱら冷蔵庫がわりに通っているメバル・スズキ・キジハタ等の安定漁場の例で言うと,ドッと雨が降ると,少し遅れて笹濁りが始まるが,透明度があまり落ちない状態がしばらく続く。いわゆる“笹濁り”だ。この過程で一時的にサカナの活性が上がるタイミングがある。それを越えると,それまで釣れていた魚は移動し,あるいは沈滞し,索餌活性は低下する。そして,雨が止んだ翌日ないし数日後に,グッと濁って透明度が著しく低下し,サカナの活性は最低となり。その後更に晴天が続くと暫時透明度が戻り,サカナも通常の状態に戻る。
具体的な魚種で言えば,スズキなどは雨が降って濁り始めた頃,その後に来る強い濁りまでの間に特に激しく餌をとる。メバルやキジハタ,アジなどは,雨が続くに従って活性が低下し,グッと濁ったあとに透明度が復活する初期の頃に荒食いする。キスやカレイでは,濁りのピークを越えて透明度がかなり回復したあたりで盛んに口を使い始める。
よく観察してみると,濁り好きと言われるスズキにせよ,濁りのピークに濁りの中で釣れてくることは稀である。濁りと濁りの合間に釣れたり,濁りが生じたり消えたりする途中のどこかに,よく食ってくるタイミングがある。サカナの索餌行動と濁りに,何らかの因果関係があるには違いない。
まず視覚的に考えてみると,フィッシュイーターが追いかけ回すシラスなどの小型魚にとって,濁りは我が身を隠してくれるベールのように機能する反面,捕食者から見れば,餌に近づきやすくなる隠れ蓑にもなるわけだ。ただ,これも濁り過ぎれば餌を見つけにくいということになり,逆効果となる。
従って捕食者であるスズキやアジなどの活は,雨が降り始めてから濁りがピークになるまでの一時期,結構早い段階で高まるのは,そういうわけではないかと推測している。スズキは視覚的にちょうどよい濁りを利用して餌を効率よく取ろうとしている。
では,小魚を追いかけ回すわけではないカレイやキスやアナゴはどうであろうか。
これは生態系の中の栄養の流れを考えてみれば説明がつく。富山湾を思い出していただきたい。山から流れ出る川水や地下水には,様々なミネラル分が溶け込んでおり,海洋生産の基礎となる植物プランクトンが育つために不可欠な窒素,リン,カリウムといった成分も多く含まれる。降雨があれば,陸上から更に多くの栄養物質が洗い流され,河川を経て海へ流入する。
雨が降り始めても,土砂が混じらない限り,海水はあくまでも薄濁り程度であるが,濁りがピークになるのは,雨が止み,次の日照が続いたときだ。
すなわちこの濁りは,植物プランクトンが雨水に流された栄養物質を吸収し,太陽エネルギーを得て増殖した結果なのである。そして,増殖した植物プランクトンを動物プランクトンが捕食していくと,次第に水は澄んでくる。また,植物プランクトンが増殖のピークを越えて自然に死滅して沈殿すれば,彼らが吸収した栄養物質は,有機物として海底に帰る。
結果として動物プランクトンに形を変えた海の濁りは,イワシの稚魚であるシラスをはじめ,様々な小生物に補食されていき,更にこれらはより大きな生物に補食されていく。たとえばアジやメバルやスズキなど。
一方,植物プランクトンが死滅して海底に沈殿してできた栄養物質は,付着性の生物や貝類やゴカイの仲間などに消費され,これらもまた,より大きな生物に補食されていく。たとえばカレイやキスやクロダイなど。
冒頭に書いた,“サカナは梅雨の水を飲んで旨くなる”,の一件は,つまるところ,こういうわけではないかと思う。当然ながら、けして雨水を飲んで旨くなるわけではない。この表現は,あくまでも経験則であり比喩である。
梅雨のまとまった雨水によって栄養が海に供給され,食物連鎖によってそれが循環的に消費され,より高次な捕食者であるサカナの餌となる。結果,サカナが肥え,味が良くなってゆく。
逆に言えば,断続的な雨と比較的強い日照の両方が交互に得られる梅雨時期こそ,このようなことが起こりうるということだ。
ただし,これも,雨が運んだ陸の栄養を循環させる「健全な食物連鎖」があってこそだ。
干潟が消え,渚に道路が通り,磯がコンクリート護岸となりつつある現代の海において,連鎖を担う生物の種類も数も減っている。梅雨の水を飲んで旨くなるサカナのその旨さは,この説に照らせば明らかに質が落ちているはずだ。昔日の自然が存在した豊かな海の,梅雨のサカナの旨さは,いかばかりであったろうか。
****************************
さて,ここ数日雨が続いた。今日は少し晴れ間も見えたが,濁り初めのチャンスを狙うには雨が続きすぎた。次の照りが来れば,グッと濁る。そのアトのひとチャンスで勝負だ。
既に述べたように,梅雨の雨による濁りはサカナにとって恵みの濁りだ。ただ,釣りによってサカナを追いかける我々としては,今見ている海の濁りが,どの段階の濁りなのかを前後の状況から見極め,食い気のあるサカナの所在を探すことが肝要となる。
濁りにチャンスあり。しかし,魚種によって濁りに対する行動や活性は異なる。狙うサカナが今の濁りに対してどこでどのようにしているのか,これを考え推測し,つかむことが安定したオカズ供給につながる。
この時期,メバルも相変わらず旨いのだが,何せこのところスズキがメキメキと味を上げている。特に40~50㎝くらいのがよい。栄養豊富な真水が育てたプランクトンを餌とする小イワシに脂が乗ってくるからであって,これを食べるスズキも当然良くなる。体高も幅も広くなり,風味のある脂が乗り,なんといっても塩焼きが最高に旨い。旨いのだから,この時期は,けして“またスズキが釣れてしまった”などとは言わない。
もちろん,当家の過去ブログ「スズキの臭味」にて述べたとおり,下処理が肝心だ。現場で活け締めして,台所でウロコと内臓を取ったら体表を塩ずりし,酒を振りかけてから水で洗い,切れ目をいくつか入れたら塩をまんべんなく薄くあてて暫く置き,焼く前にあらためて振り塩をする。表をちょっと焼いたあと,裏で7割を焼き,再び表にかえして3割を焼き上げる。表面はパリッと,中はジューシーに仕上げる。身肉もさることながら,ヒレの根元,シッポのキワなどにムッチリとした旨味を湛え,春の痩せスズキとは比較にならない別物だ。
まさに“梅雨の雨を飲むごとに”,スズキも旨くなってゆく。いいですな。
ここ境港も雨続きで釣行のタイミングを逃し気味。こんな状況の中,やはりいかにコンスタントにオカズを確保するか,が重要課題。我が家のサカナ在庫はチヌ半身とメバル3尾であったが,昨夜は松江の釣天狗兄弟の訪問があり,全て食ってしまった。もうこれは出漁せざるをえない。サカナ在庫がないこと自体,我が家では由々しきことなのだ。
ところで余談になりますが,前回「末期のサカナ」と書いた表題を「マッキノサカナ?」と読んだ人が,びっくりするくらい結構いた。「マツゴ」のサカナですね,念のため。まさか今回も「梅雨」を「バイウ」などと読む人はサスガにいないとは思うが,念のため。けして間違いとは言えないが,やはり言葉も状況によって適正表音がある,ということで・・・。
***************************
さて本題。
“○○は梅雨の水を飲んで旨くなる”という言い習わしは,全国各地,特に関東以西の沿岸で聞くことができる。○○,は当然サカナであり,カレイであったり,タコであったり,キスであったり,アナゴであったり,シャコであったり,イサキやメバルなどなど,探せばもっとあると思う。いったいどういう意味なのであろうか。単によく釣れる時期を言っているとも思えない。たしかに,ここに掲げたサカナ達は,梅雨の雨が降るごとに,なぜか旨味を増す感じがするし,脂を乗せてくる。成長もいい。
数ヶ月も前になると思うが,国営放送が「富山湾」の豊饒さの謎を科学的に追跡したドキュメンタリーを発表し,何らかの賞に輝いたと記憶している。その中で,急峻な能登半島の豊かな森林が蓄える地下水が,川や井戸のみならず沿岸の海底からユラユラと湧き出ており,周囲にカレイなどの底棲魚類が蝟集して餌をとっている光景が報じられた。いわく,この真水が魚族を涵養するということであった。
「城下(しろした)カレイ」で有名な,大分県瀬戸内海側のマコガレイも同じ理屈で説明されており,沿海に臨む日出(ひじ)町は暘谷(ようこく)城跡の前浜の海底に真水が湧き出ているがために,カレイの味が良いのだと言われている。その理由は明らかにされていないが,経験的になぜかそう言われている。
毎日のように海を見,釣りをしていると,晴天から転じて降雨し,雨が上がってその後どのように海が変化していき,サカナの所在や行動状況がどう変わるかといったこと,すなわち雨の海に対する影響が,なんとなくわかってくる。釣果にも影響が出るのでお気づきの方も多いと思う。
川釣り師であれば,水の出所に近いこともあって,もっとハッキリと認識している。釣りをしている現在地が晴天であっても,水温や濁りの変化で上流部の状態を推測し,また,熟練した釣り師は変化する状況に合わせて釣り場所と釣り方を変えてゆく。海の釣りではどうであろうか。
****************************
最近もっぱら冷蔵庫がわりに通っているメバル・スズキ・キジハタ等の安定漁場の例で言うと,ドッと雨が降ると,少し遅れて笹濁りが始まるが,透明度があまり落ちない状態がしばらく続く。いわゆる“笹濁り”だ。この過程で一時的にサカナの活性が上がるタイミングがある。それを越えると,それまで釣れていた魚は移動し,あるいは沈滞し,索餌活性は低下する。そして,雨が止んだ翌日ないし数日後に,グッと濁って透明度が著しく低下し,サカナの活性は最低となり。その後更に晴天が続くと暫時透明度が戻り,サカナも通常の状態に戻る。
具体的な魚種で言えば,スズキなどは雨が降って濁り始めた頃,その後に来る強い濁りまでの間に特に激しく餌をとる。メバルやキジハタ,アジなどは,雨が続くに従って活性が低下し,グッと濁ったあとに透明度が復活する初期の頃に荒食いする。キスやカレイでは,濁りのピークを越えて透明度がかなり回復したあたりで盛んに口を使い始める。
よく観察してみると,濁り好きと言われるスズキにせよ,濁りのピークに濁りの中で釣れてくることは稀である。濁りと濁りの合間に釣れたり,濁りが生じたり消えたりする途中のどこかに,よく食ってくるタイミングがある。サカナの索餌行動と濁りに,何らかの因果関係があるには違いない。
まず視覚的に考えてみると,フィッシュイーターが追いかけ回すシラスなどの小型魚にとって,濁りは我が身を隠してくれるベールのように機能する反面,捕食者から見れば,餌に近づきやすくなる隠れ蓑にもなるわけだ。ただ,これも濁り過ぎれば餌を見つけにくいということになり,逆効果となる。
従って捕食者であるスズキやアジなどの活は,雨が降り始めてから濁りがピークになるまでの一時期,結構早い段階で高まるのは,そういうわけではないかと推測している。スズキは視覚的にちょうどよい濁りを利用して餌を効率よく取ろうとしている。
では,小魚を追いかけ回すわけではないカレイやキスやアナゴはどうであろうか。
これは生態系の中の栄養の流れを考えてみれば説明がつく。富山湾を思い出していただきたい。山から流れ出る川水や地下水には,様々なミネラル分が溶け込んでおり,海洋生産の基礎となる植物プランクトンが育つために不可欠な窒素,リン,カリウムといった成分も多く含まれる。降雨があれば,陸上から更に多くの栄養物質が洗い流され,河川を経て海へ流入する。
雨が降り始めても,土砂が混じらない限り,海水はあくまでも薄濁り程度であるが,濁りがピークになるのは,雨が止み,次の日照が続いたときだ。
すなわちこの濁りは,植物プランクトンが雨水に流された栄養物質を吸収し,太陽エネルギーを得て増殖した結果なのである。そして,増殖した植物プランクトンを動物プランクトンが捕食していくと,次第に水は澄んでくる。また,植物プランクトンが増殖のピークを越えて自然に死滅して沈殿すれば,彼らが吸収した栄養物質は,有機物として海底に帰る。
結果として動物プランクトンに形を変えた海の濁りは,イワシの稚魚であるシラスをはじめ,様々な小生物に補食されていき,更にこれらはより大きな生物に補食されていく。たとえばアジやメバルやスズキなど。
一方,植物プランクトンが死滅して海底に沈殿してできた栄養物質は,付着性の生物や貝類やゴカイの仲間などに消費され,これらもまた,より大きな生物に補食されていく。たとえばカレイやキスやクロダイなど。
冒頭に書いた,“サカナは梅雨の水を飲んで旨くなる”,の一件は,つまるところ,こういうわけではないかと思う。当然ながら、けして雨水を飲んで旨くなるわけではない。この表現は,あくまでも経験則であり比喩である。
梅雨のまとまった雨水によって栄養が海に供給され,食物連鎖によってそれが循環的に消費され,より高次な捕食者であるサカナの餌となる。結果,サカナが肥え,味が良くなってゆく。
逆に言えば,断続的な雨と比較的強い日照の両方が交互に得られる梅雨時期こそ,このようなことが起こりうるということだ。
ただし,これも,雨が運んだ陸の栄養を循環させる「健全な食物連鎖」があってこそだ。
干潟が消え,渚に道路が通り,磯がコンクリート護岸となりつつある現代の海において,連鎖を担う生物の種類も数も減っている。梅雨の水を飲んで旨くなるサカナのその旨さは,この説に照らせば明らかに質が落ちているはずだ。昔日の自然が存在した豊かな海の,梅雨のサカナの旨さは,いかばかりであったろうか。
****************************
さて,ここ数日雨が続いた。今日は少し晴れ間も見えたが,濁り初めのチャンスを狙うには雨が続きすぎた。次の照りが来れば,グッと濁る。そのアトのひとチャンスで勝負だ。
既に述べたように,梅雨の雨による濁りはサカナにとって恵みの濁りだ。ただ,釣りによってサカナを追いかける我々としては,今見ている海の濁りが,どの段階の濁りなのかを前後の状況から見極め,食い気のあるサカナの所在を探すことが肝要となる。
濁りにチャンスあり。しかし,魚種によって濁りに対する行動や活性は異なる。狙うサカナが今の濁りに対してどこでどのようにしているのか,これを考え推測し,つかむことが安定したオカズ供給につながる。
この時期,メバルも相変わらず旨いのだが,何せこのところスズキがメキメキと味を上げている。特に40~50㎝くらいのがよい。栄養豊富な真水が育てたプランクトンを餌とする小イワシに脂が乗ってくるからであって,これを食べるスズキも当然良くなる。体高も幅も広くなり,風味のある脂が乗り,なんといっても塩焼きが最高に旨い。旨いのだから,この時期は,けして“またスズキが釣れてしまった”などとは言わない。
もちろん,当家の過去ブログ「スズキの臭味」にて述べたとおり,下処理が肝心だ。現場で活け締めして,台所でウロコと内臓を取ったら体表を塩ずりし,酒を振りかけてから水で洗い,切れ目をいくつか入れたら塩をまんべんなく薄くあてて暫く置き,焼く前にあらためて振り塩をする。表をちょっと焼いたあと,裏で7割を焼き,再び表にかえして3割を焼き上げる。表面はパリッと,中はジューシーに仕上げる。身肉もさることながら,ヒレの根元,シッポのキワなどにムッチリとした旨味を湛え,春の痩せスズキとは比較にならない別物だ。
まさに“梅雨の雨を飲むごとに”,スズキも旨くなってゆく。いいですな。
2007年07月05日
末期のサカナ
「死ぬ前に何かひとつだけ食ってよろしい」という状況になったとき,ナニを食って死にたいか。
そこにどう答えるか。
前回“忘我の味”,などということを書いていたら,その延長でこんなことに思い当たった。
ひとそれぞれいろいろあろうが,まあ,ここでは当然サカナが話しの対象となる。これを仮に“末期のサカナ”としよう。
これについて,私はこれまで,いつでもどこでも,即座に「サバです。特にサバ寿司です!」とキッパリ叫んでいたものだ。逝く前に,旨いサバ寿司をひとくち食って一瞬味わったのち静かに目を閉じたい。と思っていた。
旨いサカナを数えればキリがない。
獲れる時期,場所,サイズ,鮮度,そして調理法,食環境,等々が適切に融合すれば,それぞれに旨いし,或いは旨くすることができる。
しかし“末期のサカナ”となると,単なる旨いマズイだけでなく,むしろ個々人の内面的な世界と強くつながっているサカナ,あるいはそのような料理,ということになるのかもしれない。最近流行のソウルフードなどとは,また意味合いが違うのだが。
さばアレルギーの人には申し訳ないが,「サバ」のうまさ。これは今さら言い立てるまでもあるまい。
適切な手法で鮮度を維持し適切な処理さえ心得ておけば,その身肉は,およそ魚類界において最強クラスの旨味をもち,それはいかなる料理に仕立てても揺らぐことがない。負けないのである。
たとえばサカナのカレーを作るとき,マグロ,アジ,サバ,サンマ,その他白身のサカナいろいろと使ってみると,違いがよくわかる。香辛料に負けず,いくら煮込んでも歯ごたえも維持しつつ,噛み下した直後からグッと迫る旨味を固持しているのがサバだ。それだけに,“品のある味”とは言い難いが,まあ強くしっかりしているのである。多少鮮度が落ちている場合であっても,だいたい旨味が勝つ。そばつゆなどにグッとくるコクを出したいときに,サバ節を加えるのもこういうわけだ。
塩サバ,焼サバ,汁物,煮物,揚物,刺身にシメサバ,サラダにしてもよいし,オードブルにも,和・洋・中全てに化ける。我が国では塩や糠に漬けて保存食にもする。“鯖の水煮”はサカナ缶詰の代名詞たる存在だ。汎用性が広く,人間の魚食生活に古くから深く溶け込んでいる。その点,大衆性の強い青ザカナの一員でありながら,他の青ザカナとは歴史と実力が違う。
中でも,こと「サバ寿司」となると,別格だ。
関東のバッテラ,土佐の姿寿司,最近では若狭の焼きサバ寿司など,要は塩をあてたサバを酢でシメ,整形した酢飯に乗せて押しをかけた寿司は各地に存在し,余計な添加物さえ入っていなければそれぞれに旨いが,ここで言うのは京都で作る郷土食たる「サバの棒寿司」だ。
京都のアレは,日本の風土と文化伝統が生んだサバ料理の最高傑作ではないかと思う。
日本海は若狭湾の,脂の乗りすぎない肉厚の朝獲れサバを背割りにしてひと塩し,これをカマス袋に担いで京都まで運んだ。この道が言わずと知れた「サバ街道」だ。福井県の若狭小浜から南西に下って琵琶湖西岸に至り南下し,幾多の峠を越えて京都に至る,全長約72㎞の山道である。サバの押し寿司を作り食べる習慣は,この途中の宿場町の随所にみられる。
ひと塩モノのサバがたどりついた先の京の料理人および家庭のご婦人方は,馬上で揺られ運ばれる間にちょうどよく塩のなじんだこれを酢で締め,若干甘めに仕上げた酢飯と合わせて押しをかけ,短期保存食とした。ただでさえ“サバの生き腐れ”と言われるほど鮮度の落ちやすいサバを,冷蔵器機のない時代,よくぞここまで生に近いかたちで食べられるところまで昇華したものだ(このへん,過日書いた「カルパッチョ」の根本原理と相通ずる原理があると思う。生で旨いかぎり生で食いたいという人間の欲求と,その発露たる工夫の産物だ)。
あらゆる面で合理的,かつ味覚のバランスが良くできており,そのための技術の粋が細部に凝らされている。京の実力。京の格式にいくらお高くとまられようが,これを食ったら「さすがミヤコじゃ・・・」と納得せざるをえない。
今でこそ日常的に周年食べられるようになっているが,本来は祝い事や祭りの時につくる“ハレ”の食であった。
かつて学生時代,京都の友人の実家に招いていただき,年の暮れ明けとお世話になったおり,そこの母上殿のこしらえたサバ寿司を口にして目を瞠った。九谷の大皿にどっしりびっしりと並んだそれは,
まず,美しかった。3㎝ほどにも分厚く切ったサバ寿司がしっかりまとまってピカピカ輝いている姿は,美しいだけでなく安心感を与えた。
そして次に,口元に運んでも,かみ砕いたときの空気が鼻腔に抜けても,臭みがない。生でもないが,生じゃないとも言えない。旨いが,旨過ぎない。郷土の香りがする。伝統の重さがある,かの母の佇まいそのままに優しさと力強さが同居している。という具合であった。
今でもその具象・心象風景が,味と共に,ありありと残映しているのである。背筋のピシッと通った立派な母上であったが,今はもうおられない。あのサバ寿司は,夢の中でしか,もう食えない。
作り方は教わっていて,自分でもしきりとやってみるのだが,やはり違う。旨くはあるのだけれど,やはり,このような伝統料理には人間の格みたいなものが出てしまう。かの母のそれには遠く及ばない。次元が違うのだと思う。
というわけで,やれ大味だ小味だとウルサイ私の「末期のサカナ」は,ここ20年来「サバ」なのであった。味もさることながら,特に私の中でのサバ棒寿司の存在が,魂の根幹奥深くまで食い込み息づいている。幼少の頃から食べた経験があるわけでもなく,まして京都に住んだこともない。ところがこうなってしまうのは不思議なことだ。
さて,振り返って今。
ここ境港に水揚げされる山陰のサバは,今でこそ,いくら大きくても1㎏いくかいかないか,というところであるが,かつて10年前には,大きいもので2㎏もあるようなサバも獲れていたという。今では考えられない,カツオと見まがうばかりのサイズである。味はいかばかりであったろうか。思いめぐらせば,つい遠い目になる。海は変わった。サカナも変わった。ヒトの生活が変わってしまったからだ。
地元で名を知られる廻船時代からの弁当「五左右衛門寿司」は,昔からこの形態かどうかは知らないが,今は山陰沖のサバを用いたまさに棒寿司で,旨いのである。が,地物とはいえ現在使用しているサバはせいぜい25~30㎝程度。境の昔日を想わせるべくもない。
現代のここ境港市中で旨いサバを存分に食いたくなったら,「ぶっこん亭」に行けばよい。旬の最盛期であれば刺身が味わえるし,シメサバは常備している。よくまあサバをこれだけ揃えられるものだと感心する。しかも全て地物だ。
なかなかに秀逸なのは酒後に注文する「サバ押し」で,これは即席の棒寿司である。即席であるが故に,塩加減も酢加減も浅く,刺身感覚の旨さがあり,いかにも毎日新鮮魚が水揚げ豊富な境港らしい仕上がりだ。寿司の歴史において紀州を起源とし西日本で発達した「なれ(熟れ)寿司」に対し,江戸日本橋の魚河岸で生まれた「握り寿司」の別名である,いわゆる「早なれ」もしくは「早ずし」とはこんなものではなかったか,とのイメージがよぎる。
京都のサバ寿司とは違って値段もお手頃で,スバヤク気取らずジワリと旨い。この点,若き店主の門脇誠君の料理に対する姿勢が表れているといってよい。入り口には営業中ではなく「合戦中」と大きな殴り筆の木札が掛かっている。彼は毎日素材と合戦しているのだ。されど料理はさりげない。このへんがニクイ。他のサカナ料理も気が利いており,とにかく私のような根っからの“サカナっ食い”にはありがたい店だ。
が,末期のサカナ,とは別のもの。
境港で日々旨いサカナを食いながら,件のサバ寿司を静かに回顧している。
そこにどう答えるか。
前回“忘我の味”,などということを書いていたら,その延長でこんなことに思い当たった。
ひとそれぞれいろいろあろうが,まあ,ここでは当然サカナが話しの対象となる。これを仮に“末期のサカナ”としよう。
これについて,私はこれまで,いつでもどこでも,即座に「サバです。特にサバ寿司です!」とキッパリ叫んでいたものだ。逝く前に,旨いサバ寿司をひとくち食って一瞬味わったのち静かに目を閉じたい。と思っていた。
旨いサカナを数えればキリがない。
獲れる時期,場所,サイズ,鮮度,そして調理法,食環境,等々が適切に融合すれば,それぞれに旨いし,或いは旨くすることができる。
しかし“末期のサカナ”となると,単なる旨いマズイだけでなく,むしろ個々人の内面的な世界と強くつながっているサカナ,あるいはそのような料理,ということになるのかもしれない。最近流行のソウルフードなどとは,また意味合いが違うのだが。
さばアレルギーの人には申し訳ないが,「サバ」のうまさ。これは今さら言い立てるまでもあるまい。
適切な手法で鮮度を維持し適切な処理さえ心得ておけば,その身肉は,およそ魚類界において最強クラスの旨味をもち,それはいかなる料理に仕立てても揺らぐことがない。負けないのである。
たとえばサカナのカレーを作るとき,マグロ,アジ,サバ,サンマ,その他白身のサカナいろいろと使ってみると,違いがよくわかる。香辛料に負けず,いくら煮込んでも歯ごたえも維持しつつ,噛み下した直後からグッと迫る旨味を固持しているのがサバだ。それだけに,“品のある味”とは言い難いが,まあ強くしっかりしているのである。多少鮮度が落ちている場合であっても,だいたい旨味が勝つ。そばつゆなどにグッとくるコクを出したいときに,サバ節を加えるのもこういうわけだ。
塩サバ,焼サバ,汁物,煮物,揚物,刺身にシメサバ,サラダにしてもよいし,オードブルにも,和・洋・中全てに化ける。我が国では塩や糠に漬けて保存食にもする。“鯖の水煮”はサカナ缶詰の代名詞たる存在だ。汎用性が広く,人間の魚食生活に古くから深く溶け込んでいる。その点,大衆性の強い青ザカナの一員でありながら,他の青ザカナとは歴史と実力が違う。
中でも,こと「サバ寿司」となると,別格だ。
関東のバッテラ,土佐の姿寿司,最近では若狭の焼きサバ寿司など,要は塩をあてたサバを酢でシメ,整形した酢飯に乗せて押しをかけた寿司は各地に存在し,余計な添加物さえ入っていなければそれぞれに旨いが,ここで言うのは京都で作る郷土食たる「サバの棒寿司」だ。
京都のアレは,日本の風土と文化伝統が生んだサバ料理の最高傑作ではないかと思う。
日本海は若狭湾の,脂の乗りすぎない肉厚の朝獲れサバを背割りにしてひと塩し,これをカマス袋に担いで京都まで運んだ。この道が言わずと知れた「サバ街道」だ。福井県の若狭小浜から南西に下って琵琶湖西岸に至り南下し,幾多の峠を越えて京都に至る,全長約72㎞の山道である。サバの押し寿司を作り食べる習慣は,この途中の宿場町の随所にみられる。
ひと塩モノのサバがたどりついた先の京の料理人および家庭のご婦人方は,馬上で揺られ運ばれる間にちょうどよく塩のなじんだこれを酢で締め,若干甘めに仕上げた酢飯と合わせて押しをかけ,短期保存食とした。ただでさえ“サバの生き腐れ”と言われるほど鮮度の落ちやすいサバを,冷蔵器機のない時代,よくぞここまで生に近いかたちで食べられるところまで昇華したものだ(このへん,過日書いた「カルパッチョ」の根本原理と相通ずる原理があると思う。生で旨いかぎり生で食いたいという人間の欲求と,その発露たる工夫の産物だ)。
あらゆる面で合理的,かつ味覚のバランスが良くできており,そのための技術の粋が細部に凝らされている。京の実力。京の格式にいくらお高くとまられようが,これを食ったら「さすがミヤコじゃ・・・」と納得せざるをえない。
今でこそ日常的に周年食べられるようになっているが,本来は祝い事や祭りの時につくる“ハレ”の食であった。
かつて学生時代,京都の友人の実家に招いていただき,年の暮れ明けとお世話になったおり,そこの母上殿のこしらえたサバ寿司を口にして目を瞠った。九谷の大皿にどっしりびっしりと並んだそれは,
まず,美しかった。3㎝ほどにも分厚く切ったサバ寿司がしっかりまとまってピカピカ輝いている姿は,美しいだけでなく安心感を与えた。
そして次に,口元に運んでも,かみ砕いたときの空気が鼻腔に抜けても,臭みがない。生でもないが,生じゃないとも言えない。旨いが,旨過ぎない。郷土の香りがする。伝統の重さがある,かの母の佇まいそのままに優しさと力強さが同居している。という具合であった。
今でもその具象・心象風景が,味と共に,ありありと残映しているのである。背筋のピシッと通った立派な母上であったが,今はもうおられない。あのサバ寿司は,夢の中でしか,もう食えない。
作り方は教わっていて,自分でもしきりとやってみるのだが,やはり違う。旨くはあるのだけれど,やはり,このような伝統料理には人間の格みたいなものが出てしまう。かの母のそれには遠く及ばない。次元が違うのだと思う。
というわけで,やれ大味だ小味だとウルサイ私の「末期のサカナ」は,ここ20年来「サバ」なのであった。味もさることながら,特に私の中でのサバ棒寿司の存在が,魂の根幹奥深くまで食い込み息づいている。幼少の頃から食べた経験があるわけでもなく,まして京都に住んだこともない。ところがこうなってしまうのは不思議なことだ。
さて,振り返って今。
ここ境港に水揚げされる山陰のサバは,今でこそ,いくら大きくても1㎏いくかいかないか,というところであるが,かつて10年前には,大きいもので2㎏もあるようなサバも獲れていたという。今では考えられない,カツオと見まがうばかりのサイズである。味はいかばかりであったろうか。思いめぐらせば,つい遠い目になる。海は変わった。サカナも変わった。ヒトの生活が変わってしまったからだ。
地元で名を知られる廻船時代からの弁当「五左右衛門寿司」は,昔からこの形態かどうかは知らないが,今は山陰沖のサバを用いたまさに棒寿司で,旨いのである。が,地物とはいえ現在使用しているサバはせいぜい25~30㎝程度。境の昔日を想わせるべくもない。
現代のここ境港市中で旨いサバを存分に食いたくなったら,「ぶっこん亭」に行けばよい。旬の最盛期であれば刺身が味わえるし,シメサバは常備している。よくまあサバをこれだけ揃えられるものだと感心する。しかも全て地物だ。
なかなかに秀逸なのは酒後に注文する「サバ押し」で,これは即席の棒寿司である。即席であるが故に,塩加減も酢加減も浅く,刺身感覚の旨さがあり,いかにも毎日新鮮魚が水揚げ豊富な境港らしい仕上がりだ。寿司の歴史において紀州を起源とし西日本で発達した「なれ(熟れ)寿司」に対し,江戸日本橋の魚河岸で生まれた「握り寿司」の別名である,いわゆる「早なれ」もしくは「早ずし」とはこんなものではなかったか,とのイメージがよぎる。
京都のサバ寿司とは違って値段もお手頃で,スバヤク気取らずジワリと旨い。この点,若き店主の門脇誠君の料理に対する姿勢が表れているといってよい。入り口には営業中ではなく「合戦中」と大きな殴り筆の木札が掛かっている。彼は毎日素材と合戦しているのだ。されど料理はさりげない。このへんがニクイ。他のサカナ料理も気が利いており,とにかく私のような根っからの“サカナっ食い”にはありがたい店だ。
が,末期のサカナ,とは別のもの。
境港で日々旨いサカナを食いながら,件のサバ寿司を静かに回顧している。
2007年07月03日
忘我の味「ノドクロ」
本当は釣りについても,水産業などについてもいろいろ書きたいことはあるのだが,相変わらず食い意地にまかせて“サカナっ食い”の話で恐縮です。
さて皆さん。
サカナに限らず,およそ食べ物の中で,食べたら“陶酔”してしまうもの。言葉を代えれば“忘我”してしまうもの。カンタンに言えば,“ウットリ”ないし“ボーッ”となっちゃうもの。そんな食べ物がこの世にどれだけあるでしょうか。
なにせ味の世界のことだから,人畜それぞれにいろいろあるかもしれない。現にネコ共が陶酔してやまないマタタビの風味は我々人間にはわからないし,ワインマニアの方が美辞麗句を述べつつ一杯の赤ワインに陶酔している有様を見ても,もっと素朴な物差ししか持たないがゆえにピンと来ないワタクシもいる。
やはり味の嗜好というものは,生物ごとの生理と,生い立ち,経験,それらを統括する感覚や精神,そんなものが総合されて形成されている。
とはいえ・・・,
これまでピンからキリまでいろんなものを口にしてきたが,私はここ山陰で,初めて我を忘れる“忘我の味”に出会ってしまった。今のところ,唯一無二であり,他の追随を許さない。そのサカナの名を「ノドクロ」という。
最近ではテレビの料理試合番組にも出場したせいか,けっこう名を知る人も増えた。標準和名を「アカムツ」といい,口の中および腹腔の内側が黒い皮膜で覆われているのでノドクロと呼ばれている。
水深200m前後の中深海の大陸棚に棲み,イカや小魚を食っている。底引き網や深場の刺し網,はえ縄などで漁獲されるが,漁獲量は少なく幻とまでは言えないまでも希少価値。値段も高い。
関東以南の太平洋から東シナ海,中部日本海までグルッと分布しており,それぞれの環境で質は違うが,太平洋や東シナ海よりも,まず日本海,特に島根県以北のものをもって最上とする。体型も違うし,脂の入り具合も断然違ってくるのである。
【 ノドクロ陶酔症 第一期症状 】
初めてノドクロを食ったのは,誰かの結婚式で友人と山陰に出かけた折,出雲駅にほど近い小料理屋で,店主に勧められるままに一尾を塩焼きにしてもらったのが最初であった。30㎝をちょっと出るくらいの大きなヤツで,店主がえらく神経を使って焼いていたのが印象的であった。
さて焼き上がり,それまではツマラン結婚式だったのなんのとやかましかった我々は,早速これを口にし,そして沈黙した。隣にいた獣医のやつが,「すごいな・・・」とだけつぶやいた。この獣医は,普段は雑な物も食うくせに,真剣になると本当の意味で味にはうるさい。旨味世界の身体的受容体およびそれを感受する精神的背景が広く,かつ深いということであろうと思う。ナマイキなことだ。
二人で夢中でたいらげ,驚いて見ている店主に向き直り,「こここ・これ,このアラ,お椀にお湯注いで吸い物にしてください!」と指さし叫んだが,店主は「もはいアンタやち,食べーとこあーませんがな」などと,出雲弁で静かにあきれられたのみであった。
微々たる残骸の,そのまたカスを前に,我々は酒を飲むのも忘れて暫くボーッとしていた。忘我の味は忘酒の味でもあることがわかった。もう一尾おかわりを注文すればよかったことだが,結婚式の後では既に財布の余裕は尽きていたのである。
【 ノドクロ陶酔症 第二期症状 】
その後数年がたち,はからずも境港に転勤となり,当時は隣町の米子にアパートを借りて住んでいた。近所の鮮魚直売所に赴くと,再びノドクロと遭遇した。25㎝ばかりのそれを,引っ越しの片づけもまだ終わらぬ家に買って帰り,塩をしてレンジの魚焼きグリルで焼いた。匂いも良い。期待に心が震えていた。
が,片面を七分がた焼き終わり,返すときに身がざっくりと崩れてしまった。それでもガンバって両面を焼き終えたときには,骨がすっかり露出し,グリルのトレイの上に“ほぐし身”がボトボトと散乱している惨状となった。これではたして両面焼いたと言えるのか。
トレイから拾い集めた身肉を食いつつ,心中複雑ながら,それでもやはり陶酔していった。やはり旨い。そして,ひと月に1回はノドクロを食べられるような生活をしよう,と心に誓った。
かたわら,ボロボロとなったノドクロの原因追及を始めた。
身肉が焼くほどに崩れてしまった可能性として,
①鮮度が低下していたので過熱によりもろくなった。
②反対に返すときの箸が食い込んで割れた。
③自重によってグリルの網目が食い込んで割れた。
などが考えられたが,観察する限り,原因は明らかに②と③である。しかし,およそ魚類界を見渡してみても,姿がこれほどしっかりしているくせに,こんなことになる魚は滅多にない。何がこうさせるのであろうか。
初めてノドクロを口にしたときにわかったことだが,このサカナは,単に脂が乗っているだけのサカナではない。通常のサカナは,脂が乗ってくると皮と肉の間に溜まっていき,皮沿い,もしくは筋膜や腱などのスジ沿いに,徐々に筋肉中に入りこんでくる。これを一般に“サシが入った”と言い,極まれば“霜降り”などとも言う。マグロの中トロや脂の乗ったイワシやサワラなどの切断した断面に目を近づけてよーく見れば,脂の入り方のルートがよくわかる。鯛やヒラメなどの白身でも若干乗りが薄いがほぼ同様である。
が,ノドクロの場合はちょっと違う。脂が乗り始めると,皮沿いだけでなく,同時に骨に接する中心部までサシが入るのだ。それともうひとつ特徴的なのは,脂と共に,大量の水分を筋肉中に蓄えている点だ。けして水っぽいというのではない。旨味を伴った水分である。“ジューシーな肉汁”,というやつだ。これが極めて多い。筋肉繊維自体は,タイ並にしっかりしているのだが,この独特の脂乗りと肉汁によって,噛みしめるほどにみずみずしい旨さが口中にしみ出すしくみとなっている。上手に焼いたノドクロの塩焼きを食ったとき,香ばしさと共に,大量の肉汁が口中にあふれかえるのは,そのせいだ。ただし,“上手に焼く”ということが前提であって,ここが難しい。
ここで比較すべく他魚を引き合いに出すと,北海道および東北地方には魚族脂肪番付上横綱級の「キンキ」がいる。根室を発祥とする炉端焼きで味わうと,これもまたむっちりしたコラーゲンといいますか,透明感のある濃厚な脂の乗りがスゴイ魚であるが,いかんせん,①肉のジューシーさが少ない,②肉質に北方のカサゴの仲間に特有のパラパラ感がある。種族の系譜の違いはぬぐえない。この魚はカサゴの仲間なのである。いくら脂が乗っていようとも,どうしても総合点でノドクロには及ばない。
話を戻す。
世間ではノドクロの刺身やタタキ,あるいは煮付けが最高と言うヒトもいるし,その後私も食う機会があり,それぞれに旨いものであったが,「脂でカリッと揚げたように焼けた皮の香味と共に,あふれかえる脂と肉汁の混合液を口中にからませ,その中に同居するコクのある肉を噛みしめ味わい飲み下す,複雑にして玄妙ナル旨さ」は,塩焼き以外では実現できない。世間に異論があろうとも,ノドクロの特性を100%引き出せるのは塩焼きだけなのだ,と断定したい。
とにかくその後,私は節約を重ね,月に1回はノドクロを吟味購入し,身崩れを防ぐため,塩して干したり,アルミホイルやフライパンに載せて焼いたりと,今思えば短絡的かつ稚拙な工夫を始めたのであった。
【ノドクロ陶酔症 第三期症状】
あれこれやってみた結果,やはりストレートに直火で焼く意外,ノドクロの本性味を引き出すことはできない,という結論に至った。
住んでいたプレハブ2階のベランダに板を敷き,20×40㎝の鋳物製炭火コンロを据え,ホームセンターでスチール棚のパーツを買い揃え,やぐらのようにネジで組み合わせて,串を打ったサカナの高さが多段階的に調整可能なプラントを作った。串はステンレス2㎜径の60㎝を数本買い求めた。これでノドクロ焼きの試行錯誤が始まったのである。
毎月のようにノドクロを購入し,炭火を熾し,塩加減,火力,高さ調整,等々を入念に工夫して2年が経った。最低計算で計24本,来客などあったときには更に多く,おそらく総計50本以上焼いたのではないか。これは料理屋であれば少ない数かも知れないが,数が少ない分,一回ごとの努力と反省には重さがあったように思う。
その結果得たノドクロの塩焼きに関する要諦,以下のとおり。
***************************
【ノドクロを焼く】
①ノドクロは,無理をしてでも25㎝以上の中型より大きいもの,中でも特に背が張りシッポの太いものを選び,肌身を傷つけないようウロコをとり,体の右側(背上・頭左に盛りつけたときの裏側)横に包丁を入れ,エラ・内臓を取り去る。
②水洗いしながら口から歯ブラシを入れて,腹腔の背骨に付着した血合いをこすりとる。
③体全体および腹腔の内部,口の中等の水分をよく拭き取り,体の両面の首の付け根から尻ビレにかけてナナメに,中骨にギリギリ到達しない程度に包丁目を入れる。
④手を少し湿らせて粗塩をつけ,口の中や腹腔の内部を含むカラダ全体に塩をあてる。塩加減は,押しつけた指をなめたときに,ちょっとだけ塩がきついのではないか,という程度。これは一般的な他のサカナより少し多めの塩加減。ここでは振り塩ではなく,全体に塩がゆきわたることを目的とするのでベタ塩とする。このまま最低30分置く。
⑤串を打つ。これを間違えると,ノドクロが焼けるに伴って身が崩れ,最悪の場合,身が脱落する。頭を手前,背を右に寝かせ,頭をグッと持ち上げて裏側の目の後方,エラ蓋から串を刺す(容易に串が入る場所がある)。表面に串が出ないようにそのまま尾のほうへ向けてナナメ下方へ串を進め(この時点で背側から見ると逆くノ字型になっている),次に尾を頭と反対側に強く折り曲げ,そのまま串を尾の手前に出す(この時点で,背側から見ると,S字型になっている)。留意すべきは,串がノドクロの背骨の棘をしっかり縫っていること。そのため,しっかりと曲げながら串を打つ必要がある。
更に,2本目の串を同じ手法で腹側に打つ。
⑥炭火を熾し,最高火力から少し落ち着くまで待つ。手をかざしたとき,すぐに耐えられなくなるような距離に串の高さを調節する。
⑦各ヒレに化粧塩を施し,体にもサッと振り塩をあて,火にかける。
⑧裏になる側(体の右側)から焼き初め,しばらくの後,汁が落ち始めたら,魚がかぶるくらいの船型をアルミホイルで作り,上にかぶせる。このことによって,身の厚いノドクロの全体に熱が回ると共に,したたり落ちた脂が煙となって魚体全体にまわり,風味を増す。
⑨全体の7割方火が通り,片面がこんがりキツネ色に仕上がったところで,火の高さを少々下げ,表(魚体の左側)に返し,再びアルミホイルをかぶせる。
(注 意)
表も裏も、焼きすぎればノドクロ特有のみずみずしさは失われ、まずくはないが単なるタイの塩焼きのような味になってしまう。この焼き加減の見極めが最重要ポイント。
⑩表も同様にキツネ色に仕上がったら,大皿に移し,串を回しながら素早く抜く。
⑪このまま即座に食べるが良い。更に,おろしワサビを添え,それを少しつけながら食べると目を瞠る旨さを知ることができる。醤油はかけてはいけない。
****************************
境港は,実は日本海で一番ノドクロが安い土地だ。そういう値段しかつかないところと言ってもよいし,庶民重視の薄利多売の土地柄と言ってもよい。お隣の島根や兵庫でも,新潟や富山でも,値段を見たらビックリする。
魚種が豊富で比較的サカナの安い日本海の中にあって安さ一番ということは,全国一安いということだ。この僥倖に浴している我が身を幸せに思う。
これからもワタクシは,最高の中の更に最高を求めてノドクロを焼き続けるであろう。
ひとたびこの陶酔症に罹患すれば、潜伏し日和見発症するウイルスのごとく、その味は骨の髄にインプットされてしまう。
しばらく食べていないと,車の運転中でも,この味と香りを想い出しただけでボーッとしてしまいそうになるが,これは危険だ。
さて皆さん。
サカナに限らず,およそ食べ物の中で,食べたら“陶酔”してしまうもの。言葉を代えれば“忘我”してしまうもの。カンタンに言えば,“ウットリ”ないし“ボーッ”となっちゃうもの。そんな食べ物がこの世にどれだけあるでしょうか。
なにせ味の世界のことだから,人畜それぞれにいろいろあるかもしれない。現にネコ共が陶酔してやまないマタタビの風味は我々人間にはわからないし,ワインマニアの方が美辞麗句を述べつつ一杯の赤ワインに陶酔している有様を見ても,もっと素朴な物差ししか持たないがゆえにピンと来ないワタクシもいる。
やはり味の嗜好というものは,生物ごとの生理と,生い立ち,経験,それらを統括する感覚や精神,そんなものが総合されて形成されている。
とはいえ・・・,
これまでピンからキリまでいろんなものを口にしてきたが,私はここ山陰で,初めて我を忘れる“忘我の味”に出会ってしまった。今のところ,唯一無二であり,他の追随を許さない。そのサカナの名を「ノドクロ」という。
最近ではテレビの料理試合番組にも出場したせいか,けっこう名を知る人も増えた。標準和名を「アカムツ」といい,口の中および腹腔の内側が黒い皮膜で覆われているのでノドクロと呼ばれている。
水深200m前後の中深海の大陸棚に棲み,イカや小魚を食っている。底引き網や深場の刺し網,はえ縄などで漁獲されるが,漁獲量は少なく幻とまでは言えないまでも希少価値。値段も高い。
関東以南の太平洋から東シナ海,中部日本海までグルッと分布しており,それぞれの環境で質は違うが,太平洋や東シナ海よりも,まず日本海,特に島根県以北のものをもって最上とする。体型も違うし,脂の入り具合も断然違ってくるのである。
【 ノドクロ陶酔症 第一期症状 】
初めてノドクロを食ったのは,誰かの結婚式で友人と山陰に出かけた折,出雲駅にほど近い小料理屋で,店主に勧められるままに一尾を塩焼きにしてもらったのが最初であった。30㎝をちょっと出るくらいの大きなヤツで,店主がえらく神経を使って焼いていたのが印象的であった。
さて焼き上がり,それまではツマラン結婚式だったのなんのとやかましかった我々は,早速これを口にし,そして沈黙した。隣にいた獣医のやつが,「すごいな・・・」とだけつぶやいた。この獣医は,普段は雑な物も食うくせに,真剣になると本当の意味で味にはうるさい。旨味世界の身体的受容体およびそれを感受する精神的背景が広く,かつ深いということであろうと思う。ナマイキなことだ。
二人で夢中でたいらげ,驚いて見ている店主に向き直り,「こここ・これ,このアラ,お椀にお湯注いで吸い物にしてください!」と指さし叫んだが,店主は「もはいアンタやち,食べーとこあーませんがな」などと,出雲弁で静かにあきれられたのみであった。
微々たる残骸の,そのまたカスを前に,我々は酒を飲むのも忘れて暫くボーッとしていた。忘我の味は忘酒の味でもあることがわかった。もう一尾おかわりを注文すればよかったことだが,結婚式の後では既に財布の余裕は尽きていたのである。
【 ノドクロ陶酔症 第二期症状 】
その後数年がたち,はからずも境港に転勤となり,当時は隣町の米子にアパートを借りて住んでいた。近所の鮮魚直売所に赴くと,再びノドクロと遭遇した。25㎝ばかりのそれを,引っ越しの片づけもまだ終わらぬ家に買って帰り,塩をしてレンジの魚焼きグリルで焼いた。匂いも良い。期待に心が震えていた。
が,片面を七分がた焼き終わり,返すときに身がざっくりと崩れてしまった。それでもガンバって両面を焼き終えたときには,骨がすっかり露出し,グリルのトレイの上に“ほぐし身”がボトボトと散乱している惨状となった。これではたして両面焼いたと言えるのか。
トレイから拾い集めた身肉を食いつつ,心中複雑ながら,それでもやはり陶酔していった。やはり旨い。そして,ひと月に1回はノドクロを食べられるような生活をしよう,と心に誓った。
かたわら,ボロボロとなったノドクロの原因追及を始めた。
身肉が焼くほどに崩れてしまった可能性として,
①鮮度が低下していたので過熱によりもろくなった。
②反対に返すときの箸が食い込んで割れた。
③自重によってグリルの網目が食い込んで割れた。
などが考えられたが,観察する限り,原因は明らかに②と③である。しかし,およそ魚類界を見渡してみても,姿がこれほどしっかりしているくせに,こんなことになる魚は滅多にない。何がこうさせるのであろうか。
初めてノドクロを口にしたときにわかったことだが,このサカナは,単に脂が乗っているだけのサカナではない。通常のサカナは,脂が乗ってくると皮と肉の間に溜まっていき,皮沿い,もしくは筋膜や腱などのスジ沿いに,徐々に筋肉中に入りこんでくる。これを一般に“サシが入った”と言い,極まれば“霜降り”などとも言う。マグロの中トロや脂の乗ったイワシやサワラなどの切断した断面に目を近づけてよーく見れば,脂の入り方のルートがよくわかる。鯛やヒラメなどの白身でも若干乗りが薄いがほぼ同様である。
が,ノドクロの場合はちょっと違う。脂が乗り始めると,皮沿いだけでなく,同時に骨に接する中心部までサシが入るのだ。それともうひとつ特徴的なのは,脂と共に,大量の水分を筋肉中に蓄えている点だ。けして水っぽいというのではない。旨味を伴った水分である。“ジューシーな肉汁”,というやつだ。これが極めて多い。筋肉繊維自体は,タイ並にしっかりしているのだが,この独特の脂乗りと肉汁によって,噛みしめるほどにみずみずしい旨さが口中にしみ出すしくみとなっている。上手に焼いたノドクロの塩焼きを食ったとき,香ばしさと共に,大量の肉汁が口中にあふれかえるのは,そのせいだ。ただし,“上手に焼く”ということが前提であって,ここが難しい。
ここで比較すべく他魚を引き合いに出すと,北海道および東北地方には魚族脂肪番付上横綱級の「キンキ」がいる。根室を発祥とする炉端焼きで味わうと,これもまたむっちりしたコラーゲンといいますか,透明感のある濃厚な脂の乗りがスゴイ魚であるが,いかんせん,①肉のジューシーさが少ない,②肉質に北方のカサゴの仲間に特有のパラパラ感がある。種族の系譜の違いはぬぐえない。この魚はカサゴの仲間なのである。いくら脂が乗っていようとも,どうしても総合点でノドクロには及ばない。
話を戻す。
世間ではノドクロの刺身やタタキ,あるいは煮付けが最高と言うヒトもいるし,その後私も食う機会があり,それぞれに旨いものであったが,「脂でカリッと揚げたように焼けた皮の香味と共に,あふれかえる脂と肉汁の混合液を口中にからませ,その中に同居するコクのある肉を噛みしめ味わい飲み下す,複雑にして玄妙ナル旨さ」は,塩焼き以外では実現できない。世間に異論があろうとも,ノドクロの特性を100%引き出せるのは塩焼きだけなのだ,と断定したい。
とにかくその後,私は節約を重ね,月に1回はノドクロを吟味購入し,身崩れを防ぐため,塩して干したり,アルミホイルやフライパンに載せて焼いたりと,今思えば短絡的かつ稚拙な工夫を始めたのであった。
【ノドクロ陶酔症 第三期症状】
あれこれやってみた結果,やはりストレートに直火で焼く意外,ノドクロの本性味を引き出すことはできない,という結論に至った。
住んでいたプレハブ2階のベランダに板を敷き,20×40㎝の鋳物製炭火コンロを据え,ホームセンターでスチール棚のパーツを買い揃え,やぐらのようにネジで組み合わせて,串を打ったサカナの高さが多段階的に調整可能なプラントを作った。串はステンレス2㎜径の60㎝を数本買い求めた。これでノドクロ焼きの試行錯誤が始まったのである。
毎月のようにノドクロを購入し,炭火を熾し,塩加減,火力,高さ調整,等々を入念に工夫して2年が経った。最低計算で計24本,来客などあったときには更に多く,おそらく総計50本以上焼いたのではないか。これは料理屋であれば少ない数かも知れないが,数が少ない分,一回ごとの努力と反省には重さがあったように思う。
その結果得たノドクロの塩焼きに関する要諦,以下のとおり。
***************************
【ノドクロを焼く】
①ノドクロは,無理をしてでも25㎝以上の中型より大きいもの,中でも特に背が張りシッポの太いものを選び,肌身を傷つけないようウロコをとり,体の右側(背上・頭左に盛りつけたときの裏側)横に包丁を入れ,エラ・内臓を取り去る。
②水洗いしながら口から歯ブラシを入れて,腹腔の背骨に付着した血合いをこすりとる。
③体全体および腹腔の内部,口の中等の水分をよく拭き取り,体の両面の首の付け根から尻ビレにかけてナナメに,中骨にギリギリ到達しない程度に包丁目を入れる。
④手を少し湿らせて粗塩をつけ,口の中や腹腔の内部を含むカラダ全体に塩をあてる。塩加減は,押しつけた指をなめたときに,ちょっとだけ塩がきついのではないか,という程度。これは一般的な他のサカナより少し多めの塩加減。ここでは振り塩ではなく,全体に塩がゆきわたることを目的とするのでベタ塩とする。このまま最低30分置く。
⑤串を打つ。これを間違えると,ノドクロが焼けるに伴って身が崩れ,最悪の場合,身が脱落する。頭を手前,背を右に寝かせ,頭をグッと持ち上げて裏側の目の後方,エラ蓋から串を刺す(容易に串が入る場所がある)。表面に串が出ないようにそのまま尾のほうへ向けてナナメ下方へ串を進め(この時点で背側から見ると逆くノ字型になっている),次に尾を頭と反対側に強く折り曲げ,そのまま串を尾の手前に出す(この時点で,背側から見ると,S字型になっている)。留意すべきは,串がノドクロの背骨の棘をしっかり縫っていること。そのため,しっかりと曲げながら串を打つ必要がある。
更に,2本目の串を同じ手法で腹側に打つ。
⑥炭火を熾し,最高火力から少し落ち着くまで待つ。手をかざしたとき,すぐに耐えられなくなるような距離に串の高さを調節する。
⑦各ヒレに化粧塩を施し,体にもサッと振り塩をあて,火にかける。
⑧裏になる側(体の右側)から焼き初め,しばらくの後,汁が落ち始めたら,魚がかぶるくらいの船型をアルミホイルで作り,上にかぶせる。このことによって,身の厚いノドクロの全体に熱が回ると共に,したたり落ちた脂が煙となって魚体全体にまわり,風味を増す。
⑨全体の7割方火が通り,片面がこんがりキツネ色に仕上がったところで,火の高さを少々下げ,表(魚体の左側)に返し,再びアルミホイルをかぶせる。
(注 意)
表も裏も、焼きすぎればノドクロ特有のみずみずしさは失われ、まずくはないが単なるタイの塩焼きのような味になってしまう。この焼き加減の見極めが最重要ポイント。
⑩表も同様にキツネ色に仕上がったら,大皿に移し,串を回しながら素早く抜く。
⑪このまま即座に食べるが良い。更に,おろしワサビを添え,それを少しつけながら食べると目を瞠る旨さを知ることができる。醤油はかけてはいけない。
****************************
境港は,実は日本海で一番ノドクロが安い土地だ。そういう値段しかつかないところと言ってもよいし,庶民重視の薄利多売の土地柄と言ってもよい。お隣の島根や兵庫でも,新潟や富山でも,値段を見たらビックリする。
魚種が豊富で比較的サカナの安い日本海の中にあって安さ一番ということは,全国一安いということだ。この僥倖に浴している我が身を幸せに思う。
これからもワタクシは,最高の中の更に最高を求めてノドクロを焼き続けるであろう。
ひとたびこの陶酔症に罹患すれば、潜伏し日和見発症するウイルスのごとく、その味は骨の髄にインプットされてしまう。
しばらく食べていないと,車の運転中でも,この味と香りを想い出しただけでボーッとしてしまいそうになるが,これは危険だ。
2007年07月01日
「カルパッチョ」について、ひとこと
たいへんご無沙汰しております。
つまらないことを言うようですが,,,
ここ数年来,都市部を中心に,店内にジャズが流れているようなナンチャッテハイカラ居酒屋,或いはあくまで自称創作料理屋などのいたるところに「カルパッチョ」なるメニューが導入され,最近は釣り人までもパッチョパッチョとかまびすしい。マグロや鮭,タイやヒラメなど,多様化をみせている。このことが,悪いけれどちょいと神経に障る。最近では,その名を聞くだけでもナンダカ腹が立つようになってしまっていけない。条件反射か。
というのも,これだけ普及している「カルパッチョ」であるが,店だろうが誰かが作ってくださるものだろうが,私はマトモなソレに一度も出会ったことがないからだ。具体的かつ断定的に言わせてもらえれば,世間で氾濫しているソレは,単なる“薄切り刺身と野菜のサラダ”である。ソレのソレたる最重要ポイントがボッカリ抜けてしまっているのである。ここを申し上げたい。
では,カルパッチョのソレたるゆえんは何か。
①塩,②黒コショウ,③柑橘汁,④オリーブ油,以上。これが構成要素。
こう書くと,ちゃんと全部入ってるじゃないですかっ,ウチのも! とおっしゃる方もおられようが,順序が違う。合わせればいいというものではない。同じ材料を用いても,順序と手法が異なれば,味としては違うものとなるは料理の理。やりかたが変われば“似て非なるもの”というのだ。
カルパッチョは言うまでもなく,元来,新鮮な畜肉を生で食べることを目的とし,これがイタリア南部を主産地とするオリーブ油および柑橘類と出会い,更に地中海の魚にも波及して定着したと推せられる。
しかし,現代でこそ,新鮮な肉や魚の入手が常識化しているが,その昔,どうであったろうか。まず,鮮度維持に必要な,冷やすための氷がふんだんにあるワケがない。かといって肉にしても魚にしても,屠殺ないし漁獲してから長期間常温で放置するわけにもいかなかったであろう。雑菌が繁殖する条件,すなわち①適度な温度,②水分,③豊富な栄養,が揃えば肉は腐敗へと進む。まして,カルパッチョの必須構成要素である柑橘類の地理的分布は温帯~亜熱帯域であるから,雑菌にとってはより快適なのである。そこで,2つの選択肢が生ずる。新鮮な肉や魚を入手したら,①速やかに食べてしまう,②保存するための処理を施す。
ところで,冷蔵庫が当たり前となった現代の我々は,たとえば肉の表面が菌に冒されて腐敗臭がしたら,可食部全てが腐敗していると錯覚してはいないだろうか。
実は,新鮮な肉の大きな固まりがあったとして,表面が痛んできたとしても,その内部は大丈夫,なのである。危ない部分と安全な部分をごっちゃにしてはもったいない。また魚であれば,大きな魚,たとえばマグロやクジラなどでも同じようなことが言える。丸ごとの小さな魚でも,新鮮なうちにウロコや内臓,ヒレなどの雑菌が付着しやすい部位を除いておけば,大型の生物ほど比較的常温でも長持ちするのである。初期の段階であれば,表面が臭くなったら洗えばよろしい。
そもそも熱帯地方の市場で,常温で魚がゴロゴロ並べられていてもちゃんと食べられるのはなぜか?これも同じ原理で,表面には菌がついていても,「生体」の内部は無菌状態だからだ。死んだ魚や牛でも,初めのうちは内部たる筋肉細胞は生きている。時間がたてば細胞中の分解酵素が作用して細胞が崩壊し,旨みが増し,それを越えれば外側から次第に菌が侵入し繁殖する場所となる。
ちなみに畜肉やマグロを「熟成する」といって固まりのまま保存しておくのは,この自己分解(=旨み成分の増加)と腐敗のきわどいところを見極める技術である。
さて。
とはいえ表面が雑菌に冒されることには変わりはない。そこで保存する手段として,当時氷が少ない時代に使用されるのがまず「塩」であろう。塩は最も入手しやすく生命と関わりの深い最初の調味料であり,味付けのみならず,その強い浸透圧によって肉の細胞から水分を奪うことができる。更に,付着した雑菌の細胞からも水分を奪ってしまう。もちろん海水中には塩分を好む菌もいるのであるが,陸上であれば,塩は,まず,先述した,菌の発生条件の最重要条件である「水分」を奪う力を持っているのである。
肉が腐敗しやすい温・熱帯の地方にあった,冷蔵手段もなく,それでもなお“生で食いたい”という欲求,おそらくそれがカルパッチョを生んだ原動力である。そこでは塩が不可欠のはずだ。しかも,味付け程度ではなく,雑菌が繁殖できない強い塩加減が求められたはずだ。
そして,もうひとつ,安全な生食を実現したのが,レモンやライムをはじめとする柑橘類の植生である。強度な酸味が雑菌の繁殖を阻害して保存性と安全性を高めることは,我が国のシメサバやすし飯でも見るとおり,言うまでもない。固まりに塩をして表面の腐敗を防ぎ,薄く切って露出した肉の断面には柑橘の酸で殺菌する。
更に更に,これほどまでに防菌・殺菌された肉片にオリーブ油をかけて空気を遮断して万全を期している。
これが,カルパッチョという,極めて合理的な生食料理の真髄ではないだろうか。
これと全く同様の生魚料理が南米にあり「セビッチェ」という。ちがうのは,魚にあてる塩分がカルパッチョよりきついことと,柑橘汁を,よりたっぷりかけること。また,粒コショウなどを使う点だ。これもまた,イタリアよりも赤道に近い熱帯地方に叶った流用といえよう。
というわけで,以上の条件を満たした「カルパッチョ」の作り方を紹介しよう。
*******************************
【カルパッチョ】
①肉ないし魚は,小口に切りやすい大きさの固まり(魚であれば“サク”程度の大きさ)のまま,全体にきつく塩をまぶし,皿に載せておく。
②タマネギをごく薄くスライスして水にさらし,パリッとしたところで水分をよく切っておく。
③放置する時間は固まりの大きさによって異なるが,更に肉の水分が流れ出る頃を見計らい,表面をなでるように流水で塩をサッと流し,水分を拭いておく。
④薄くそぎ切りにし,タマネギをまんべんなく敷いた皿の上に,密に並べていく。肉の両端は塩辛いので特に薄く切ること。
⑤皿いっぱいに並べ終わったら,柑橘汁をまんべんなくたらしかける。次いで,粗挽き黒コショウをまんべんなく薄くふりかける。
⑥最後にバージンオリーブ油を,細くまんべんなくかけ回す。
⑦これで食べられるが,現代であれば,このまま皿ごとよく冷やして食べるのがオツ。
******************************
「カルパッチョ」の要諦は次のとおり
●肉ないし魚には,切りやすく整形した固まりのままシッカリと塩をあてること。
●薄く切ってちょうどよくなるよう,寝かせる時間を調節すること。
●スライスタマネギの上に薄切りした身を並べ,「柑橘汁→香辛料→オリーブ油」の順に細くまんべんなくふりかけること(ドバッとかけたり,この順序を変えたりしてはいけない。塩・酸・香辛料・オリーブ油のバランスが重要なのであり,また,順序を違えて先に油をかけたりすれば柑橘汁や香辛料の効能が損なわれる)。
******************************
我が国や外国の郷土料理,特に古い歴史を持つ料理を再現するとき,ぜひとも,その地域の地理や環境に想いをはせていただきたい。そして更に言えば,時代をさかのぼり,その土地でその料理が生まれた当時の背景を考えてもらいたい。現代に比べて,何があって,何がなかったのか。そしてどのようにしていたのか。そこに料理の構成要素があるからだ。
料理にせよ文化にせよ,原点にさかのぼると,おのずから“ホンモノ”が見えてくる。料理であればホンモノにより近い旨さを味わうことができる。ホントウのホンモノに出会うには現地に赴くしかないのであるが,その現地にさえ,ホントウのホンモノが消えつつある昨今だ。ぜひとも想像力をたくましくし,それぞれのご家庭に,ホンモノにを再現して伝えてほしいと願う。
つまらないことを言うようですが,,,
ここ数年来,都市部を中心に,店内にジャズが流れているようなナンチャッテハイカラ居酒屋,或いはあくまで自称創作料理屋などのいたるところに「カルパッチョ」なるメニューが導入され,最近は釣り人までもパッチョパッチョとかまびすしい。マグロや鮭,タイやヒラメなど,多様化をみせている。このことが,悪いけれどちょいと神経に障る。最近では,その名を聞くだけでもナンダカ腹が立つようになってしまっていけない。条件反射か。
というのも,これだけ普及している「カルパッチョ」であるが,店だろうが誰かが作ってくださるものだろうが,私はマトモなソレに一度も出会ったことがないからだ。具体的かつ断定的に言わせてもらえれば,世間で氾濫しているソレは,単なる“薄切り刺身と野菜のサラダ”である。ソレのソレたる最重要ポイントがボッカリ抜けてしまっているのである。ここを申し上げたい。
では,カルパッチョのソレたるゆえんは何か。
①塩,②黒コショウ,③柑橘汁,④オリーブ油,以上。これが構成要素。
こう書くと,ちゃんと全部入ってるじゃないですかっ,ウチのも! とおっしゃる方もおられようが,順序が違う。合わせればいいというものではない。同じ材料を用いても,順序と手法が異なれば,味としては違うものとなるは料理の理。やりかたが変われば“似て非なるもの”というのだ。
カルパッチョは言うまでもなく,元来,新鮮な畜肉を生で食べることを目的とし,これがイタリア南部を主産地とするオリーブ油および柑橘類と出会い,更に地中海の魚にも波及して定着したと推せられる。
しかし,現代でこそ,新鮮な肉や魚の入手が常識化しているが,その昔,どうであったろうか。まず,鮮度維持に必要な,冷やすための氷がふんだんにあるワケがない。かといって肉にしても魚にしても,屠殺ないし漁獲してから長期間常温で放置するわけにもいかなかったであろう。雑菌が繁殖する条件,すなわち①適度な温度,②水分,③豊富な栄養,が揃えば肉は腐敗へと進む。まして,カルパッチョの必須構成要素である柑橘類の地理的分布は温帯~亜熱帯域であるから,雑菌にとってはより快適なのである。そこで,2つの選択肢が生ずる。新鮮な肉や魚を入手したら,①速やかに食べてしまう,②保存するための処理を施す。
ところで,冷蔵庫が当たり前となった現代の我々は,たとえば肉の表面が菌に冒されて腐敗臭がしたら,可食部全てが腐敗していると錯覚してはいないだろうか。
実は,新鮮な肉の大きな固まりがあったとして,表面が痛んできたとしても,その内部は大丈夫,なのである。危ない部分と安全な部分をごっちゃにしてはもったいない。また魚であれば,大きな魚,たとえばマグロやクジラなどでも同じようなことが言える。丸ごとの小さな魚でも,新鮮なうちにウロコや内臓,ヒレなどの雑菌が付着しやすい部位を除いておけば,大型の生物ほど比較的常温でも長持ちするのである。初期の段階であれば,表面が臭くなったら洗えばよろしい。
そもそも熱帯地方の市場で,常温で魚がゴロゴロ並べられていてもちゃんと食べられるのはなぜか?これも同じ原理で,表面には菌がついていても,「生体」の内部は無菌状態だからだ。死んだ魚や牛でも,初めのうちは内部たる筋肉細胞は生きている。時間がたてば細胞中の分解酵素が作用して細胞が崩壊し,旨みが増し,それを越えれば外側から次第に菌が侵入し繁殖する場所となる。
ちなみに畜肉やマグロを「熟成する」といって固まりのまま保存しておくのは,この自己分解(=旨み成分の増加)と腐敗のきわどいところを見極める技術である。
さて。
とはいえ表面が雑菌に冒されることには変わりはない。そこで保存する手段として,当時氷が少ない時代に使用されるのがまず「塩」であろう。塩は最も入手しやすく生命と関わりの深い最初の調味料であり,味付けのみならず,その強い浸透圧によって肉の細胞から水分を奪うことができる。更に,付着した雑菌の細胞からも水分を奪ってしまう。もちろん海水中には塩分を好む菌もいるのであるが,陸上であれば,塩は,まず,先述した,菌の発生条件の最重要条件である「水分」を奪う力を持っているのである。
肉が腐敗しやすい温・熱帯の地方にあった,冷蔵手段もなく,それでもなお“生で食いたい”という欲求,おそらくそれがカルパッチョを生んだ原動力である。そこでは塩が不可欠のはずだ。しかも,味付け程度ではなく,雑菌が繁殖できない強い塩加減が求められたはずだ。
そして,もうひとつ,安全な生食を実現したのが,レモンやライムをはじめとする柑橘類の植生である。強度な酸味が雑菌の繁殖を阻害して保存性と安全性を高めることは,我が国のシメサバやすし飯でも見るとおり,言うまでもない。固まりに塩をして表面の腐敗を防ぎ,薄く切って露出した肉の断面には柑橘の酸で殺菌する。
更に更に,これほどまでに防菌・殺菌された肉片にオリーブ油をかけて空気を遮断して万全を期している。
これが,カルパッチョという,極めて合理的な生食料理の真髄ではないだろうか。
これと全く同様の生魚料理が南米にあり「セビッチェ」という。ちがうのは,魚にあてる塩分がカルパッチョよりきついことと,柑橘汁を,よりたっぷりかけること。また,粒コショウなどを使う点だ。これもまた,イタリアよりも赤道に近い熱帯地方に叶った流用といえよう。
というわけで,以上の条件を満たした「カルパッチョ」の作り方を紹介しよう。
*******************************
【カルパッチョ】
①肉ないし魚は,小口に切りやすい大きさの固まり(魚であれば“サク”程度の大きさ)のまま,全体にきつく塩をまぶし,皿に載せておく。
②タマネギをごく薄くスライスして水にさらし,パリッとしたところで水分をよく切っておく。
③放置する時間は固まりの大きさによって異なるが,更に肉の水分が流れ出る頃を見計らい,表面をなでるように流水で塩をサッと流し,水分を拭いておく。
④薄くそぎ切りにし,タマネギをまんべんなく敷いた皿の上に,密に並べていく。肉の両端は塩辛いので特に薄く切ること。
⑤皿いっぱいに並べ終わったら,柑橘汁をまんべんなくたらしかける。次いで,粗挽き黒コショウをまんべんなく薄くふりかける。
⑥最後にバージンオリーブ油を,細くまんべんなくかけ回す。
⑦これで食べられるが,現代であれば,このまま皿ごとよく冷やして食べるのがオツ。
******************************
「カルパッチョ」の要諦は次のとおり
●肉ないし魚には,切りやすく整形した固まりのままシッカリと塩をあてること。
●薄く切ってちょうどよくなるよう,寝かせる時間を調節すること。
●スライスタマネギの上に薄切りした身を並べ,「柑橘汁→香辛料→オリーブ油」の順に細くまんべんなくふりかけること(ドバッとかけたり,この順序を変えたりしてはいけない。塩・酸・香辛料・オリーブ油のバランスが重要なのであり,また,順序を違えて先に油をかけたりすれば柑橘汁や香辛料の効能が損なわれる)。
******************************
我が国や外国の郷土料理,特に古い歴史を持つ料理を再現するとき,ぜひとも,その地域の地理や環境に想いをはせていただきたい。そして更に言えば,時代をさかのぼり,その土地でその料理が生まれた当時の背景を考えてもらいたい。現代に比べて,何があって,何がなかったのか。そしてどのようにしていたのか。そこに料理の構成要素があるからだ。
料理にせよ文化にせよ,原点にさかのぼると,おのずから“ホンモノ”が見えてくる。料理であればホンモノにより近い旨さを味わうことができる。ホントウのホンモノに出会うには現地に赴くしかないのであるが,その現地にさえ,ホントウのホンモノが消えつつある昨今だ。ぜひとも想像力をたくましくし,それぞれのご家庭に,ホンモノにを再現して伝えてほしいと願う。