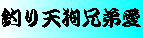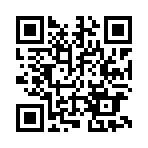2007年05月26日
スズキの臭味
このところ雨も少なく潮加減もあってか、夕方から夜にかけて濁りがきつい。
1ヶ月半も釣れ続いた“餌床付き(潮付き)”のメバルも、連日の強い南風に吹かれてイカナゴの群と共にどこかへ消えた。これからは、ほかの餌を求めてそれぞれに回遊、あるいは居残りと分かれていく。彼らが落ち着くまで、ひとまずここらで小休止か。
昨日は久しぶりの雨が降り、それでも少しは残っとらんかいなと思い、ちょいと行ってみた。ベイトは散漫なシラスの群れに変わり、小アジが散発的に群れ、雨、風、濁り、餌、とくれば、もうセイゴ・スズキの独壇場である。背中を出して餌を追い回すお祭り野郎もいた。これではメバルがいたとしても迷惑顔をするだけである。
早々に撤収、とした矢先、回収目前で65㎝が掛かってしまった。
残念なことに、スズキはここまで大きくなってしまうと食っても釣ってもつまらない。やはりスズキは、産卵前と後を除いた時期、50㎝前後の、背・腹の凛と張った勇ましいげなヤツなら良いのであって、今回釣れたようなのは本来ならばお帰り願いたいところであったが、傷がついてしまえばやむなし。
というわけで、締めて持ち帰った。
大きなスズキは、どうやって釣ろうが、どうやって食おうが、引きも食味も鈍重である。全調子に近いメバル竿にライン3ポンドだから獲るまでに時間はかかるが、重量感だけで面白くはないし、身がゆるく大味だ。どちらも総じて“のっそり”している。
世間では、90㎝のスズキ釣りました!などと釣り雑誌に見ることがあるが、釣ったあと、皆さんはどう対処しておられるのであろうか。
もうひとつスズキは問題を抱えている。大きくなるほどに、特有の「青臭さ」が強くなるのだ。これは、サカナ全般の、いわゆる“生臭み”とは別の臭さである。
スズキに近い仲間に淡水のブラックバスがいるが、やはり共通した臭さをもっている。これまた親戚のヒラスズキではそのような臭味は薄いようであるが、もし、あの臭味が淡水と関係があるのであれば(たとえば河川水に入るときの浸透圧調整や防護機能など)、河口産ののヒラスズキを一度食ってみたいところ。
投げやりに書いているようであるが、けしてスズキそのものを嫌っているわけではない。長崎や神戸では、急流でイワシを追いかける時期を狙って出かけたし、実は、水の清澄良質な湖沼を探しては、食いたくなるとブラックバスを釣りに通った。銀山湖のバスは特に風味がよい。
しかし、いかなる事情にせよ、あの青臭みをそのままにはできまい。
そこをどうするか、というお話。
***************************************
十数年前、長崎でブラックバスに手を染め始めた頃、友人が買ってきたBeナントカという物欲促進系アウトドア雑誌に、「ブラックバスを食べてみよう!」という記事が出たことがある。
その後、ブラックの日本産在来水棲生物に対する食害の問題が取り沙汰され、これはゲームフィッシャーと漁業者、研究・行政を交えての熱い論争にまで発展したが、そのときに水産庁やいくつかの県や漁協が促進PRしたのが「キャッチ&イート」であって、まあ、この雑誌の記事は先駆的であったとも言えよう。
さて、それによると「皮に臭味があるので、三枚におろして皮を必ずはがし、ムニエルとかフライとかに仕立てれば、食べられますよ」といった内容であったと思う。
で、早速やってみた。
実に腰のないサラリとした肉質で、若干の泥臭さを伴う浅い味の単なる洋食であって、あれほど果敢な魚食性のサカナが、これっぱかりのものかとガッカリしたものだ。それ以来、しばらくバス釣りからは遠ざかるのである。
それから数年。
銀山湖に仲間でキャンプに行き、私は素潜りでコイを突き、友人は散ってバス釣りだ。そして夕方、友人は35㎝内外のバスを数尾釣って戻った。
数尾のコイは、洗いにしてワサビ醤油と酢味噌として、水が良いせいか、すばらしかった。
一方、ブラックはどうしたかというと、今さらフライもムニエルもつまらんということで、ひとつは皮をひいてコイと同様に洗いとし、残り数本を、皮の臭味を知っていた私は、とりあえず基本に則り、臭味をとる意味で粗塩で擦ったのち水洗いし、塩を振り直し、焚き火にかざして焼いてみたのである。
これが、たいしたものであった。
例の雑誌には、皮がクサイからとる、と書いてあって、たしかに嗅いでみれば臭かったし、かといって皮をはいでしまったブラックバスは、味わうに値せぬ味とアタマから信じ込んでいた。
しかしこれを食ったとき、それまでの自分の固定観念と精進のなさを悔やんだことだ。
旨い。 皮が、旨い。 皮と一体となった身が化けている。
数人で、あっというまにむさぼり食ってしまった。
かつて頼りなかった身肉は、焼けた皮と合わさることによって、やさしい甘味と野性味、そして十分納得のいく旨味を獲得した。
それからのちである。私が“食える水に棲む”ブラックバスを追いかけ始めたのは。
食えるバスであれば、周囲のバスゲーム屋の冷たい視線をものともせず、活け締めにして持ち帰った。当時はバスゲーム熱が高く、今もいるのかどうか知らないがバスプロなどもいて、こういうことをおおっぴらにやると、けっこう白い目で見られることもあった。しかし、旨さが勝った。
その後、塩擦りに加え、少量の日本酒を振りかけておく手法を併せることにより、皮の臭味は全く問題にならなくなった。そしてクサイと言われてきた皮は、世に日の目を見ることになったのである。
素材の質としては、スズキとメバルの中間的な扱いができる。
ブラックバス料理は一気に展開した。
既にこのブログでも紹介した塩煮をやった。
千切り野菜をたっぷり使った蒸しものも、和・洋・中とやった。
香草をあれこれ使ったオーブン焼きもやった。
ムニエルも、皮をつけたままでやると別格の味に進化した。
また、夏であれば、トムヤク・クン(エビ)ではなく、トムヤム・プラ(魚)に仕立て、汗を流しながら大勢ですすった。
それぞれに上等の味であったが、やはり、適切な下処理をしたものに塩を振って、焚き火にかざして焼いて食うのが一番うまいように思う。それと、やはり淡水魚を使う東南アジアの料理はピッタリくる。
その一連の中で、ブラックバスもスズキと同様、大きく40㎝を越えると旨くないこともわかってきた。大味で泥臭さが出る。ベストサイズは、よく肥えた35㎝前後だ。また、30㎝程度では肉の味が出ない。
****************************************
さて、ブラックバスの事例であらかた内容を書いてしまったが、「スズキ臭さをドースルか」、という話であった。
そう。ブラックバスと同様、
ウロコ・内臓、腹腔の背骨について腎臓および血液をとり洗ったら、シッポのほうからたっぷりの粗塩で擦り、流水で洗い流し、日本酒少々を振りかけて一呼吸置いたのち、水気を拭いてペーパーでくるんで冷蔵庫へ。これで下処理完了である。
ただスズキの場合、ヒレやエラ蓋の棘が強靱であるため、慣れないとケガをすることがある。塩擦りする前に頭を落とし、全てのヒレをキッチンバサミで切り取っておくとよい。
以前、メバルの塩煮のところで少し書いたが、ヒレは雑菌が繁殖しやすい部位でもあるので、保存する場合はなおさらだ。姿を気にする料理でなければ、とってしまうのがよい。
料理法についてはブラックバスの記述から派生すればよいし、白身なので、けっこういろいろ使える。が、少し加えておく。
特に「洗い」については、上述した下処理を必要とせず、速やかに処理する必要があるからだ。
まず「洗い」にしたい場合、身が硬直前(「身が活かった状態」という)であることが前提となる。硬直中(「締まった状態」という)、もしくは硬直後(「あがった状態」という)では、洗いにする意味がない。
というのは、洗いという調理法は、そぎ切りにした身が、真水に当たったときにチリッと縮れる状態にあってこそ初めて食感と清涼感が出て、余分な脂分と臭味成分が洗い流されて淡味で旨いのであって、硬直に入った身で同じ事をやっても、水気を吸ってベタッとなるばかりなのだ。
旨い洗いを食いたければ、このことを念頭に置いてほしい。
家に帰るまでにどうしても硬直してしまったら、そぎ身を浸けた水に日本酒少々をたらすと身が縮れてくれるという裏技はあるが、その味落ちは比べるべくもない。
そこで、釣り上げてから持ち帰るまでの処置が重要となってくる。洗いをするためには、死後硬直までの時間をできるだけ長くしたいからだ。一般的なサカナの保存・輸送方法とはちょっと違うので、ぜひ憶えておいてはいかがでしょうか。
【 スズキの洗い 】
(1) 釣り上げたスズキは、暴れないように速やかに手カギで脳を壊して即殺し、次いでエラをあけて背骨を断ち切り、海水中で放血する。このとき、体を折り曲げたりしてはいけない。この一連の作業を「活け締め」という。万事を魚体に負担をかけないように配慮する。
(2) 水が澄んだらサカナを取り出し、できれば細いピアノ線を背骨に通っている神経路に通し、神経から筋肉への伝達を断っておくのがよい。
海水で濡らした新聞紙にくるみ発泡箱に横たえるが、絶対に氷水の中に浸してはいけない。氷は小さいかけらを数個、サカナに直接あてないように入れておけば足りる。箱内の温度にして7度前後。
短時間であれば、むしろ氷を入れず、そのまま通気良く持ち帰るのがよい。濡れ新聞の蒸散で冷える程度でちょうどよい。
以上が、死後硬直までの時間を延ばすための処理である。
もちろん、エアを入れた海水で活かして持って帰れるのならば、それが最高である。
洗いにする代表格でマゴチがあるが、これは発泡に活かして帰っても平べったくおとなしくしているサカナなのでかさばらない。
スズキの場合は、ちょっとなあ・・・。
(3) 持ち帰ったら、手早くウロコ・内臓・頭をとり掃除し、スバヤク水で洗い、水気を拭く。この時点で既に硬直状態に入っていたら、今回は洗いはあきらめたほうがよい。またの機会もあろう。塩と酒で臭味をとっておこう。
(4) 3枚におろす前に、ボウルに氷水を張っておく。また、盛りつける器を冷蔵庫で冷やしておく。
中骨をとり、サクにしたら、シッポのほうからそぎ切りにし、順次氷水に落としていく。
全て落とし終わったら、菜箸で軽くかき回してやると、身が縮れてくる。そこで氷を除いてザルにとり、身をペーパーで包んで軽く叩くように水気を切る。これを冷やした器に盛る。
実は、洗いの味は、文字通り、“洗い”加減で変わってくる。洗いが不足すれば臭味が残るし縮れが足りない。洗い過ぎれば旨味が逃げる。さて、そこのところですな。
ワサビ醤油、ポン酢、梅肉、ショウガ醤油、いずれでもよい。
よく冷やした純米もしくは吟醸酒が合いますよ~。
スズキを旨く食うときの要諦は、次の如し。
● 場所、時期、サイズ、体型を適切に選択すること。
● 塩と酒を適切に用いて、皮の臭味を除去しておくこと。
● ただし、洗いにする場合は、活け締めし、適切に持ち帰り、帰宅後は速やかに調理すること。
この場合に限り、塩と酒による下処理は必要ない。
以上、スズキもちゃんとしてあげればいろいろできる、というわけだ。
ということで、ウチも今日は久々のスズキ料理である。
たまにはよい。
1ヶ月半も釣れ続いた“餌床付き(潮付き)”のメバルも、連日の強い南風に吹かれてイカナゴの群と共にどこかへ消えた。これからは、ほかの餌を求めてそれぞれに回遊、あるいは居残りと分かれていく。彼らが落ち着くまで、ひとまずここらで小休止か。
昨日は久しぶりの雨が降り、それでも少しは残っとらんかいなと思い、ちょいと行ってみた。ベイトは散漫なシラスの群れに変わり、小アジが散発的に群れ、雨、風、濁り、餌、とくれば、もうセイゴ・スズキの独壇場である。背中を出して餌を追い回すお祭り野郎もいた。これではメバルがいたとしても迷惑顔をするだけである。
早々に撤収、とした矢先、回収目前で65㎝が掛かってしまった。
残念なことに、スズキはここまで大きくなってしまうと食っても釣ってもつまらない。やはりスズキは、産卵前と後を除いた時期、50㎝前後の、背・腹の凛と張った勇ましいげなヤツなら良いのであって、今回釣れたようなのは本来ならばお帰り願いたいところであったが、傷がついてしまえばやむなし。
というわけで、締めて持ち帰った。
大きなスズキは、どうやって釣ろうが、どうやって食おうが、引きも食味も鈍重である。全調子に近いメバル竿にライン3ポンドだから獲るまでに時間はかかるが、重量感だけで面白くはないし、身がゆるく大味だ。どちらも総じて“のっそり”している。
世間では、90㎝のスズキ釣りました!などと釣り雑誌に見ることがあるが、釣ったあと、皆さんはどう対処しておられるのであろうか。
もうひとつスズキは問題を抱えている。大きくなるほどに、特有の「青臭さ」が強くなるのだ。これは、サカナ全般の、いわゆる“生臭み”とは別の臭さである。
スズキに近い仲間に淡水のブラックバスがいるが、やはり共通した臭さをもっている。これまた親戚のヒラスズキではそのような臭味は薄いようであるが、もし、あの臭味が淡水と関係があるのであれば(たとえば河川水に入るときの浸透圧調整や防護機能など)、河口産ののヒラスズキを一度食ってみたいところ。
投げやりに書いているようであるが、けしてスズキそのものを嫌っているわけではない。長崎や神戸では、急流でイワシを追いかける時期を狙って出かけたし、実は、水の清澄良質な湖沼を探しては、食いたくなるとブラックバスを釣りに通った。銀山湖のバスは特に風味がよい。
しかし、いかなる事情にせよ、あの青臭みをそのままにはできまい。
そこをどうするか、というお話。
***************************************
十数年前、長崎でブラックバスに手を染め始めた頃、友人が買ってきたBeナントカという物欲促進系アウトドア雑誌に、「ブラックバスを食べてみよう!」という記事が出たことがある。
その後、ブラックの日本産在来水棲生物に対する食害の問題が取り沙汰され、これはゲームフィッシャーと漁業者、研究・行政を交えての熱い論争にまで発展したが、そのときに水産庁やいくつかの県や漁協が促進PRしたのが「キャッチ&イート」であって、まあ、この雑誌の記事は先駆的であったとも言えよう。
さて、それによると「皮に臭味があるので、三枚におろして皮を必ずはがし、ムニエルとかフライとかに仕立てれば、食べられますよ」といった内容であったと思う。
で、早速やってみた。
実に腰のないサラリとした肉質で、若干の泥臭さを伴う浅い味の単なる洋食であって、あれほど果敢な魚食性のサカナが、これっぱかりのものかとガッカリしたものだ。それ以来、しばらくバス釣りからは遠ざかるのである。
それから数年。
銀山湖に仲間でキャンプに行き、私は素潜りでコイを突き、友人は散ってバス釣りだ。そして夕方、友人は35㎝内外のバスを数尾釣って戻った。
数尾のコイは、洗いにしてワサビ醤油と酢味噌として、水が良いせいか、すばらしかった。
一方、ブラックはどうしたかというと、今さらフライもムニエルもつまらんということで、ひとつは皮をひいてコイと同様に洗いとし、残り数本を、皮の臭味を知っていた私は、とりあえず基本に則り、臭味をとる意味で粗塩で擦ったのち水洗いし、塩を振り直し、焚き火にかざして焼いてみたのである。
これが、たいしたものであった。
例の雑誌には、皮がクサイからとる、と書いてあって、たしかに嗅いでみれば臭かったし、かといって皮をはいでしまったブラックバスは、味わうに値せぬ味とアタマから信じ込んでいた。
しかしこれを食ったとき、それまでの自分の固定観念と精進のなさを悔やんだことだ。
旨い。 皮が、旨い。 皮と一体となった身が化けている。
数人で、あっというまにむさぼり食ってしまった。
かつて頼りなかった身肉は、焼けた皮と合わさることによって、やさしい甘味と野性味、そして十分納得のいく旨味を獲得した。
それからのちである。私が“食える水に棲む”ブラックバスを追いかけ始めたのは。
食えるバスであれば、周囲のバスゲーム屋の冷たい視線をものともせず、活け締めにして持ち帰った。当時はバスゲーム熱が高く、今もいるのかどうか知らないがバスプロなどもいて、こういうことをおおっぴらにやると、けっこう白い目で見られることもあった。しかし、旨さが勝った。
その後、塩擦りに加え、少量の日本酒を振りかけておく手法を併せることにより、皮の臭味は全く問題にならなくなった。そしてクサイと言われてきた皮は、世に日の目を見ることになったのである。
素材の質としては、スズキとメバルの中間的な扱いができる。
ブラックバス料理は一気に展開した。
既にこのブログでも紹介した塩煮をやった。
千切り野菜をたっぷり使った蒸しものも、和・洋・中とやった。
香草をあれこれ使ったオーブン焼きもやった。
ムニエルも、皮をつけたままでやると別格の味に進化した。
また、夏であれば、トムヤク・クン(エビ)ではなく、トムヤム・プラ(魚)に仕立て、汗を流しながら大勢ですすった。
それぞれに上等の味であったが、やはり、適切な下処理をしたものに塩を振って、焚き火にかざして焼いて食うのが一番うまいように思う。それと、やはり淡水魚を使う東南アジアの料理はピッタリくる。
その一連の中で、ブラックバスもスズキと同様、大きく40㎝を越えると旨くないこともわかってきた。大味で泥臭さが出る。ベストサイズは、よく肥えた35㎝前後だ。また、30㎝程度では肉の味が出ない。
****************************************
さて、ブラックバスの事例であらかた内容を書いてしまったが、「スズキ臭さをドースルか」、という話であった。
そう。ブラックバスと同様、
ウロコ・内臓、腹腔の背骨について腎臓および血液をとり洗ったら、シッポのほうからたっぷりの粗塩で擦り、流水で洗い流し、日本酒少々を振りかけて一呼吸置いたのち、水気を拭いてペーパーでくるんで冷蔵庫へ。これで下処理完了である。
ただスズキの場合、ヒレやエラ蓋の棘が強靱であるため、慣れないとケガをすることがある。塩擦りする前に頭を落とし、全てのヒレをキッチンバサミで切り取っておくとよい。
以前、メバルの塩煮のところで少し書いたが、ヒレは雑菌が繁殖しやすい部位でもあるので、保存する場合はなおさらだ。姿を気にする料理でなければ、とってしまうのがよい。
料理法についてはブラックバスの記述から派生すればよいし、白身なので、けっこういろいろ使える。が、少し加えておく。
特に「洗い」については、上述した下処理を必要とせず、速やかに処理する必要があるからだ。
まず「洗い」にしたい場合、身が硬直前(「身が活かった状態」という)であることが前提となる。硬直中(「締まった状態」という)、もしくは硬直後(「あがった状態」という)では、洗いにする意味がない。
というのは、洗いという調理法は、そぎ切りにした身が、真水に当たったときにチリッと縮れる状態にあってこそ初めて食感と清涼感が出て、余分な脂分と臭味成分が洗い流されて淡味で旨いのであって、硬直に入った身で同じ事をやっても、水気を吸ってベタッとなるばかりなのだ。
旨い洗いを食いたければ、このことを念頭に置いてほしい。
家に帰るまでにどうしても硬直してしまったら、そぎ身を浸けた水に日本酒少々をたらすと身が縮れてくれるという裏技はあるが、その味落ちは比べるべくもない。
そこで、釣り上げてから持ち帰るまでの処置が重要となってくる。洗いをするためには、死後硬直までの時間をできるだけ長くしたいからだ。一般的なサカナの保存・輸送方法とはちょっと違うので、ぜひ憶えておいてはいかがでしょうか。
【 スズキの洗い 】
(1) 釣り上げたスズキは、暴れないように速やかに手カギで脳を壊して即殺し、次いでエラをあけて背骨を断ち切り、海水中で放血する。このとき、体を折り曲げたりしてはいけない。この一連の作業を「活け締め」という。万事を魚体に負担をかけないように配慮する。
(2) 水が澄んだらサカナを取り出し、できれば細いピアノ線を背骨に通っている神経路に通し、神経から筋肉への伝達を断っておくのがよい。
海水で濡らした新聞紙にくるみ発泡箱に横たえるが、絶対に氷水の中に浸してはいけない。氷は小さいかけらを数個、サカナに直接あてないように入れておけば足りる。箱内の温度にして7度前後。
短時間であれば、むしろ氷を入れず、そのまま通気良く持ち帰るのがよい。濡れ新聞の蒸散で冷える程度でちょうどよい。
以上が、死後硬直までの時間を延ばすための処理である。
もちろん、エアを入れた海水で活かして持って帰れるのならば、それが最高である。
洗いにする代表格でマゴチがあるが、これは発泡に活かして帰っても平べったくおとなしくしているサカナなのでかさばらない。
スズキの場合は、ちょっとなあ・・・。
(3) 持ち帰ったら、手早くウロコ・内臓・頭をとり掃除し、スバヤク水で洗い、水気を拭く。この時点で既に硬直状態に入っていたら、今回は洗いはあきらめたほうがよい。またの機会もあろう。塩と酒で臭味をとっておこう。
(4) 3枚におろす前に、ボウルに氷水を張っておく。また、盛りつける器を冷蔵庫で冷やしておく。
中骨をとり、サクにしたら、シッポのほうからそぎ切りにし、順次氷水に落としていく。
全て落とし終わったら、菜箸で軽くかき回してやると、身が縮れてくる。そこで氷を除いてザルにとり、身をペーパーで包んで軽く叩くように水気を切る。これを冷やした器に盛る。
実は、洗いの味は、文字通り、“洗い”加減で変わってくる。洗いが不足すれば臭味が残るし縮れが足りない。洗い過ぎれば旨味が逃げる。さて、そこのところですな。
ワサビ醤油、ポン酢、梅肉、ショウガ醤油、いずれでもよい。
よく冷やした純米もしくは吟醸酒が合いますよ~。
スズキを旨く食うときの要諦は、次の如し。
● 場所、時期、サイズ、体型を適切に選択すること。
● 塩と酒を適切に用いて、皮の臭味を除去しておくこと。
● ただし、洗いにする場合は、活け締めし、適切に持ち帰り、帰宅後は速やかに調理すること。
この場合に限り、塩と酒による下処理は必要ない。
以上、スズキもちゃんとしてあげればいろいろできる、というわけだ。
ということで、ウチも今日は久々のスズキ料理である。
たまにはよい。
2007年05月24日
もうひとつの「塩煮」
なかなか更新できず,お恥ずかしい次第です。さて・・・。
ワタクシは,けして塩煮だけにこだわっているわけでもなく塩煮マニアでもないのです。が,片手落ちで終わらせるわけにもいかない。ということで「もうひとつの塩煮」についてお話しておきます。
07508「塩煮の世界」で,調理法としての塩煮には大別して2種類あると書いた。ひとつは沖縄の「マース煮」であって,これは直訳すればまさに「塩」煮であり,海水を調味料として用いた料理。 既に,この原型改良型および派生型については紹介した。
もうひとつは,長崎県を主体に九州圏で主に継承されている郷土料理の「塩煮」であり,これはきつい塩をあてた魚を煮出し,その塩分で野菜類入れた汁物に仕立てる料理で,これは氷や冷蔵庫がない時代の魚の保存法の延長にある。従って,日本海側,太平洋側を問わず,塩魚を用いた汁物は,名前を変えて各地に存在する。
たとえば三陸から北海道にかけてサバやサンマ,タラやその他の魚に塩をしてを用いた「三平汁」,大坂の船場で日本海の塩サバを用いた「船場汁」,北海道で塩したタラを用いた「じゃっぱ汁」,また,魚ではないが,塩漬けにしたクジラの本皮(表皮と脂肪繊維)を薄切りして用いる「皮汁」もしくは「クジラ汁」なども,古くから沿岸部のみならず山間部にまで浸透している。いずれにせよ,魚と塩が主役の料理なのである。
日本の魚食文化に浸透している度合いとしては,「塩煮」の方が分布が広く,むしろ沖縄の塩煮(マース煮)の方が沖縄地方に固有の特殊なケースと言えるので,本来は前者を「塩煮」,後者を「マース煮」とはっきり呼び分けるべきかもしれない。ただ,前者であっても「塩煮」という呼称は,九州地方の一部にのみ存在するので,これまたややこしい。
マース煮と塩煮の違いは,前者が魚自体を味わうことに重点を置いた一種の「煮物」であるのに対し,後者のそれは「汁」に重点を置き,その中で,魚,野菜などを総合的に味わう料理である点だ。目の前にある同じ素材で,2種類を同時につくり比較してみるのもオモシロイ。ほとんど同じ素材でも作業工程によって味のひき出されかた,味の組成がちがうことに気づくはずだ。これらは,調理技術を深めていく上で大変適した教材的料理でもあると思う。
今回は,私の中の塩煮の原型である,長崎県における塩煮のつくりかたを紹介する。要は,塩の使い方が違うのである。
【長崎県 野母崎半島における塩煮】
この塩煮は,汁の具材としてジャガイモとタマネギを合わせるところが特徴です。
(1) 魚は何でも良い。また,アラだろうが,骨ごとのブツ切りだろうが,切り身だろうが,差し支えない。ウロコは隅々までよく除き,魚は全て食べやすい大きさに切り,ザッと水洗いして水気を切ったらボウルにぶち込み,天然塩を全体にきつめにまぶしておく。そのまま最低30分寝かせる。あるいは一晩置いてもよい。
(2) 鍋に水を張り,厚めに切ったジャガイモを入れて強火にかける。ジャガイモの分量の目安は適宜。箸で刺してパリッと割れる程度に硬めに火が通ったら,塩しておいた魚を洗わずに投入する。この間,ずっと強火のまま。
(3) 沸騰したらアクをとり始める(吹きこぼれないよう,かつ沸騰が続くよう火加減を調節)。ひたすらアクをとり続け,ダシが半透明に澄んだタイミングでアク取りを終了し,沸騰しない程度に火を落とす。
(4) タマネギ半~1個程度を5㎜程度にクシ切りにし,バラして投入。タマネギの分量の目安は,鍋の表面を概ね覆う程度。タマネギが半透明になったら出来上がり。味が薄いようであれば,薄口醤油などをたらして調整する。
(5) これだけでも十分であるが,風味として刻みネギやおろし生姜を少量加えても佳。
この「塩煮」のポイントは,
● そのままで食べるには塩辛過ぎるほどの分量の塩を魚にあてる。目安としてはシメサバをつくるときに当てるベタ塩の加減とほぼ同等。浸透圧によって臭みは余分な水分と共に滲出し,身を引き締め,同時に魚の調味も兼ねている。
● 和食の教科書にある「潮汁」あるいは「すまし汁」の作り方のように,「魚にお湯をかけて掃除して冷水に放ち洗って云々,」といった細かな作業は一切必要ない。臭みとりから調味まで,全て塩がやってくれる。
● ジャガイモに火を通すとき,強火で一気に沸騰させることにより,でんぷん質がベタつかない仕上がりとなる(ただし,翌日に持ち越すと,でんぷんが糊化するので若干水っぽくなる)。
● 魚を投入してからも引き続き強火のままに沸騰させることにより,すばやく臭みと汚れを除去することができる。親の敵をとるが如く,ここではアクを取るのである。
● 魚を入れてからも,アクとりしている間はずっと強火のままであるが,ダシが澄んだにもかかわらず強火のままにしておくと,延々とアクが出る羽目になる。ダシが澄んだらアクとり終了,沸騰しない程度の弱火に落とす。
● タマネギは煮え進むと甘味成分が強くなり過ぎ,味の再調整が必要となる。従って,スッと半透明になった瞬間,いわゆる“煮えばな”を最良の食べるタイミングとする。
● 味の調整で薄口醤油を加えることもあるが,基本は,出来上がりの味を想定して魚にあてる塩を加減することにある。いわば,味の大枠は,一番最初の作業で決まってしまうと言ってよい。ここが,これまで紹介してきた塩煮(マース煮)とは異なる奥の深さの部分。
さて皆さん。この料理をつくる過程で,ひとつ試してほしいことがある。
ジャガイモが煮えたら塩魚を投入し,汁が澄むまでアクをとる,と。この段階で,汁の味をみてやってほしいのです。びっくりするハズ。
もう,ほぼ,9割以上,この段階で既に味はできているのですよ。ジャガイモからはそんなにダシが出るわけもないので,要は“塩した魚を茹でただけ”の味です。これが塩のチカラなのです。
(問い)それでは,魚を生のまま茹でて,そこに塩で味をつけたら同じ味になるか?
(答え)→なりません。旨みの薄い,生臭い,塩汁になります。一般的な和食の潮汁は,この,あとから塩を加えるタイプなので,いろいろ下処理がめんどうになりますし、十分に旨みが出ないから酒のほかに昆布や、場合によってはカツオなどのダシを加えるのです。
更に,タマネギを加えて一呼吸置いて,もういちど味見してみてください。
これにも,タマげます。完成,なのですよ。これで。
何回かやってみて,魚にこれくらいの塩をしておけば,このくらいの塩加減の汁になるな,というポイントを,自分なりに経験としてつかんでおくことは大切なのですが,実はこのタマネギ,カリウムをたくさん含んでいる。塩の主成分はナトリウムですね。
カリウムとナトリウムは,細胞の壁を境にして,常にバランスを保とうとしているのです。従って,多少塩辛すぎたとしても,ある程度はタマネギが吸収して味のバランスを保ってくれるのです。
というしくみになっております。 なんとありがたい野菜でありましょうか。
どうです?
極めてラクチンでしょう!
これも,マース煮同様,15分1本勝負であります。
ジャガやタマを入れなくても,季節の葉物,野菜,なんでも刻んで入れればOKです。根菜類を入れるときには魚の前に。葉物は魚のアクを取り終わってから入れればよろしい。ただ,ジャガタマが,いちばん魚の味を邪魔せずに旨みを出してくれるので、私はこれを基本形としています。
調味過程でマース煮との違いはどこにあるかといえば,マース煮が,焼いて,酒で煮て,味が浸透しやすくしたところに塩水で味付けするのに対し,塩煮は,あらかじめ魚に塩味をつけておいて水で煮て,その浸みだした旨みで汁や野菜を味付けする,という点。
また,マース煮が,主に白身の魚に適しているのに対し,この塩煮は,赤身の魚にも適しているのです。もちろん白身でもイケます。青魚でマース煮をすると,やや生臭さが残る。まあ魚料理はなんでも,時間がたつほどに臭みは発生するものですが。
煮物,汁物は,やはり「煮えばな」を食わないと、或いは食べてもらわないと、いけない。
料理はつくるタイミングと同等に,食べるタイミングも重要なのはご周知のとおり。
それをわかってくれる人にこそ食べてもらいたいし,一緒に暮らしたい,というのもありますな!
皆さんのご家庭はどうですかな?
さて,これまで紹介した2つの塩煮についてひと言でまとめると,
マース煮の要諦は,
「魚の下処理と加える塩水の塩加減,そして火加減」
塩煮の要諦は,
「最初に魚へあてる塩の加減,そして火加減」
内地の塩煮のほうが,チョイ楽か。
こまかいところは、お手数ですが過去記事をご覧下され。
ま,こんなとこで。
ワタクシは,けして塩煮だけにこだわっているわけでもなく塩煮マニアでもないのです。が,片手落ちで終わらせるわけにもいかない。ということで「もうひとつの塩煮」についてお話しておきます。
07508「塩煮の世界」で,調理法としての塩煮には大別して2種類あると書いた。ひとつは沖縄の「マース煮」であって,これは直訳すればまさに「塩」煮であり,海水を調味料として用いた料理。 既に,この原型改良型および派生型については紹介した。
もうひとつは,長崎県を主体に九州圏で主に継承されている郷土料理の「塩煮」であり,これはきつい塩をあてた魚を煮出し,その塩分で野菜類入れた汁物に仕立てる料理で,これは氷や冷蔵庫がない時代の魚の保存法の延長にある。従って,日本海側,太平洋側を問わず,塩魚を用いた汁物は,名前を変えて各地に存在する。
たとえば三陸から北海道にかけてサバやサンマ,タラやその他の魚に塩をしてを用いた「三平汁」,大坂の船場で日本海の塩サバを用いた「船場汁」,北海道で塩したタラを用いた「じゃっぱ汁」,また,魚ではないが,塩漬けにしたクジラの本皮(表皮と脂肪繊維)を薄切りして用いる「皮汁」もしくは「クジラ汁」なども,古くから沿岸部のみならず山間部にまで浸透している。いずれにせよ,魚と塩が主役の料理なのである。
日本の魚食文化に浸透している度合いとしては,「塩煮」の方が分布が広く,むしろ沖縄の塩煮(マース煮)の方が沖縄地方に固有の特殊なケースと言えるので,本来は前者を「塩煮」,後者を「マース煮」とはっきり呼び分けるべきかもしれない。ただ,前者であっても「塩煮」という呼称は,九州地方の一部にのみ存在するので,これまたややこしい。
マース煮と塩煮の違いは,前者が魚自体を味わうことに重点を置いた一種の「煮物」であるのに対し,後者のそれは「汁」に重点を置き,その中で,魚,野菜などを総合的に味わう料理である点だ。目の前にある同じ素材で,2種類を同時につくり比較してみるのもオモシロイ。ほとんど同じ素材でも作業工程によって味のひき出されかた,味の組成がちがうことに気づくはずだ。これらは,調理技術を深めていく上で大変適した教材的料理でもあると思う。
今回は,私の中の塩煮の原型である,長崎県における塩煮のつくりかたを紹介する。要は,塩の使い方が違うのである。
【長崎県 野母崎半島における塩煮】
この塩煮は,汁の具材としてジャガイモとタマネギを合わせるところが特徴です。
(1) 魚は何でも良い。また,アラだろうが,骨ごとのブツ切りだろうが,切り身だろうが,差し支えない。ウロコは隅々までよく除き,魚は全て食べやすい大きさに切り,ザッと水洗いして水気を切ったらボウルにぶち込み,天然塩を全体にきつめにまぶしておく。そのまま最低30分寝かせる。あるいは一晩置いてもよい。
(2) 鍋に水を張り,厚めに切ったジャガイモを入れて強火にかける。ジャガイモの分量の目安は適宜。箸で刺してパリッと割れる程度に硬めに火が通ったら,塩しておいた魚を洗わずに投入する。この間,ずっと強火のまま。
(3) 沸騰したらアクをとり始める(吹きこぼれないよう,かつ沸騰が続くよう火加減を調節)。ひたすらアクをとり続け,ダシが半透明に澄んだタイミングでアク取りを終了し,沸騰しない程度に火を落とす。
(4) タマネギ半~1個程度を5㎜程度にクシ切りにし,バラして投入。タマネギの分量の目安は,鍋の表面を概ね覆う程度。タマネギが半透明になったら出来上がり。味が薄いようであれば,薄口醤油などをたらして調整する。
(5) これだけでも十分であるが,風味として刻みネギやおろし生姜を少量加えても佳。
この「塩煮」のポイントは,
● そのままで食べるには塩辛過ぎるほどの分量の塩を魚にあてる。目安としてはシメサバをつくるときに当てるベタ塩の加減とほぼ同等。浸透圧によって臭みは余分な水分と共に滲出し,身を引き締め,同時に魚の調味も兼ねている。
● 和食の教科書にある「潮汁」あるいは「すまし汁」の作り方のように,「魚にお湯をかけて掃除して冷水に放ち洗って云々,」といった細かな作業は一切必要ない。臭みとりから調味まで,全て塩がやってくれる。
● ジャガイモに火を通すとき,強火で一気に沸騰させることにより,でんぷん質がベタつかない仕上がりとなる(ただし,翌日に持ち越すと,でんぷんが糊化するので若干水っぽくなる)。
● 魚を投入してからも引き続き強火のままに沸騰させることにより,すばやく臭みと汚れを除去することができる。親の敵をとるが如く,ここではアクを取るのである。
● 魚を入れてからも,アクとりしている間はずっと強火のままであるが,ダシが澄んだにもかかわらず強火のままにしておくと,延々とアクが出る羽目になる。ダシが澄んだらアクとり終了,沸騰しない程度の弱火に落とす。
● タマネギは煮え進むと甘味成分が強くなり過ぎ,味の再調整が必要となる。従って,スッと半透明になった瞬間,いわゆる“煮えばな”を最良の食べるタイミングとする。
● 味の調整で薄口醤油を加えることもあるが,基本は,出来上がりの味を想定して魚にあてる塩を加減することにある。いわば,味の大枠は,一番最初の作業で決まってしまうと言ってよい。ここが,これまで紹介してきた塩煮(マース煮)とは異なる奥の深さの部分。
さて皆さん。この料理をつくる過程で,ひとつ試してほしいことがある。
ジャガイモが煮えたら塩魚を投入し,汁が澄むまでアクをとる,と。この段階で,汁の味をみてやってほしいのです。びっくりするハズ。
もう,ほぼ,9割以上,この段階で既に味はできているのですよ。ジャガイモからはそんなにダシが出るわけもないので,要は“塩した魚を茹でただけ”の味です。これが塩のチカラなのです。
(問い)それでは,魚を生のまま茹でて,そこに塩で味をつけたら同じ味になるか?
(答え)→なりません。旨みの薄い,生臭い,塩汁になります。一般的な和食の潮汁は,この,あとから塩を加えるタイプなので,いろいろ下処理がめんどうになりますし、十分に旨みが出ないから酒のほかに昆布や、場合によってはカツオなどのダシを加えるのです。
更に,タマネギを加えて一呼吸置いて,もういちど味見してみてください。
これにも,タマげます。完成,なのですよ。これで。
何回かやってみて,魚にこれくらいの塩をしておけば,このくらいの塩加減の汁になるな,というポイントを,自分なりに経験としてつかんでおくことは大切なのですが,実はこのタマネギ,カリウムをたくさん含んでいる。塩の主成分はナトリウムですね。
カリウムとナトリウムは,細胞の壁を境にして,常にバランスを保とうとしているのです。従って,多少塩辛すぎたとしても,ある程度はタマネギが吸収して味のバランスを保ってくれるのです。
というしくみになっております。 なんとありがたい野菜でありましょうか。
どうです?
極めてラクチンでしょう!
これも,マース煮同様,15分1本勝負であります。
ジャガやタマを入れなくても,季節の葉物,野菜,なんでも刻んで入れればOKです。根菜類を入れるときには魚の前に。葉物は魚のアクを取り終わってから入れればよろしい。ただ,ジャガタマが,いちばん魚の味を邪魔せずに旨みを出してくれるので、私はこれを基本形としています。
調味過程でマース煮との違いはどこにあるかといえば,マース煮が,焼いて,酒で煮て,味が浸透しやすくしたところに塩水で味付けするのに対し,塩煮は,あらかじめ魚に塩味をつけておいて水で煮て,その浸みだした旨みで汁や野菜を味付けする,という点。
また,マース煮が,主に白身の魚に適しているのに対し,この塩煮は,赤身の魚にも適しているのです。もちろん白身でもイケます。青魚でマース煮をすると,やや生臭さが残る。まあ魚料理はなんでも,時間がたつほどに臭みは発生するものですが。
煮物,汁物は,やはり「煮えばな」を食わないと、或いは食べてもらわないと、いけない。
料理はつくるタイミングと同等に,食べるタイミングも重要なのはご周知のとおり。
それをわかってくれる人にこそ食べてもらいたいし,一緒に暮らしたい,というのもありますな!
皆さんのご家庭はどうですかな?
さて,これまで紹介した2つの塩煮についてひと言でまとめると,
マース煮の要諦は,
「魚の下処理と加える塩水の塩加減,そして火加減」
塩煮の要諦は,
「最初に魚へあてる塩の加減,そして火加減」
内地の塩煮のほうが,チョイ楽か。
こまかいところは、お手数ですが過去記事をご覧下され。
ま,こんなとこで。
2007年05月11日
メバル3型と,その味覚
境港は早くも夏の気配濃厚であるが,メバルが騒がしい。
ここ1ヶ月以上,相変わらず冷蔵庫のメバル在庫状況に応じていくつかの漁場をのぞきに行っているが,小さいほうでも20㎝前後,ほとんどが25㎝前後で中には尺手前も。1回もスカがない。
そもそもこんなに釣れ続くことは珍しい。潮の中ないし縁辺分にたむろして小魚を狙っているメバルの食い気はすごい。今年は餌生物の種類と出現傾向,蝟集と分散が例年と若干異なるためか,このような索餌形態が多いように感じる。根に付いている連中であれば,大きいのから順に釣っていき,次の群れが入ってくるまでにひと息入るものだが,潮付きは,条件さえ合えば毎日釣ってもおかわりが入って来る。潮に居付けるだけの体力をつけた者から順次加入,といったところだろう。餌の群れが大きいほど,また,その群れをまとめる潮目や湧昇流が長く横たわるほど,より広範囲からメバルを集めてくれる理屈だ。風向きや潮によってスポットまでの距離や方向,メバルの深度等は日並みで変わるものの,必ずどこかに居る,というのが現在の状況だ。はてさていつまで続く事やら,経過に観察を要す。
ということなので,沢山釣ってもきりがない。独りで行くときには3尾釣ったらさっさと帰ることにした。オカズさえ獲れればあとはそっとしておく。
ところで,最近学会でも常識となりつつあるメバルの3型(赤・黒(青)・茶)であるが,私がかかわっている場所でも時期的に型の組成に変化が見られてオモシロイ。現在に続く荒食いが始まったのが4月上旬で,その時は例年になく25㎝級の大きな赤が2割,居残りらしきソコソコの茶が8割といった構成だった。この頃はヘチのワカメ林の中から良型が目の前で飛び出すような見釣りが続いていたが,下旬に入り,赤はどこかへ去り(おそらく磯場に繁茂するガラモ場に),茶はここを離れて沖目の餌床に付くようになった。しばらくは夜にはヘチに戻ってくる部隊もいたようだが,4月下旬に入り,いわゆる青が混じるようになると,ヘチをねぐらとする部隊は極端に減り,沖目に散開,餌などの条件によっては集束する。胃内容物も,エビ等甲殻類から小魚に変わった。これが更に進むと,例年並みであれば,夏には青の中~大判が暴れまくり,周辺で小~中の茶とチビ赤が混じり合って遊ぶのであるが,今年はどうなるか。
さて,これらの変化に呼応して,それぞれの型ごとの体型や脂の乗り,肉質なども当然変化していく。このへんが,大変味わい深い。
とうわけで前置きが長くなったが,今回はメバルの3型とその味の考察。
メバルを釣っておられる皆さんも,どうも色カタチで味が違うようだとお気づきの方が多いと思う。そこでこんな表をまとめてみた。メバルの3型の出現時期,サイズ,および調理方法でみた食味評価である。ここ2年間の海の急激な変化によって少々傾向が変わってきている要すだが,だいたいこんなところだと感じている。メバルは概ね20㎝を境に肉質が変わるので,分けて記載した。
なお,食味で×をつけては魚に申しわけないので「△」にとどめおいた。また,来遊状況についてはあくまでも境港港湾エリアが主体であることをおことわりしておく。

この表に加え,各型の形態(プロポーション)および時期的な釣れ方の変化などを勘案し,味覚的視点からみたメバルの分類型の特徴をまとめると,およそ次のよう。
【赤】
港湾付近への滞留期間が短く,かつ小型が主体。港湾部へはワカメ林などの海藻類を拠り所として来遊するので,これが消滅すれば,よそへ向かう。他の2型に比して味が繊細で身が薄く,刺身や焼き魚では十分に味わえない。10㎝前後の小型個体は春に雨後の竹の子の如くわき出すので「竹の子メバル」と呼ばれるが,この時期は味がたよりない(標準和名のタケノコメバルは,最近,ベッコウゾイと呼ばれている)。
晩春の一時期,シラスを食い始めるエリアの20㎝前後のものは,煮魚にして佳味。濃い口醤油や砂糖を用いた田舎煮でも悪くはないが,3型中最もしっとり繊細な肉質であるため,昆布ダシに薄口醤油および少量の酒・ミリンを吸い物程度に調味した下地で静かに煮る「沢煮」が適す。また,3型中最も臭みが薄いので,沢煮を冷たく冷やして下地と共に味わう“冷製”も品がよい。
いずれにせよ,最適サイズの20㎝前後は,市場には揚がるものの,境港の港湾メバル釣り師には,ちょいと縁が薄い。
【黒(青)】
他の2型に比して,体高に対して体長が長く尾びれが大きいため,相対的に体の後半が痩せているように見える。これは,高速回遊して小魚を追い回す生態に適している。身の厚みは他の2型の中間くらいだが筋肉質。
晩春,ワカメ林が枯れ始める頃から接岸が始まり,次第に個体数を増す。餌が沖目にないときには構造物にも定着するが,他の2型ほど執着せず,夏のある時期が過ぎると一斉にいなくなる。
春の小型のものは問題ないが,夏が近づき大型が釣れだすと,これが悩ましい。磯臭さこそないものの皮が固く,煮てもブリンと反り返りゴム質,焼けば身との相性が悪い。脂が乗ってもこの傾向は変わらない。身肉のほうも,3型中最も硬く,加熱してもしっとりせずにバラバラだ。焼いても煮てもこの傾向は変わらない。
ではどうするかと言えば,刺身に限る。皮をつけたまま湯シモとし,氷水にとったのを削ぎ切りにしてワサビ醤油でもよいし,肉を薄く削ぎ,湯引いて千切りにした皮と共にポン酢で食べるのもよい。夏の風情だ。皮の薄い茶メバルでは,湯引けば皮がはがれてしまうし歯ごたえに欠ける。
また,青メバルは肉が硬いだけあって3型中最も日持ちが良く,3枚におろしてペーパーとラップにくるんでおけば,1週間でも身がしっかりしたままである。従って,尺前後の青メバルが1枚あれば,数日間にわたって夕暮れの晩酌オカズに困らない。
【茶】
他の2型,特に青は専ら索餌目的で港湾に回遊するのに対し、茶メバルの集中的な接岸は産卵が主な動機のようである。晩秋から本格的な来遊が始まり,産卵を経て分散する。3型中で最も環境適応能力が優れており,春の頃は海中林で赤メバルと,初夏には沖目で青メバルとの混在も多く見られる。例年の傾向として,成熟個体の接岸,産卵,回復,小型個体の成長,分散,をサイクルとしているが,変則的に大型個体が構造物を拠り所として長期にわたって居残る場合も散見する。
3型中,味覚上,また調理法上,最もバランスが良く,かつ汎用性が高いのがこの型だと思う。刺身ならば冬場に身が締まり脂が乗り,厚めに削ぎ切った飴色の身にははプツッとした気持ちのよい食感と穏やかな甘味がある。この意味において刺身に適すはせいぜい20㎝チョイまでで,25㎝を越えると刺身の小味は消える。そうなれば焼くか煮るのがよいが,焼いて旨いのは25㎝前後までである。いわゆる尺手前や尺上は大味になるので,若干旨みを加えてやる必要があるため,煮,或いは蒸すのが適している。煮・焼きの旬は,冬の生殖巣が未熟の時期と,晩春の回復後の2回訪れる。
本種はホントにありがたい。ほぼ周年獲れる上に近場で釣れる数も多い。時期ごとに,旨いサイズが変わり,ちゃんと適した調理法が存在する。尺に近づいても,青メバルほど味が荒れるわけでもなく,皮も硬くならず,しっとりした肉質と,しっかりした皮の味に一体感がある。
それに・・・。ここでは刺身・焼き・煮と代表的な調理法のみを挙げてきたが,実はこの茶メバルには,どうしても欠かせない,季節限定の料理があるのだ。それは「天ぷら」だ。
なーんだと言う事なかれ。
ちょうど山にコゴミ,タラの芽,ウドなどが出てくるころ,この時だけレギュレーションを18㎝から2㎝ほど下げる。スマンスマンとつぶやきつつ下げる。これを,そこそこ数を釣り,面倒でも3枚におろし,腹骨をすき,皮をひいておく。中骨はとらなくてよい。皮をつけたままでもそれはそれで香ばしくはあるのだが,この時ばかりは雑味なく味わいたいので皮はとる。
まずきれいなサラダ油で山菜類をスバヤク揚げたのち,その鍋にごく少量のゴマ油をたらし,それでカラリとメバルを揚げる。片身で1枚。少々強火でカリン,と揚げる。
単なる白身ではない。きめ細かくキューッと歯にまとわりつくようで,噛めばじんわりと甘味,その味を懸命に追いかけようとする刹那ののち,サラリと解けてノドに消え落ちてゆく。もどかしくて次の一切れに箸をのばしてしまう。単なる淡泊に非ず,ただならぬ淡味である。淡味なれど滋味である。引き際が絶妙で,知らずして引きずり込まれる味だ。
この味わいは中~大のサイズでは,まず出ない。大判を切り身にして揚げても同じ味にはならない。要は小サイズの茶メバル特有の肉質なのだ。
私にとっての春告げ魚は,これに尽きる。この短い期間だけ,毎年これを数回ヤル。メバルだけ揚げても雰囲気が出ないし,かといって他の野菜と揚げてもピンとこない。山菜と若メバル。春の天恵である。
**************************************
こうして書き綴り振り返ると,メバルの3型は,実に上手に棲み分けしており,時期・サイズで空間の共有と分離をおこなっている。そして,これに伴い食味の上でも交代があり,常にいずれかの型が何らかの調理法で賞味に値するしくみとなっている。天の采配とはこのことだ。
釣れる魚のサイズのことを言えば,釣りの指向性にもいろいろある中,私は完全に味覚第一,かつオカズ確実確保,必要十分量漁獲,といったスタイルである。その時期に応じて一番旨い種類とサイズが適度に釣れてくれればよい。それを選んで釣ろうとするから,それはそれでアレコレ頭を悩ます。
こんなだから,時折,意に反して季節はずれの青の尺物などが釣れると,当惑する。釣れたぜと自慢はするけれど・・・。
茶メバルであっても大きすぎるのは考えものだ。今期釣れた茶の32㎝は煮て食ったのだが,やはり大味であった。この場合,「煮付けがいい」のではなく,「煮付けが妥当」なのである。いくら茶メバルとはいえ,煮て本当に旨いのは尺以下だ。特に25~28㎝あたり。
昨年は年末にかけて,尺前後が結構続いた時期があった。オカズ優先なのでほかになければ持ち帰り食べるが,大きいのが釣れて,釣り人としてはウレシイ心理もある反面,実はいささか複雑な心境である。おのずから,そのような時期のそのような場所では,あまり釣らないようになる。メバルは尺越えまで10年以上かかるといった事実もあるが,やはり最高に旨く食べようと思えばこそだ。今日もこの時期,せっせと中判を追っかけている。
少しずつ,青が混じり始めた。夏になって,この大判を数枚釣ったら,晩秋までお休みだ。
ここ1ヶ月以上,相変わらず冷蔵庫のメバル在庫状況に応じていくつかの漁場をのぞきに行っているが,小さいほうでも20㎝前後,ほとんどが25㎝前後で中には尺手前も。1回もスカがない。
そもそもこんなに釣れ続くことは珍しい。潮の中ないし縁辺分にたむろして小魚を狙っているメバルの食い気はすごい。今年は餌生物の種類と出現傾向,蝟集と分散が例年と若干異なるためか,このような索餌形態が多いように感じる。根に付いている連中であれば,大きいのから順に釣っていき,次の群れが入ってくるまでにひと息入るものだが,潮付きは,条件さえ合えば毎日釣ってもおかわりが入って来る。潮に居付けるだけの体力をつけた者から順次加入,といったところだろう。餌の群れが大きいほど,また,その群れをまとめる潮目や湧昇流が長く横たわるほど,より広範囲からメバルを集めてくれる理屈だ。風向きや潮によってスポットまでの距離や方向,メバルの深度等は日並みで変わるものの,必ずどこかに居る,というのが現在の状況だ。はてさていつまで続く事やら,経過に観察を要す。
ということなので,沢山釣ってもきりがない。独りで行くときには3尾釣ったらさっさと帰ることにした。オカズさえ獲れればあとはそっとしておく。
ところで,最近学会でも常識となりつつあるメバルの3型(赤・黒(青)・茶)であるが,私がかかわっている場所でも時期的に型の組成に変化が見られてオモシロイ。現在に続く荒食いが始まったのが4月上旬で,その時は例年になく25㎝級の大きな赤が2割,居残りらしきソコソコの茶が8割といった構成だった。この頃はヘチのワカメ林の中から良型が目の前で飛び出すような見釣りが続いていたが,下旬に入り,赤はどこかへ去り(おそらく磯場に繁茂するガラモ場に),茶はここを離れて沖目の餌床に付くようになった。しばらくは夜にはヘチに戻ってくる部隊もいたようだが,4月下旬に入り,いわゆる青が混じるようになると,ヘチをねぐらとする部隊は極端に減り,沖目に散開,餌などの条件によっては集束する。胃内容物も,エビ等甲殻類から小魚に変わった。これが更に進むと,例年並みであれば,夏には青の中~大判が暴れまくり,周辺で小~中の茶とチビ赤が混じり合って遊ぶのであるが,今年はどうなるか。
さて,これらの変化に呼応して,それぞれの型ごとの体型や脂の乗り,肉質なども当然変化していく。このへんが,大変味わい深い。
とうわけで前置きが長くなったが,今回はメバルの3型とその味の考察。
メバルを釣っておられる皆さんも,どうも色カタチで味が違うようだとお気づきの方が多いと思う。そこでこんな表をまとめてみた。メバルの3型の出現時期,サイズ,および調理方法でみた食味評価である。ここ2年間の海の急激な変化によって少々傾向が変わってきている要すだが,だいたいこんなところだと感じている。メバルは概ね20㎝を境に肉質が変わるので,分けて記載した。
なお,食味で×をつけては魚に申しわけないので「△」にとどめおいた。また,来遊状況についてはあくまでも境港港湾エリアが主体であることをおことわりしておく。
この表に加え,各型の形態(プロポーション)および時期的な釣れ方の変化などを勘案し,味覚的視点からみたメバルの分類型の特徴をまとめると,およそ次のよう。
【赤】
港湾付近への滞留期間が短く,かつ小型が主体。港湾部へはワカメ林などの海藻類を拠り所として来遊するので,これが消滅すれば,よそへ向かう。他の2型に比して味が繊細で身が薄く,刺身や焼き魚では十分に味わえない。10㎝前後の小型個体は春に雨後の竹の子の如くわき出すので「竹の子メバル」と呼ばれるが,この時期は味がたよりない(標準和名のタケノコメバルは,最近,ベッコウゾイと呼ばれている)。
晩春の一時期,シラスを食い始めるエリアの20㎝前後のものは,煮魚にして佳味。濃い口醤油や砂糖を用いた田舎煮でも悪くはないが,3型中最もしっとり繊細な肉質であるため,昆布ダシに薄口醤油および少量の酒・ミリンを吸い物程度に調味した下地で静かに煮る「沢煮」が適す。また,3型中最も臭みが薄いので,沢煮を冷たく冷やして下地と共に味わう“冷製”も品がよい。
いずれにせよ,最適サイズの20㎝前後は,市場には揚がるものの,境港の港湾メバル釣り師には,ちょいと縁が薄い。
【黒(青)】
他の2型に比して,体高に対して体長が長く尾びれが大きいため,相対的に体の後半が痩せているように見える。これは,高速回遊して小魚を追い回す生態に適している。身の厚みは他の2型の中間くらいだが筋肉質。
晩春,ワカメ林が枯れ始める頃から接岸が始まり,次第に個体数を増す。餌が沖目にないときには構造物にも定着するが,他の2型ほど執着せず,夏のある時期が過ぎると一斉にいなくなる。
春の小型のものは問題ないが,夏が近づき大型が釣れだすと,これが悩ましい。磯臭さこそないものの皮が固く,煮てもブリンと反り返りゴム質,焼けば身との相性が悪い。脂が乗ってもこの傾向は変わらない。身肉のほうも,3型中最も硬く,加熱してもしっとりせずにバラバラだ。焼いても煮てもこの傾向は変わらない。
ではどうするかと言えば,刺身に限る。皮をつけたまま湯シモとし,氷水にとったのを削ぎ切りにしてワサビ醤油でもよいし,肉を薄く削ぎ,湯引いて千切りにした皮と共にポン酢で食べるのもよい。夏の風情だ。皮の薄い茶メバルでは,湯引けば皮がはがれてしまうし歯ごたえに欠ける。
また,青メバルは肉が硬いだけあって3型中最も日持ちが良く,3枚におろしてペーパーとラップにくるんでおけば,1週間でも身がしっかりしたままである。従って,尺前後の青メバルが1枚あれば,数日間にわたって夕暮れの晩酌オカズに困らない。
【茶】
他の2型,特に青は専ら索餌目的で港湾に回遊するのに対し、茶メバルの集中的な接岸は産卵が主な動機のようである。晩秋から本格的な来遊が始まり,産卵を経て分散する。3型中で最も環境適応能力が優れており,春の頃は海中林で赤メバルと,初夏には沖目で青メバルとの混在も多く見られる。例年の傾向として,成熟個体の接岸,産卵,回復,小型個体の成長,分散,をサイクルとしているが,変則的に大型個体が構造物を拠り所として長期にわたって居残る場合も散見する。
3型中,味覚上,また調理法上,最もバランスが良く,かつ汎用性が高いのがこの型だと思う。刺身ならば冬場に身が締まり脂が乗り,厚めに削ぎ切った飴色の身にははプツッとした気持ちのよい食感と穏やかな甘味がある。この意味において刺身に適すはせいぜい20㎝チョイまでで,25㎝を越えると刺身の小味は消える。そうなれば焼くか煮るのがよいが,焼いて旨いのは25㎝前後までである。いわゆる尺手前や尺上は大味になるので,若干旨みを加えてやる必要があるため,煮,或いは蒸すのが適している。煮・焼きの旬は,冬の生殖巣が未熟の時期と,晩春の回復後の2回訪れる。
本種はホントにありがたい。ほぼ周年獲れる上に近場で釣れる数も多い。時期ごとに,旨いサイズが変わり,ちゃんと適した調理法が存在する。尺に近づいても,青メバルほど味が荒れるわけでもなく,皮も硬くならず,しっとりした肉質と,しっかりした皮の味に一体感がある。
それに・・・。ここでは刺身・焼き・煮と代表的な調理法のみを挙げてきたが,実はこの茶メバルには,どうしても欠かせない,季節限定の料理があるのだ。それは「天ぷら」だ。
なーんだと言う事なかれ。
ちょうど山にコゴミ,タラの芽,ウドなどが出てくるころ,この時だけレギュレーションを18㎝から2㎝ほど下げる。スマンスマンとつぶやきつつ下げる。これを,そこそこ数を釣り,面倒でも3枚におろし,腹骨をすき,皮をひいておく。中骨はとらなくてよい。皮をつけたままでもそれはそれで香ばしくはあるのだが,この時ばかりは雑味なく味わいたいので皮はとる。
まずきれいなサラダ油で山菜類をスバヤク揚げたのち,その鍋にごく少量のゴマ油をたらし,それでカラリとメバルを揚げる。片身で1枚。少々強火でカリン,と揚げる。
単なる白身ではない。きめ細かくキューッと歯にまとわりつくようで,噛めばじんわりと甘味,その味を懸命に追いかけようとする刹那ののち,サラリと解けてノドに消え落ちてゆく。もどかしくて次の一切れに箸をのばしてしまう。単なる淡泊に非ず,ただならぬ淡味である。淡味なれど滋味である。引き際が絶妙で,知らずして引きずり込まれる味だ。
この味わいは中~大のサイズでは,まず出ない。大判を切り身にして揚げても同じ味にはならない。要は小サイズの茶メバル特有の肉質なのだ。
私にとっての春告げ魚は,これに尽きる。この短い期間だけ,毎年これを数回ヤル。メバルだけ揚げても雰囲気が出ないし,かといって他の野菜と揚げてもピンとこない。山菜と若メバル。春の天恵である。
**************************************
こうして書き綴り振り返ると,メバルの3型は,実に上手に棲み分けしており,時期・サイズで空間の共有と分離をおこなっている。そして,これに伴い食味の上でも交代があり,常にいずれかの型が何らかの調理法で賞味に値するしくみとなっている。天の采配とはこのことだ。
釣れる魚のサイズのことを言えば,釣りの指向性にもいろいろある中,私は完全に味覚第一,かつオカズ確実確保,必要十分量漁獲,といったスタイルである。その時期に応じて一番旨い種類とサイズが適度に釣れてくれればよい。それを選んで釣ろうとするから,それはそれでアレコレ頭を悩ます。
こんなだから,時折,意に反して季節はずれの青の尺物などが釣れると,当惑する。釣れたぜと自慢はするけれど・・・。
茶メバルであっても大きすぎるのは考えものだ。今期釣れた茶の32㎝は煮て食ったのだが,やはり大味であった。この場合,「煮付けがいい」のではなく,「煮付けが妥当」なのである。いくら茶メバルとはいえ,煮て本当に旨いのは尺以下だ。特に25~28㎝あたり。
昨年は年末にかけて,尺前後が結構続いた時期があった。オカズ優先なのでほかになければ持ち帰り食べるが,大きいのが釣れて,釣り人としてはウレシイ心理もある反面,実はいささか複雑な心境である。おのずから,そのような時期のそのような場所では,あまり釣らないようになる。メバルは尺越えまで10年以上かかるといった事実もあるが,やはり最高に旨く食べようと思えばこそだ。今日もこの時期,せっせと中判を追っかけている。
少しずつ,青が混じり始めた。夏になって,この大判を数枚釣ったら,晩秋までお休みだ。
2007年05月08日
続・塩煮の世界
塩煮が簡易かつ滋味なる料理法である点,前回述べた次第。
そしてシンプルなものほど使い手に応じて様々に応用が利く。その点,料理も釣り道具もすべからく同じと思う。
過日,メバルの塩煮道にはまり込んでおられるイカロック氏の前に,次なる課題出現。それは“塩煮にもいろいろバリエーションがある”ということ。
世界の主たる料理を和・洋・中とおおまかに分類したとき,用いる素材の種類でみると,意外と似たようなものを使っていることに気づく。では何が違うのかと言えば,素材から出る旨み成分が共通であるとすれば,あとは素材の組み合わせ,中でも素材の味を補うために用いる主たる調味料,それから“香味”と“油脂の風味”の違いが最も大きいと思われる。これがひとつのカギとなる。
塩煮はその名のとおり塩水,それと少量の酒によって魚の旨みを引き出したもので,それ以外の風味は長ネギとサラダ油であり,これら調味料は魚の味を損なわず,かつ過不足のない役割を果たしてくれる。これを「和」,とするならば,洋や中との関係はどうなるのか,塩煮が化けるとはどういうことなのか、というのが今回のお題。理屈はこれくらいにして実践です。
●「洋」の塩煮
(1) 魚の下処理は塩煮に準ず。万事これを怠ってはいけない。
(2) フライパンにオリーブ油を若干多めに入れ,火を入れる前に厚めにスライスしたニンニク数片および種を抜いた唐辛子1本を投じ,弱火で加熱。辛味は唐辛子を熱する時間で調節する(油の味見も大切)。ニンニクは両面きつね色になったら小皿に取り出しておく。
(3) 火を中火に上げメバルの表・裏の順に焼き目をつける点も塩煮に準ず。表を焼き終わった時点 で,黄パプリカ,ピーマン等をメバルの周囲で炒め始める。
(4) メバルの両面を焼き終えたら,強火にして酒を投入し,蓋。アルコールが飛んだら蓋をとり塩煮と同濃度の塩水を注ぎ,粗挽きコショウを少々。ここでとり置いたニンニクスライスを戻す。
(5) 再度沸いたところで,トマト適量個数を“粗くすり下ろして”加える。竹製の「鬼おろし」があれば用いて最良。沸いたらアクをとる。
(6) 煮加減も塩煮に準ず。最後にセロリの葉,もしくは三つ葉を刻んだものを振りかけ,なじんだら火を止める。スープを飲みつつ食べるのがいいので,スプーンを添えることをお忘れなく。
さて,以上を見れば,あれあれ!いわゆるイタリーの“アクア・パッツァ”ではないか,と思い当たる方がおられて当然と思う。そこはそれ,本品はあくまでも“和”たる塩煮から派生したものであるから,味のスジは同じでも風味が少々異なる。パンだけではなく白いご飯にも合う。これは,食べていただければわかること。
アクア~も家庭料理なので,作り方もいろいろであるが,ここでご紹介したスタイルの特徴は,旨みはそのままに風味が爽やかであること。本場モノも大変おいしいが,いささか重たい。逆に,アチラ慣れした方には物足りないということもあろうが、当家の要点は以下の如し。
①ニンニクは途中で取り出し後で再度戻すことにより,香味と香ばしさのみ用いることができる。
②使用する酒はワインではなく日本酒を用いることにより,酒の酸味を控える。
③甘味の強いプチトマトやドライトマト,或いはトマトピューレなどは用いず,大型トマトを生ですり下ろ して加える。
③香辛料として通常用いるバジルやオレガノ等は入れず,香味はニンニク・黒コショウとセロリないし 三つ葉程度とする。
では次に,中国大陸に赴きますか。
●「中」の塩煮
(1) 魚の下処理は塩煮に準ず。ゆめゆめこれを怠ってはいけない。
(2) フライパンにゴマ油を入れ,皮付きショウガのスライス数片を投じ,弱火に点火。香りが立ったところで長ネギの青い方から半分をみじんに切ったものを投入し,軽く炒める。
(3) 長ネギの香りが立ったところで,火を中火にしてメバルを入れ,表・裏と焼き目をつける。そして酒入れて蓋。アルコールが飛んだら塩水を加え,煮加減を料る。この一連の工程,全て塩煮に準ずる。
(4) 煮上がり直前にゴマ油ごく少量をメバルに直接たらし,火を止める。
(5) 残った長ネギの白い方を5㎝ほどに切りそろえ,芯を抜いてタテに極細に刻んで,水にさらして水気を切る。いわゆる白髪ネギ。そして,ショウガの皮を剥き,針に刻んで水にさらして水気を切る。いわゆる針ショウガ。これを,器に移した魚の上に,ネギたっぷり,ショウガ適量,の順に盛りつける。これは,ネギとショウガを熱いスープの中に崩し入れ,ほぐした身と共に浸しながら食うのがスバラシイ。
さて,以上を読めば,アレね!いわゆるチャイナの“清蒸(チンジャオ)”??,半疑問系でおっしゃられても,この場合は,いいえ全く違いマスとお答えするしかない。ご覧のとおり蒸していない。
第一,恐れ多くも中国大陸最強の魚料理であるチンジャオは,本格の料理店であれば,これ専門の達人が一日中それのみの任に徹し,魚のサイズ・質,調味,蒸し加減に至るまで,全神経を針のようにして蒸し上げるという、たいした料理なのである。そこでまたまた当家としては,「本品はあくまでも塩煮から派生したものでありますから云々,」などと述べるのみ。
しかし,食べてもらえばわかるが,なかなかいい線をイッテるのである。かの蒸し魚料理のように神経をとがらかすことなく,極めて短時間で,別の、近い味を味わえる,というのは言い過ぎか。風味の要件は満たしている。試しに,かの料理に専ら用いるデカ口の魚=ハタ類,マハタ(ホンカナ)やアオハタ(キカナ),キジハタ(アカミズ)なんかで作ってみると,これがイケルのである。
→ ただし,決定的なことが・・・
● フライパンに入れて蓋できないサイズの魚は無理。かといってちょん切るのは惜しい。
● 魚が大きいと,直火では火の通りにムラが生ずる。
・・・ですから,小さいキジハタなど釣れた時には,お手軽に,ぜひ。
総じて,洋や中から和には化けにくい。が,和から洋や中テイストへの移行は,その構成要素さえ押さえれば比較的容易である。これは和の世界がに素材の持ち味を優先していることの証であろうと思う。従って,たとえば「韓」はどうか(ゴマ油,大葉・ニンニク・辛・味噌など),「タイ」はどうか(サラダ油,甘・辛・酸+香味),というように,世界の料理と芋ヅル式に広がっていける。どこを旅してもいろいろできる。構成要素とそれらの加減。順序とタイミング。これだけでもいろいろできる。最初は似て非なるものであっても,研鑽すればしただけ独自のホンモノとなる。
もっとも,最近の創作料理なんてのにマトモなものに出会ったためしがない。趣味の延長で、古今東西の味の系譜を逸脱した独善的ママゴトのように見える。プロというからには基礎と基本は一度はちゃんとカラダに憶えさせないといけない。草書の前には楷書の練習が必要ではないか。なんてのは余談。
まあ,だまされたと思って、塩煮と真剣に遊んでみてはいかがでしょうか。
おもしろくて旨いですよ!
そしてシンプルなものほど使い手に応じて様々に応用が利く。その点,料理も釣り道具もすべからく同じと思う。
過日,メバルの塩煮道にはまり込んでおられるイカロック氏の前に,次なる課題出現。それは“塩煮にもいろいろバリエーションがある”ということ。
世界の主たる料理を和・洋・中とおおまかに分類したとき,用いる素材の種類でみると,意外と似たようなものを使っていることに気づく。では何が違うのかと言えば,素材から出る旨み成分が共通であるとすれば,あとは素材の組み合わせ,中でも素材の味を補うために用いる主たる調味料,それから“香味”と“油脂の風味”の違いが最も大きいと思われる。これがひとつのカギとなる。
塩煮はその名のとおり塩水,それと少量の酒によって魚の旨みを引き出したもので,それ以外の風味は長ネギとサラダ油であり,これら調味料は魚の味を損なわず,かつ過不足のない役割を果たしてくれる。これを「和」,とするならば,洋や中との関係はどうなるのか,塩煮が化けるとはどういうことなのか、というのが今回のお題。理屈はこれくらいにして実践です。
●「洋」の塩煮
(1) 魚の下処理は塩煮に準ず。万事これを怠ってはいけない。
(2) フライパンにオリーブ油を若干多めに入れ,火を入れる前に厚めにスライスしたニンニク数片および種を抜いた唐辛子1本を投じ,弱火で加熱。辛味は唐辛子を熱する時間で調節する(油の味見も大切)。ニンニクは両面きつね色になったら小皿に取り出しておく。
(3) 火を中火に上げメバルの表・裏の順に焼き目をつける点も塩煮に準ず。表を焼き終わった時点 で,黄パプリカ,ピーマン等をメバルの周囲で炒め始める。
(4) メバルの両面を焼き終えたら,強火にして酒を投入し,蓋。アルコールが飛んだら蓋をとり塩煮と同濃度の塩水を注ぎ,粗挽きコショウを少々。ここでとり置いたニンニクスライスを戻す。
(5) 再度沸いたところで,トマト適量個数を“粗くすり下ろして”加える。竹製の「鬼おろし」があれば用いて最良。沸いたらアクをとる。
(6) 煮加減も塩煮に準ず。最後にセロリの葉,もしくは三つ葉を刻んだものを振りかけ,なじんだら火を止める。スープを飲みつつ食べるのがいいので,スプーンを添えることをお忘れなく。
さて,以上を見れば,あれあれ!いわゆるイタリーの“アクア・パッツァ”ではないか,と思い当たる方がおられて当然と思う。そこはそれ,本品はあくまでも“和”たる塩煮から派生したものであるから,味のスジは同じでも風味が少々異なる。パンだけではなく白いご飯にも合う。これは,食べていただければわかること。
アクア~も家庭料理なので,作り方もいろいろであるが,ここでご紹介したスタイルの特徴は,旨みはそのままに風味が爽やかであること。本場モノも大変おいしいが,いささか重たい。逆に,アチラ慣れした方には物足りないということもあろうが、当家の要点は以下の如し。
①ニンニクは途中で取り出し後で再度戻すことにより,香味と香ばしさのみ用いることができる。
②使用する酒はワインではなく日本酒を用いることにより,酒の酸味を控える。
③甘味の強いプチトマトやドライトマト,或いはトマトピューレなどは用いず,大型トマトを生ですり下ろ して加える。
③香辛料として通常用いるバジルやオレガノ等は入れず,香味はニンニク・黒コショウとセロリないし 三つ葉程度とする。
では次に,中国大陸に赴きますか。
●「中」の塩煮
(1) 魚の下処理は塩煮に準ず。ゆめゆめこれを怠ってはいけない。
(2) フライパンにゴマ油を入れ,皮付きショウガのスライス数片を投じ,弱火に点火。香りが立ったところで長ネギの青い方から半分をみじんに切ったものを投入し,軽く炒める。
(3) 長ネギの香りが立ったところで,火を中火にしてメバルを入れ,表・裏と焼き目をつける。そして酒入れて蓋。アルコールが飛んだら塩水を加え,煮加減を料る。この一連の工程,全て塩煮に準ずる。
(4) 煮上がり直前にゴマ油ごく少量をメバルに直接たらし,火を止める。
(5) 残った長ネギの白い方を5㎝ほどに切りそろえ,芯を抜いてタテに極細に刻んで,水にさらして水気を切る。いわゆる白髪ネギ。そして,ショウガの皮を剥き,針に刻んで水にさらして水気を切る。いわゆる針ショウガ。これを,器に移した魚の上に,ネギたっぷり,ショウガ適量,の順に盛りつける。これは,ネギとショウガを熱いスープの中に崩し入れ,ほぐした身と共に浸しながら食うのがスバラシイ。
さて,以上を読めば,アレね!いわゆるチャイナの“清蒸(チンジャオ)”??,半疑問系でおっしゃられても,この場合は,いいえ全く違いマスとお答えするしかない。ご覧のとおり蒸していない。
第一,恐れ多くも中国大陸最強の魚料理であるチンジャオは,本格の料理店であれば,これ専門の達人が一日中それのみの任に徹し,魚のサイズ・質,調味,蒸し加減に至るまで,全神経を針のようにして蒸し上げるという、たいした料理なのである。そこでまたまた当家としては,「本品はあくまでも塩煮から派生したものでありますから云々,」などと述べるのみ。
しかし,食べてもらえばわかるが,なかなかいい線をイッテるのである。かの蒸し魚料理のように神経をとがらかすことなく,極めて短時間で,別の、近い味を味わえる,というのは言い過ぎか。風味の要件は満たしている。試しに,かの料理に専ら用いるデカ口の魚=ハタ類,マハタ(ホンカナ)やアオハタ(キカナ),キジハタ(アカミズ)なんかで作ってみると,これがイケルのである。
→ ただし,決定的なことが・・・
● フライパンに入れて蓋できないサイズの魚は無理。かといってちょん切るのは惜しい。
● 魚が大きいと,直火では火の通りにムラが生ずる。
・・・ですから,小さいキジハタなど釣れた時には,お手軽に,ぜひ。
総じて,洋や中から和には化けにくい。が,和から洋や中テイストへの移行は,その構成要素さえ押さえれば比較的容易である。これは和の世界がに素材の持ち味を優先していることの証であろうと思う。従って,たとえば「韓」はどうか(ゴマ油,大葉・ニンニク・辛・味噌など),「タイ」はどうか(サラダ油,甘・辛・酸+香味),というように,世界の料理と芋ヅル式に広がっていける。どこを旅してもいろいろできる。構成要素とそれらの加減。順序とタイミング。これだけでもいろいろできる。最初は似て非なるものであっても,研鑽すればしただけ独自のホンモノとなる。
もっとも,最近の創作料理なんてのにマトモなものに出会ったためしがない。趣味の延長で、古今東西の味の系譜を逸脱した独善的ママゴトのように見える。プロというからには基礎と基本は一度はちゃんとカラダに憶えさせないといけない。草書の前には楷書の練習が必要ではないか。なんてのは余談。
まあ,だまされたと思って、塩煮と真剣に遊んでみてはいかがでしょうか。
おもしろくて旨いですよ!
2007年05月08日
塩煮の世界
ようやくノロノロと始動。
のっけから食う話で恐縮です。
この借家を建ててくだすったイカロックさん,最近,塩煮に熱く傾倒しておられるようで。
たしかに,それほど簡易でかつしみじみと旨い料理だと思う。簡易ゆえに各人ごとの味があり,また,安定した味になるには経験を要す奥深さがある。
今回はこの料理の背景を含め,いちどおさらいをしておこうと思う。この内容は,片親である釣り天狗さんの掲示板に以前投稿した内容の増補版である点,あしからず。
日本における「塩煮」は、大別して2つ。
Ⅰ. 沖縄郷土料理である「マース煮」(マースとは塩のこと)→これは元来、獲りたての魚を海水で煮た浜料理が原型。
Ⅱ. 長崎・熊本を中心とした九州地方の郷土料理である「塩煮」→これは、あらかじめきつく塩をして寝かせておいた魚の旨みと塩気を活かした吸い物。ジャガイモやタマネギを入れることが多い。かつて保存目的で塩をした魚を使ったのが原型。同様な手法は、塩サバの塩気で大根を煮た「船場汁」、北方で塩したタラを用いた「じゃっぱ汁」、或いは三陸の「三平汁」などに散見される。
このうち,ご紹介するのは、Ⅰ.をより内地の口に合うようにアレンジしたものです。では勘所を一手。Ⅱ.についてはまた後日。
①メバルの鱗、鰓、内臓をとり、内外の水気を拭いておく。
このとき、以下に注意するとよろしい。これによって、生臭さを低減し、強火で煮立てたときの身崩れを防ぎます。
●鱗は細かいところまでとること
●鰓をとるときに、胸とアゴのつながりを切らないこと(煮たときの首折れを防ぐ)
●内臓をとるときは、腹の真ん中から切らず、体側の右側にかくし包丁を入れ、そこから取り出すこと (腹身の崩れを防ぐ)。
●腹の中の背骨沿いに固着している血液および腎臓は歯ブラシで取り除いておくこと。
●身に入れる切れ目は骨に到達する程度に、長く斜めに1本のみとすること(バッテンに入れると身が 崩れる)
●一日以上冷蔵庫に保存する場合は、全てのヒレをハサミで切り取り,基地員ペーパーとラップで包 んでおく(ヒレは雑菌が多いので臭みの原因となる)
②長ネギは3~5㎝ほどに切っておく(切る長さによって味わいが変化するところがオモシロイ)
③ボウルの水に粗塩を溶き、濃いすまし汁程度の塩水に加減する。
④フライパンにサラダ油をひき中火で熱し、まず先にメバルの左側(盛りつけた時に表になる側)を下にして焼き目をつけたら、ひっくり返して右側を同様に。同時に長ネギにも焼き目をつける(→左側を焼き終わったあたりから長ネギを入れ、箸で返し焼き目をつけながら右側を焼くと丁度よい。要は、メバルの裏・表・長ネギの焼き目が、同時に仕上がるよう、入れるタイミングを調節するのです)。
⑤軽く焼き目がついたら、強火にし、コップ半分~1杯くらいの日本酒を注ぎ、すかさず蓋をする。
( 注意!→酒が沸騰しているときにいきなり蓋をとると,アルコールに引火します。そこで,アルコールが飛んだ加減を見るときには,蓋を一瞬少しだけ持ち上げてスバヤク蓋を戻すときに出るわずかな湯気を嗅いで,酒臭さが飛んだら良しとする。)
⑥アルコールが飛んで,メバルのシッポあたりの肉が反り返ったら蓋をあけ、作り置いた塩水をメバルの高さヒタヒタまで注ぐ。甘めがお好きな方は,煮立ったらミリンをごく少々。
⑦メバルの切れ目を入れたところの身が反って骨から浮いたら火を切ってひと呼吸置き完成。以上、必殺15分勝負です。
この料理はショウガなどを使わないので純粋な魚の味を感じますが、では、何によって臭みをとっているのか ↓。
血液および水分に臭み成分は溶けていますので、背骨の血合いをこすり落とす。調理前に水気を拭いておく。焼き目の香ばしさで臭みをマスクし、そして、強火にした後に酒を一気に注ぎ、旨みを込めると共にアルコール分で臭み成分を分解。塩水を注いで身を引き締め、終始強火でスバヤク炊き上げることによって煮くずれを回避する。
すなわち、①水、②塩、③酒、④熱、の要素をいかにタイミング良くコントロールするか、ということなのであります。
いずれにせよ,“考えながら”,“場数を踏む”ということでしょう。釣りも同じですねえ。
さて,この塩煮。メバル以外ではどんな魚に適するのであろうか。ぜひいろいろ試していただきたい。けして白身魚がいいといった単純な事ではない。魚の種類はもとより,サイズによっても味わいが違います。たとえばこれからの季節,イサキ,とか~,アジ,とか~,いいようですよ! タイは?(タイは意外に合わないんだな,これが)。加熱すると身がしっとりするヤツがいい。
のっけから食う話で恐縮です。
この借家を建ててくだすったイカロックさん,最近,塩煮に熱く傾倒しておられるようで。
たしかに,それほど簡易でかつしみじみと旨い料理だと思う。簡易ゆえに各人ごとの味があり,また,安定した味になるには経験を要す奥深さがある。
今回はこの料理の背景を含め,いちどおさらいをしておこうと思う。この内容は,片親である釣り天狗さんの掲示板に以前投稿した内容の増補版である点,あしからず。
日本における「塩煮」は、大別して2つ。
Ⅰ. 沖縄郷土料理である「マース煮」(マースとは塩のこと)→これは元来、獲りたての魚を海水で煮た浜料理が原型。
Ⅱ. 長崎・熊本を中心とした九州地方の郷土料理である「塩煮」→これは、あらかじめきつく塩をして寝かせておいた魚の旨みと塩気を活かした吸い物。ジャガイモやタマネギを入れることが多い。かつて保存目的で塩をした魚を使ったのが原型。同様な手法は、塩サバの塩気で大根を煮た「船場汁」、北方で塩したタラを用いた「じゃっぱ汁」、或いは三陸の「三平汁」などに散見される。
このうち,ご紹介するのは、Ⅰ.をより内地の口に合うようにアレンジしたものです。では勘所を一手。Ⅱ.についてはまた後日。
①メバルの鱗、鰓、内臓をとり、内外の水気を拭いておく。
このとき、以下に注意するとよろしい。これによって、生臭さを低減し、強火で煮立てたときの身崩れを防ぎます。
●鱗は細かいところまでとること
●鰓をとるときに、胸とアゴのつながりを切らないこと(煮たときの首折れを防ぐ)
●内臓をとるときは、腹の真ん中から切らず、体側の右側にかくし包丁を入れ、そこから取り出すこと (腹身の崩れを防ぐ)。
●腹の中の背骨沿いに固着している血液および腎臓は歯ブラシで取り除いておくこと。
●身に入れる切れ目は骨に到達する程度に、長く斜めに1本のみとすること(バッテンに入れると身が 崩れる)
●一日以上冷蔵庫に保存する場合は、全てのヒレをハサミで切り取り,基地員ペーパーとラップで包 んでおく(ヒレは雑菌が多いので臭みの原因となる)
②長ネギは3~5㎝ほどに切っておく(切る長さによって味わいが変化するところがオモシロイ)
③ボウルの水に粗塩を溶き、濃いすまし汁程度の塩水に加減する。
④フライパンにサラダ油をひき中火で熱し、まず先にメバルの左側(盛りつけた時に表になる側)を下にして焼き目をつけたら、ひっくり返して右側を同様に。同時に長ネギにも焼き目をつける(→左側を焼き終わったあたりから長ネギを入れ、箸で返し焼き目をつけながら右側を焼くと丁度よい。要は、メバルの裏・表・長ネギの焼き目が、同時に仕上がるよう、入れるタイミングを調節するのです)。
⑤軽く焼き目がついたら、強火にし、コップ半分~1杯くらいの日本酒を注ぎ、すかさず蓋をする。
( 注意!→酒が沸騰しているときにいきなり蓋をとると,アルコールに引火します。そこで,アルコールが飛んだ加減を見るときには,蓋を一瞬少しだけ持ち上げてスバヤク蓋を戻すときに出るわずかな湯気を嗅いで,酒臭さが飛んだら良しとする。)
⑥アルコールが飛んで,メバルのシッポあたりの肉が反り返ったら蓋をあけ、作り置いた塩水をメバルの高さヒタヒタまで注ぐ。甘めがお好きな方は,煮立ったらミリンをごく少々。
⑦メバルの切れ目を入れたところの身が反って骨から浮いたら火を切ってひと呼吸置き完成。以上、必殺15分勝負です。
この料理はショウガなどを使わないので純粋な魚の味を感じますが、では、何によって臭みをとっているのか ↓。
血液および水分に臭み成分は溶けていますので、背骨の血合いをこすり落とす。調理前に水気を拭いておく。焼き目の香ばしさで臭みをマスクし、そして、強火にした後に酒を一気に注ぎ、旨みを込めると共にアルコール分で臭み成分を分解。塩水を注いで身を引き締め、終始強火でスバヤク炊き上げることによって煮くずれを回避する。
すなわち、①水、②塩、③酒、④熱、の要素をいかにタイミング良くコントロールするか、ということなのであります。
いずれにせよ,“考えながら”,“場数を踏む”ということでしょう。釣りも同じですねえ。
さて,この塩煮。メバル以外ではどんな魚に適するのであろうか。ぜひいろいろ試していただきたい。けして白身魚がいいといった単純な事ではない。魚の種類はもとより,サイズによっても味わいが違います。たとえばこれからの季節,イサキ,とか~,アジ,とか~,いいようですよ! タイは?(タイは意外に合わないんだな,これが)。加熱すると身がしっとりするヤツがいい。